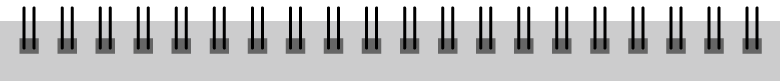私の画材
はじめに
アクアレル画の生命は、透明感のある発色であると言っても過言ではありません。少量の絵の具で発色させるため、画材、特に「絵の具」と「紙」と「筆」には神経を使います。ここではそれらを中心に、私の画材について紹介したいと思います。
1 絵の具
絵の具は、いわゆる透明水彩絵の具を使いますが、水彩絵の具の透明感は、油彩画のように顔料の粒子が油などの透明な媒材で包まれて表現される透明感ではなく、顔料の粒子が紙の繊維の隙間に引っかかった状態で表される透明感なので、顔料そのものの良し悪しが大いに発色に影響します。日本のメーカーからも専門家用水彩絵の具が出されていますが、顔料の良さと純粋性で私はイギリス"Winsor and Newton"社のチューブ入りとハーフパン(半固形)やオランダTarrens社のレンブラント水彩絵の具を使っています。
色数は12色程度で十分です。絵の具にはもともと宝石の美しさがあり、特に薄い色を塗り重ねるアクアレル画においては、色数を多くすると色の濁った作品になってしまいます。また、最近の絵の具は様々な理由から、単一の顔料ではなく、いくつかの顔料を混ぜ合わせて色出しをしているものが多くなってきました。私は、塗り重ねたときに色が濁らないよう出来るだけ単一顔料から作られた色を使うようにしています。絵の具会社で出しているカラーチャートや組成表を参考にするといいと思います。
2 紙
少量の絵の具を多量の水で広げて表現するアクアレル画においては、絵の具と同様、紙の良し悪しが大きく発色に影響します。
日本で手に入る高級水彩紙は、イタリアの「ファブリアーノ紙」やフランスの「アルシュ紙」などがあります。また、フランスの「セヌリエ紙」も程よい発色でとても使いやすかったのですが、製造取り止めということで手に入らなくなってしまいました。
優れた水彩紙は「コットン紙」といって綿の繊維を漉いて作られています。その中でも「ラグペーパー」といって「コットンラグ(木綿のぼろ布)」を細かくほぐして漉き、ゼラチンに漬け込んで滲み止めをしたものは、発色が素晴らしくとても堅牢な紙です。しかし、残念なことに最近この紙を見ることは出来なくなってしまいました。私の手元には、かつて購入したものが何枚か残るだけです。
最近は「コットン100%」紙が手に入る紙では最も良い紙となっています。この紙も丈夫で発色が良く、失敗した時などは、たわしで水洗いしても大丈夫です。また、ファブリアーノ社から「クラシコ50」という「コットン50%」の紙も出ています。これも程よい発色でスケッチなどには使いやすい紙です。
他にも高価な和紙風の水彩紙や、パルプや他の植物の繊維を使った安価な水彩紙も多数出ていますが、絵の具を薄く塗り重ねるアクアレル画には、発色と堅牢さの点から今ひとつのものも多く、相応しいものはなかなか見つかりません。
水彩紙は膠やゼラチンで滲み止め(サイジング)してありますが、「BFKリーブス紙」のような吸水性の版画紙なども、味わいのある表現が出来ます。
3 筆
アクアレル画の筆は水をよく含み、腰が強くしなやかで、先がまとまるものが良いものです。一般に貂毛(セーブル)筆、中でもシベリヤ産のコリンスキーセーブルが最も良いとされています。また、広い面積を塗る場合などは、リス毛の筆も水の含みがよく使いやすいです。最近では安価なナイロン製の水彩筆も質が良くなってきており、使用に耐えるものとなってきました。
4 パレット
専門家用のパレットとして、ブリキやアルミに漆などの白い塗料を塗ってあるものが市販されていますが、私は"Winsor and Newton"社やTarrens社のハーフパンが付いたものや、白いホーローのトレイを使っています。
パレットに出した絵の具は、そのままで水をつければ使えるので、パレットは毎回掃除する必要はありません。
5 その他
・筆洗 学童用の黄色いプラスチック製のもので十分使えます。
・海綿 画面に水を引いたり、絵の具を部分的に落としたり多用途で必需品です。
お茶の水の「文房堂」の筆の軸に海綿が付いたものがとても便利です。
・マスキング液
紙の白地を生かす技法に使います。

〈私の画材〉
左上から
・筆洗、海綿、マスキング液、マスキング用筆洗液、水張りテープ
・パレット付きハーフパン(半固形)絵の具、パレット用トレイと水彩絵の具(ハーフパン、チューブ)
・筆(コリンスキー3本、リス毛2本)、パレット用トレイ
私の技法
はじめに
アクアレル画にはさまざまな技法がありますが、あくまで技法は表現の必要性から使われるべきものです。ここでは代表的で基本的な技法を紹介したいと思います。
アクアレル画の特徴は、なんと言っても透明感と、絵の具と水と紙の微妙な関係で表現された生命感にあります。絵の具にホワイトを混ぜると透明な輝きがなくなってしまいますので、原則として、ホワイトは使いません。白い部分、明るい部分は紙の地の白を使って表現します。わざと余白を残して仕上げる場合もあります。
1 水張り
紙の表裏両面に十分水を含ませ、パネルなどに水張りテープで留めてから描くと、水で紙が波打つのを抑えられて描きやすいです。最近では、四辺を糊で留めたブロック式のスケッチブックも出されており、屋外で描くときなどにはとても便利です。
2 ウォッシュ
最初に水をたっぷり使って色を薄く塗り、紙に絵の具を馴染ませることを「ウォッシュ」といいます。平らに塗る場合もあるし、タッチやにじみで変化を付けて塗ることもあります。基礎となる部分であり、明るい色を使うことが基本です。
セザンヌは最初からタッチを付けて塗っています。アルシュ紙のようにサイジングの強い紙は、最初絵の具が乗りにくいので海綿などを使って水を全体に引いてから塗るといいです。
3 ウェット・オン・ドライ
アクアレル画の原則は「ウェット・オン・ドライ」、つまり下の色が乾いてから上に塗れた色を重ねていきます。重ねることで色が濁らないよう、使う色には十分注意が必要です。筆のタッチを生かしながら塗っていきます。
4 ウェット・イン・ウェット
下の色が乾かないうちに違う色を置き、偶然にできるにじみを生かしながら塗る技法です。繊細な感性が要求されます。また、下の色が生乾きのうちに上から水をたらすと、江戸時代の「琳派」がよく用いた「たらし込み」の効果を出すことが出来ます。
5 ドライブラッシュ
筆の水気を布などでとって、筆をこすりつけるようように細部などを描いていく技法です。荒めの紙を使うと効果が出ます。アンドリュー・ワイエスの得意とする技法です。
6 マスキング
マスキング液でハイライトの部分や紙の白を残す部分をマスクし、上に塗った絵の具が乾いたら、ラバークリーナーでマスキング液をとります。紙の白地を残したり、形をはっきりさせたい場合に使うとメリハリのある作品が出来ます。
7 その他
他にも方解石の粉末を膠で溶いたものを使ってマチエール作りをすることもあります。
始めにも述べましたが、表現があっての技法ですので技法に流されない事が大切です。また、逆説的ですが、絵の具の色数を極力抑えることが色彩豊かで調和のとれた作品を作る秘訣です。