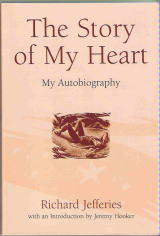
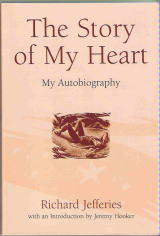
リチャード・ジェフリーズ(Richard Jefferies 1848-1887)
英国の忘れられた実存主義的ナチュラリスト。イングランドのカントリーライフを細密、清新に描写したネイチャーライターとして知られたが、単なる自然の礼讃や田園趣味にとどまることなく、精神と生命の熱烈な探求者であった。
代表作として、The Life of the Fields (1884), The Open Air (1885 「野外にて」),
小説に Bevis (1882), After London (1885) があり、自伝としてここに新しく訳された
The Story of My Heart (1883) がある。
(画像はGreen Books 2002年版)
エポス文学館トップへ
翻訳城へ
| <白波の立つ海の上に、大いなる日輪は燃え、大空の屋根の下で、私は私について自覚する。それは大自然によって私に呼び覚まされた意識である。――思想は更に広大にならねばならないし、大自然に匹敵する概念の大きさを持たねばならないと私は感じる。けれども、大自然は私を満足させはしない。海や太陽や宇宙空間といった、これらの巨大な事象だけでは。私の思想はこれらよりも力強いものであると、私は感じている。私は生命を松明のごとく燃やす。海から照り返す熱い日差しは私の頬を焼く――わが命はわが内に燃えている。心はより広大な生命を求めて、海のように脈打っている。これまで私が知ったどんな思想も、私の心を満たしはしなかった。>
( 「第六章」より ) わが心の物語 リチャード ジェフリーズ 翻訳copyright syuuji kai 2004 < 第一章 > わが心の物語は十七年前にさかのぼる。燃え盛る青春のさ中で、時折り私は心の奥深い思いを強烈にかきたてられたいという欲求に駆られることがあった。私の心には埃が堆積し、深い感情の雨を欲して渇いていた。私の心が乾燥し涸渇していたというのは、棚の上に埃が積もるように、心に積もる塵埃もあるからである。絶えず同じ場所にいて、絶えず同じ環境の中に暮らすことは、身体にとってはおろか、心にとっても良いことではない。一種の厚着した服の様なものが次第に心の回りを取り巻いていく。そうなると毛穴のふさがる鬱陶しさが感じられ、取るに足らない習慣が生活の一部を占めて行き、心は徐々に殻の中に閉じこめられていく。この殻が形成されだすと、私は痛切にそれから逃れたいと願った。重い服を脱ぐようにそれをかなぐり棄て、いま一度新鮮な生命の泉で思う存分喉をうるおしたかった。奥深い思いをかきたてられること――思想の新鮮な空気を深く呼吸すること――これだけが心に健康を与えることができた。 そうした場合に私がよく出かけていった一つの丘[訳注1]があった。そこへたどり着くまでに、ゆるやかな勾配の三マイルの道のりを骨折って歩いていくと、家に居つづけてすっかりめぐりの悪くなった私の血が生き生きとよみがえる思いがした。夏の暖かい日に、そのゆるやかな坂道を登りつめていくことはかなりの根気を要したが、それが鬱屈した気分を取り払ってくれたのである。やがて見なれた日常の光景が視界から去り、見なれない木々や牧草地や野原が現われてきた。私は新しい空気を呼吸し始め、一層新鮮な憧憬に駆られだした。私は丘の草地にたどり着くまで、私のはやる心(soul)、解放を希求している魂(psyche)を押し鎮めていた。私はsoulという言葉に付着してしまっている雑多な意味を避けるために、いつでもpsycheという言葉を使いたいのであるが、それではぎこちなくなる。日常生活という鈍重な舞台から離れ出るや否や、すべての言葉はぎこちなくなるものだ。私は緑の丘自体がそこから始まる草地にたどり着き、足を踏み入れるまでは、わが心、わが魂を押し鎮めていた。 香りの良い短い芝草の丘を登りながら、一歩ごとに私の心は情感の領域を広げていくように思われた。新鮮なあふれる大気を吸うごとに、私の心はより深い欲求を覚えていくようだった。陽の光そのものが、ここでは一層白色に、一層輝いて見えた。頂に着く頃には、私はつまらない境遇や生活の煩い事などをすっかり忘れ去っていた。私は私自身、私自身だけを感じていた。頂には古代の壕の跡が残されていた。その壕の中に降り立って、私は息を静めるためにゆっくりとめぐって行った。南西の方面に壕の外郭が一部崩れて、隙間の出来ている箇所があった。そこからは小麦畑の美しい、緑の丘陵で円形劇場のように隙なく囲まれた、広い平野が見渡せた。それらの丘陵を抜けて、一本の狭い条の様な峠道が南の方面に伸びていたが、その辺りは白い雲が地平を閉ざしている様に見えた。散在する小村や農家は森の蔭になっていたので、私は全く独りであった。 私は完全な孤独の状態で太陽と大地とにまみえていた。草の上に寝転ぶと、私は心の中で、大地や太陽や大気や、遥か視界の外にある遠い海に語りかけた。私は大地の固さを思い、それが私を支えているのを感じた。草のしとねを通して、大地が私に語りかけてくるのが感じられるような気がした。私は空の気流とその澄明な美しさとを思った。気流は私に触れ、それ自身の持つ何かを私に授けていった。私は海に語りかけた。遥か彼方にあっても、私の心の目には見えていた――陸地に接するところでは緑色の、深さの増す沖合いでは紺青の海が。私は海の力強さと神秘と壮麗を我がものにしたいと欲した。それから私は太陽に向かって語りかけた。そのまばゆい光輝と、その忍耐と、たゆむことのない運行に匹敵する魂を欲した。私は上方の青空に眼を転じた。その奥底を見入って、その絶妙な色彩と甘美さとを吸収した。大空の摘み取れない花の藍色は、そこに向かって私の魂を引きつけ、魂はそこに安息を覚えた。清らかな色彩は心の安らぎであるから。すべてそうした物によって私は祈りの心を起こした。私はどんな言葉にも言い表わし難い魂の感動を覚えた。祈りなどと言うものはそれに較べればちっぽけなことであって、この言葉はこの感動を表わす粗末な記号にすぎない。けれども、私はほかに言い表わし様を知らないのだ。 青空にかけて私は祈り、日ごとに明らかにされる新たなエーテル[訳注2]の海である人跡未踏の宇宙空間を突き進みつつ、空をへめぐって行く日輪にかけて祈った。地球を取り巻き流れる爽やかな大気にかけて祈り、岸に打ち寄せ鳴る海と、白波に縁どられた緑の海と、大海原とにかけて祈り、我が足もとの堅固な大地にかけて祈った。それから身辺にたち返り、香りの良いたち麝香草の小さな花に手を触れつつ祈り、すらりとした草の姿に祈り、石灰質の乾いた土くれを手に拾い上げ、指の間からこぼしつつ祈った。土くれと、草の葉と、たち麝香草の花に手を触れながら、地球をめぐる大気を呼吸しながら、海と空とを思いながら、日の光が当たる様にと手を差し伸べながら、心の底からの敬いのあかしとして草の上に倒れ伏しつつ、神よりも限りなく高尚な言い表わしがたい存在にまで触れることができるようにと、私はその様な祈り方をしたのである。 私を高揚させた熱い情感を余すところなくこめて、大地と、太陽や大空と、日光に隠されている星々と、海洋とかわした熱い心の交わりを、余すところなくこめて、――そうした情感の身の震える奥深さは、とても言い表わしようがない――そうした情感をこめて私は祈ったのだ。あたかもこれらの情感がある楽器の、例えばオルガンの鍵盤ででもあるかのように、それを奏することによって私は私の魂の音楽をかなで、その力強い伴奏によって私自身の声を増幅させたのである。 輝き燃える大いなる太陽、堅固にして愛しい大地、暖かな空、すがすがしい大気、海への想い、すべて言い表わし難く美しいものが私を歓喜と陶酔と感応(inflatus)とで満たした。この感応によっても又、私は祈ったのだ。それから私は私自身をかえりみ、私そのもの、私の身体的存在に思いを致した。わが手を差し伸べると、日光が皮膚と真珠色の爪を照らした。私は肉体の美と神秘に思いを致した。また私は遥か六十マイル先にある海原を想像させてくれ、その壮麗を目のあたりに見させてくれる精神について思いをめぐらせた。私はわが内なる実在、魂と呼ばれている意識について思いをめぐらせた。こうした私自身に関することを、私はその分だけ祈りの重さが増すようにと、天秤の皿に投じたのである。肉体と精神と魂の力をかきたて、そこに投じたのである。わが全力をふりしぼった祈りの業において、私は格闘し、苦闘し、苦悶した。この祈り、この魂の感動は、何かに向かうのではなく、それ自体に留まっており、それは一つの熱情であった。私は草の中に顔を隠し、体ごと倒れ伏していた。心のうちの格闘に我を忘れ、恍惚として正体を失っていた。 やや気持が静まると、私は正気をとりもどし、仰向けに寝転がって、陶然とした想いにふけり、憧れで胸をふくらませ、魂のふちからあふれそうな欲求に身をまかせていた。その頃の私は、この状態をはっきりとつかむことも、分析することも、理解することもしなかった。今の私には、当時の私が切実に求めていたものが、心の生活(soul-life)であり、心の本質を広げることであり、心を高められることであり、心の知識で充満されることであったことが分かっている。私はようやく立ち上がり、丘の頂に沿って東に半マイル程歩き、気持を落ち着けてからもとの平凡な日常生活に戻ったのである。たまたま羊飼いがいて、草の上に横たわっている私を見たとしても、彼は単に私が数分の休息をとっているものと考えたことであろう。私は見た目には一切表わさなかったからである。その場に横たわっていた私の内面に、旋風のような熱情が渦巻いていたことを、誰が想像できたであろうか!帰宅した頃には私はすっかり疲れ切っていた。時には私は、そうするのが良いと考えることで、意図的にその丘に登った。又、時にはこの渇望がおのずと私をその丘の上へ駆り立てて行った。大本の感情は同じであったが、それが私に影響する仕方は様々であった。 ある時は、私は芝草に寝転ぶと、先ず空を見上げ、青空の奥底をのぞきこむようにして、目の中が青一色になるまでしばらく見つめていた。それから顔を芝草やたち麝香草に向け、両手で顔の両側を覆って何も見えなくなる様にし、私自身を隠した。頭上の青空を心ゆくまで味わい、昼間のもっとも壮麗な美に感じ入り、そして私には視界のすぐ先にあるように思われた古い、古い海を想像したその後で、私は今度は宇宙そのものの存在もしくは実在の中に思いを潜めていった。私は下に地球の奥深い内部を感じ取り、上に遥かな天空を、太陽や星々の彼方まで感じ取った。更に遠く、星々を越えた宇宙空間に思いを馳せて行き、こうして私が切り離された存在であるという意識を失うと同時に、私は全宇宙の一部であるかに思われてくるのであった。 それから私は芝草とたち麝香草のしとねを通して、奥深い地球の耳に囁きかけ、そうして再び仰いでは、青空に隠された星の宇宙に囁きかけた。私は一瞬のうちに遠くの海を翔りながら、あたかも目のあたりに椰子やココ椰子の木を見、インドの竹林と最果ての南の国の杉林を見た。大海は湖のように島々を点在させて、目の前に広がっていた。それは眼下の円形劇場を思わせる丘陵で囲まれた平野と同じほど、ありありと鮮明に見えていた。 要するに、私は、大海原の壮麗に祈り、堅固な支えである地球に、遥か彼方まで果て知らに広がるエーテルの空間に、年古りた海原の奔放と止むことのない揺動に、星々と未知の宇宙にかけて祈るのであり、すべて私の知る最も力強いものにかけ、在りとは知りつつも何であるとはまるで知れないものにかけて祈るのである。さらに私は、地球よりも、太陽よりも、星よりもはるかに身近な、ほかの何にもまして理想の精神に最も近く似かよった、かの秘められた存在者である私自身の魂にかけて祈る。言葉によってではなく、思いを傾けることによって語りつつ、わが魂は祈る――そうしたものの一つ一つから何事かを得られるようにと、それらのものの一つの精髄を摘みとれるようにと、地球や黄金色の太陽や、光や、白波立つ海から、その秘められた意味をわが心のうちにとらえることが出来るようにと。わが心よ、広がり行け、私は足らぬ者であり、ちっぽけで、蔑むべき存在だ。私は心の偉大さと、精神の輝きと、より深い洞察力と、より広大な望みを欲している。魂の力を私に与えよ、私が得ようと努めているものを,その意志によって実現できるように。 冬になると草の上に横たわることができず、はっきりした思いを表わすことができるほど長くは留まれなかったのであるが、私はやはり何度かその丘に登った。単にその場所を訪れるだけでも、これまで私が述べた心の状態が再現される思いがしたのである。しかし、それは冬のその時ばかりではなかった。 夏には、私は野原へ出かけて行き、木立の幹にもたれ、枝の間からのぞかれる空を見上げながら、そうした思いを心に呼び覚まさせたのである。もし木々が口を利くことができるものなら、何百本という木が、その下で私が魂の感動を覚えたことを証言するであろう。樫の木の太い幹にもたれ、背中にざらざらした樹皮と苔とを感じ、南の方の黄花(cowslip)で黄色く染まった野原の向こうの、なだらかな斜面の森を見つめつつ、私はより深い心の生活への私の欲求に思いふけったのである。あるいはまた、緑の樅の木の下に立って見上げる空は、梢の先でいっそうの青味を増していた。おりしも、蕨の葉はほどけ、山鳩が鳴き、茂みは風に揺れ、晩いトネリコの葉が開き始めていた。形よく丸く茂った楡の下で、サンザシの藪やハシバミの傍らで、到る所で私は心の本質を求めて同じ深い欲求にふけったのだ。あらゆる緑の植物から、日の光から、それら自身は知ることのない内面の意味を汲みとることにより、森が日の光にあふれる様に、私もまた光であふれんことを願ったのである。歩みつつ、苔むした樹の肌に触れ、径に突き出した小枝の先に触れなどするだけでも、この同じ祈りが私の中に甦るここちがした。 夏の長い日足は、牧草地の草を乾燥させ、温めた。私はよく人気のない片隅で、あおむけに長々と寝そべっては、大地の抱擁を感じていた。草は丈高く生い茂って私を隠し、木の枝の影が顔の上で踊った。私は眩しさに半ば両眼をとじて、青空を見上げていた。蜜蜂が私の上で唸り、時たま蝶がよぎっていった。空中にはブンブン鳴る音がし、生垣ではカワラヒワが囀った。夏の日の熾烈な生命―― 一つ一つの草の葉や木の葉が松明であるかのように燃え広がる生命―― の中にいつしか身を没入させて行くうちに、今この陽ざしを肌に温かく感じていながら、渺たる太古に連綿とつらなる地球の生命が感じ取られてくるのであった。昔、昔のこと、南方の国の最も古い砂漠で、セソストリス[訳注3]は己れについて知り、太陽について知った。この陽光が幾時代を隔てて、私とかの過ぎ去った意識とを結びつけていた。日の光が絶え間なく地に降り注いだように、あらゆる時代を通して流れ続けた心の生命を、私の心はあらゆる時代から摂取しようと欲した。熱砂が熱を吸収するように、そのように熱く私は心のエネルギーを吸収したいと欲した。外見は夢想にふけっているかに見えながら、私ははっきりと実在の意識を持ちながら呼吸していた。草の葉や花や、サンザシなどの木々の葉を目にとらえていた。それらの一つ一つが、あたかもそこに口をつけて飲んだ飲み口であるかのように、私はそれらによってより広大な生命を得ているように思われた。キリギリスが鳴いては飛び跳ね、カワラヒワが囀り、黒歌鳥が陽気に笛を吹いた。あたり一面の空気は命でさんざめいていた。私は実在の世界に深く没入して、実在するものすべてにかけて祈ったのである。 幾千もの草のひと葉ひと葉にかけて、茂みや木立の、葉脈と切れこみのある幾百万もの葉にかけて、鳥たちの歌声や紋様のついた翼にかけて、虫たちの羽音や蝶の羽色にかけて、千切れ雲の消えていく暖かく和やかな大気にかけて――私はそうしたものすべてを祈りのよすがとした。いにしえの砂漠でセソストリスが日の光について知った時よりこの方、倦むことなく地上に降り注がれた日光の全エネルギーにかけて、何よりも愛しいギリシャにおいて最初に神々についての夢が織り成された時よりこの方、たくましくも麗しい男女によって生きてこられたすべての人生にかけて、この私にまで連綿として流れつづけて来たすべての心の生命にかけて、私は祈ったのだ。過去にまれ、現在にまれ、そうしたものを凌駕する魂を、そればかりか、そうしたものについての私の理解をはるかに超えたところにある魂をわがものに出来、全生命の充実をわがものに出来るようにと。そうしたものに匹敵するばかりか、凌駕し、わが想像を絶して、更に高く、更に力強い魂を。そうしたもののエネルギーと偉大さと美とをまるごと摂取して、わが内に蓄えることが出来るようにと。わが心が生命宇宙よりも広大であらんことを。 私は日没時の夕焼け雲に祈り、すみれ色の空にほのかに点った一番星に祈った。夜中には四季おりおりの星たちに祈った。ある夜はプレアデス(すばる)に、ある夜は白鳥座、又は青白く燃えるシリウス(天狼星)に、それから雄大なオリオン星座に、赤き星アルデバランに、アルクトゥールス星に、そして北の冠座に。また、時々それを見かけた折には、夜明けをもたらす明けの明星の、ある時は紫紺の空に白金の光を放つ姿に、ある時は東の空に紅の光芒が地平へ広がりゆく時、晴れゆく夏の薄い朝もやにつつまれたその姿に。差し初めたウコン色は、まばゆい蒼穹へと立ち昇っていった。日輪が光の拍動で揺れ動きながら、丘の上に昇った。日の胸は光輝に熱く燃えて波打っていた。その壮麗な日の出の全光景が、溶鉱炉のような激しさと広がりとを帯びた祈りの念で私を満たした。最も深い心の生活、どんなものよりも深い、この目に見える宇宙ばかりでなく、目に見えない宇宙のあらゆる偉大さをはるかに超えた深さを持つ心の生活を、我がものに出来るようにと。今日まで誰も体験したことがないほどの、私自身まるで想像がつかないほどに充実した魂を、所有出来るようにと。 昼の明るい陽光の中でも、夜の漆黒の闇の中でも、等しくこの思いがわが心に沸き起こった。この変わらぬ感動を強めようとして、私が利用しなかったよすがが何かあるだろうか? 訳注1.ジェフリーズの生まれ育ったWiltshire州の小村Coateの農場の近くにあるLiddington Hillのこと。 訳注2.当時の物理学では、宇宙空間はエーテルと称される微妙な粒子からなる媒質で満たされていると考えられていた。マイケルソン=モーレーの実験でこの仮説はくつがえされた。 訳注3.Sesostris=古代エジプト第十二王朝の王。第一世(kheperkare)は前1971生―1926没。三世まで知られる。 <第二章> 時おり私は丘陵地にある、とある人目につかない、ひっそりとした、深く狭い谷間へ出かけて行った。空は谷の一方の側から他方へ、緑の壁で支えられた屋根のように架け渡されていた。谷の上の縁沿いに広がる小麦畑では、雀がさえずっており、その鳴き交わす声は燕のさえずりのように空から降ってきた。ほかに物音とてない。伸びかけた短い草が、暑熱によって灰色に干からびていた。その狭い谷から見上げる空には、あたかも手でそこに置かれたかの様に、太陽が懸けられていた。絶え間なく燃える日の光は、谷の裾の草の上に照り映え、そこにいる私の中へも想念が燃え入ってきた。どれ程の長い年月を、どれ程の長い年月の繰り返しの間を、どれ程の長い年月の繰り返しの積み重ねの間を、太陽はこのようにしてこの谷間を照らしてきたのであるか?谷間が造られて以来、どれ程の長きに渡ったのであるか?すでに退いていった巨大な自然力によって、丘陵地の脇腹に溝のようにえぐられ、形づくられて以来。谷間が造られた時の自然の営みを照らした太陽と一人向き合いながら、私は時を越えて、鱗木や、空を飛ぶ爬虫類や、海の白波をけたてて泳ぐ恐竜や、象の倍もある陸生の巨大な生きものやの跋扈した太古を思い描き、生命全体の曲がりくねった連続に思いを馳せた。わが傍らを飛ぶ蜻蛉は、その時代の石の上に印された飛ぶ虫からの連綿とした系統に連なるのである。その莫大な時の流れが、小舟の下に巻き起こるうねりのように私を高揚させた。幾時代もの波浪が押し寄せるにつれ、私の精神もまた高まっていく思いがした。精神は幾多の時代の活力を吸収して、力強さを覚えた。そうした時の流れとその活力のすべてにかけて、私は祈った――それの知性的部分である理念と思想とを、わが心に受け取ることが出来るようにと。精神は過去と現在の間を、瞬時にして杼(ひ)の如く行きかった。 驚嘆すべき過去であふれるほどに満たされた私は、また驚嘆すべき現在を感じとっていた。その一日、私が息をしているその瞬間、その谷間でのその時の一秒は、過ぎ去ったすべての時間に劣らず驚異的で壮大であった。今というこの瞬間は驚異であり、壮観であった。今というこの瞬間は、とてつもなく驚嘆すべきものであった。今というこの瞬間は、私を取り巻く宇宙において表現されているすべての思想、すべての理念、すべての魂を私に与える。さらに多くのものを我に与えよ。と言うのは、過去と現在における限りない宇宙も地上のものにすぎないからである。地とは全くかけ離れた知られない魂を我に与えよ。それについて私が知ることはただ、私が地面に触れたり、陽の光が私の手を照らしたりするとき、そこには存在していないということだけである、そのようなものである魂を。それ故に、心は地上から逃れようとして、宇宙へ目を注ぐ。あらゆる時代と、それらを貫き流れる陽光と、現在というものが意味することのすべてを心にかけ、私はその深い谷間で思索し、祈ったのである。 時として私は、奥まった所にある泉へ行き、掌にその清らかな水を汲んで喉をうるおした。光そのものが溶けたかのように透きとおった水を飲みほしながら、私はその水の美しさと清らかさを吸収した。私は水という物質(エレメント)への思いを飲みほした。私は清らかで透明な心の本質を欲していたのだ。草の上にきらきらと光る、砕けた虹の滴のような露を目にしたときにも、同じ思いが祈りとなって呼び覚まされた。突風が巻き起こり、木々が地になぎ倒された時にも、同じ情感が目覚まされた。私の心は突風と共に叫んでいた。夏の朝、開け放った窓から吹き入って来た涼風は、同じ甘美な欲求をささやいた。夜には、私は眠りにつく前に、いつでも戸外の陰々とした木立や、闇の中にぼんやりと浮かびあがっている丘の影や、流れる雲の切れ間に見える一つ星に目をやった。そのたびに、心の生活への祈りが生じた。私は最上階のがらんとした荒れ部屋を私の部屋としていた。それと言うのも、座って仕事をしながら、広々とした大地がずっとよく見渡せ、大空の丸天井がずっとよく見え、それらによってわが欲求に思いを致すことが出来たからだ。新月の細い月が輝きだすと、昔からの思いがすべて蘇ってきた。 一年のあらゆる移ろいが、目にし耳にするごとに私の祈りを反復させた。サンザシの緑の葉が開き初める時、牧草に穂の形の花が咲き初める時、小夜啼鳥(ナイチンゲール)が初めて鳴く時、小麦の緑の穂が伸びる時、私の祈りはくり返された。太陽が黄金に染めた小麦の穂に、白さを増していく大麦に、また秋にはブナの木の赤みを帯びた金色の斑紋に、オークの黄ばんだ葉に、そして露の玉を連ねた蜘蛛の細糸に、私は祈った。緑の小麦畑で、見上げる中空に囀るどのひばりも、愛らしいどの燕も、その祈りを私のために歌った。青葉がそれをそよがせ、緑のハナショウブ(brook-flag)がそれを波うたせ、燕たちがそれを携えて、遠い国々で私のためにそれをくり返した。小川のたもとに佇んで、私はその祈りの思いにひたった。日光はこちらの流れの折れ曲がる所ではまばゆく照り映え、むこうの小波の立つ所ではきらきら輝いている。砂底の浅い所では鳥たちが水浴びをし、急な流れがさらさらとせせらいでいる。小川が牧草地をくねくねと流れていくそのように、一つの思いがわが日々をくねり流れていた。 私が学んだ諸々の科学は、一時たりともその思いを堰き止めることがなかった。老獪な哲学書も、それを堰き止めはしなかった。太陽は科学よりも力強く、丘陵は哲学よりも豊かだった。束の間であったが、二度海を見る機会があった。その時、猛烈な熱情が波浪のようにわき起こった。海を去ることは非常につらい思いがした。 時には、私は祈りを求めて、一日中丘陵地を歩き回った。歩くことの骨折りが、地の中から祈りの思いをしぼり出しでもするかのように。私は森の中に幾時間となく留まり、トネリコの小枝や、白子鳩が巣に羽搏く音や、ここかしこの松の木の香りに囲まれて、わが祈りを夢見ていた。 私の仕事ははなはだ性に合わない、無益なものであった。けれども、そんな仕事の最中であっても、時として壁の上に差す一条の陽の光や、窓際の蜜蜂の羽音が、例の思いを呼び起こすのであった。その度に私は惨めな気持になった。丘や平野に陽の光がたっぷりと降り注いでいるのに、最高の時を浪費していたのであったから。ある胸苦しさ、いわば心の筋の収縮が起こった。私はやむをえずこの仕事をしていたが、心は遠くにあった。そんなわけで、しばしば倦怠感や憔悴や神経衰弱におちいった。貧困に浴びせられる侮辱、長い労苦、境遇の重圧、不幸などは、しかし、例の情動の発露を妨げるだけであった。その思いはいつでも存在していた。しばしばロンドンの街中においても、赤い夕日が家並の上に燃える時、この昔からの思い、昔からの祈りがわき起こってきた。 小川の流れる緑の草原でばかり、この絶えざる願いが甦ったわけではない。生ける人体の美に接した時には、さらに奥底からこの願いがわき起こった。完璧な体形、単に体形だけであっても、私はそれに魅せられたし、これからも常に魅せられるであろう。日光と青葉と花々、清らかな水とすがすがしい空気、それらのあらゆる快美が結実したものが、人体の形の中にある。これこそ具象化であり、最高の表現である。そこには樹木や陽光の拡散した、不確かな、意匠を欠いた快美が形を与えられている。この人体の美にかけて、私は最も深く、最も長く祈ったのであり、それは今に到るまで変わらない。人体の形―その形の神々しい理念―隆起した筋肉、惚れぼれさせる四肢、強靭な腱、盛りあがった胸部、アフロディーテであれヘラクレスであれ、いずれも同じ思いをかきたてる。願わくば、心の生活、心の本質をわがものとなすために、神々しき美よ、われに神々しき魂をもたらせ。浅黒いヌビア人、白皙のギリシャ人、繊細なイタリア人、がっしりしたスカンディナビア人は、人体の形状が昔も今も与えているあらゆる絶妙な快美において、私には直ちに熱烈な祈りの思いをかきたてるのである。 私が身体的形状において彼らの如くでありえたならばよかったのだが、実際の私は何と見すぼらしい存在か。形の良い身体を持つことは、富や権力や名声など、すべて野心のもたらすものに遙かに優越しており、そうしたものはこれの前には塵あくたに等しい。人体の形状でなければ、どんな絵画も私の興味を引かない。それ以外の絵画は表面だけの平板なものである。他の芸術についても同じことで、それらには生命が欠けている。陶器や建築は意味がなく、石のように冷淡で、あるものは、例えば磁器の冷たい手触りに到っては、不快を起こさせる。こうしたものには祈りの念は起こらない。芸術においては人体の形状だけが、なかんづく彫像において最も良く、それを起こすことが出来た。これまで私は、良い彫像をあまりにわずかしか見たことがないのが残念である。それでも私が見たわずかなものは、他のすべての芸術に勝っている。ここかしこで見た断片や胸像、ギリシャからもたらされた欠けた像、模造品、石膏像、アフロディーテやペルセフォネやアポロの記念品、それらがすべてだ。けれども、たとえ彫像を描いたものであっても祈りの念を引き起こす。これらの彫像は、私自身と同様に一つの思想で充満しており、蕾のようにはち切れそうになりながら、永遠にその姿勢のままで沈黙している。これらの彫像が表現している魂の生活を私も生きてみたい。人間の腕の形に彫られた大理石のどんな小さな破片も、私が丘の上の祈りで覚えた願望を目覚めさせるのである。 歳月が過ぎて、幸運や成功に恵まれても、私は一瞬たりとも、そうしたものをそれ自体として追い求めるべきであるなどという、惑いに陥ることはなかった。ただ私の心の思想だけが、そうすべき価値のあるものであった。その後の年月において、多くの苦しみがもたらされ、生命そのものがすり減らされ、新たな煩い事と、くり返される屈辱と、営々辛苦によって得たものの喪失と、その果てに、海中に身を投じた方がましではないか?という苦い自問が生じた時にも、そうした事態もまた、何らの刻印を残すことがなかった。私の心は依然として、以前の祈りに忠実なままに留まっている。私が大いに悔やんだ事は、この熱情を表現するために、これらの事を書きとめておく労を惜しんだことである。これを今私はなしているが、部分的にしかうまくいかないことであろう。 この変わらぬ祈りの念は、今この時私に生じている。今ではしかし、それが専ら太陽と海、丘や森、又は人体と結びつくわけではなくなっている。それはつねに内面にある。それを呼び起こす必要はない。回復する必要もない。それはつねに私と共にある。私はそれであり、私が存在するということは、それを表現することと一つである。 長い合い間の後、私は今度は海岸沿いに、再び丘陵地を訪れた。私は大きな丘の側面にある深い窪み、海に面した緑の入江を見つけ、その無上の静寂の中で休息し、思索することができた。背後には暑さのために乾いたハリエニシダの藪があり、すぐ眼前では鉢形の窪地の険しい崖が海に落ちこみ、崖にあたる夏濤(なみ)のかすかな音が立ちのぼってきた。彼方には茫洋たる海原が広がっていた。絶え間なく降りそそぐ陽光のもとで、その熱によって色彩が蒸発でもしたかのように、海はこの上なく薄い緑をおびていた。水平線は明瞭に見分けることができなかった。陽炎がそれを包みこんで、水平線よりも遠く広がっているように見えたので。静寂と陽光、海と丘は、次第に私の心を熱烈な祈りの状態へもたらした。来る日も来る日も、私はその場所を訪れ、幾時間を過ごし、つねに変わらぬ心の願いに燃えていた。やがて私は、その祈りの一部なりと、それに目的を与えることで形式化できないものかと考えるようになった。つまり、その祈りが指し示す方針に従って、実際に何らかの有益な活動をすることを可能にするような、そうした形態をその祈りに持たせることができはしないかと。 ある暮れ方、琴座の白色の輝星〔ヴェガ〕がほぼ天頂に近く光を放ち、薄ら闇の中に深い入江が一層深々と見えていた時、私は祈りを三つの区分に言い表わした。第一は、心を高めさせる何事か、心がそれ自身の生命を生き、今やより力強い存在として生きることができるようにさせる何事かを行いたい、もしくは見つけだしたいという、私の願いである。第二は、肉の身のために何事かを行いうるようにしたい、何らかの発見をなすか、何らかの方法を完成することによって、肉体がより多くの快楽を、より長い生命を享受し、より少ない苦痛をこうむるようにしたいという、私の願いである。第三に、意志の目的を実行に移すための、より融通の利く機械を組み立てたいという、私の願いである。私はこの三つに区分された祈りを琴座の祈りと名づけ、心のみが関係するはるかに深い情動から、それを区別した。 この三区分の中で、最後のものはすこぶる重要性が劣っていたので、他の二つと並べ称するに値しないほどだった。機械装置は便利さを増しはするが、それは決して身体的、精神的完成をもたらしはしない。数千年前に建築のために用いられた初歩的な機械は、その点において、現在の複雑な機械と変わるものではない。鉄や鋼鉄の支配は、身体としての人間を変えることも、改善することもなかった。私はこのような第三区分をそもそも加えるべきかどうか、しばらく思案しさえした。我々の身体は、今日では世界各地にやすやすと運ばれていくが、それによって何ら優れたものになるわけではない。出発した時のままに、帰ってくるのである。古代の最も卓越した人類の種族、例えばギリシャの種族は、ほとんど一箇所に留まっていた。スパルタにおいては体形の完成が見られたが、今日、我々がはなはだ速やかに運ばれていく諸大陸に比べれば、なんとちっぽけな土地であったか!おそらく今後も、そうした体形の完成は、海岸の砂と私との間に見えるほどの、細々とした土地の上に、自給自足の中で生じうるものだろう。 さらに言えば、時計が正確な時を刻んでいるからといって、その持ち主が苦痛を受けないでいる保障となるわけではない。時計の所有者も非情で、心が燃え立つことがなく、単なる被造物であるかもしれない。最も精巧な機械装置からですら、心や身体に対して何らかの利益が生じるわけではない。そうした理由で、私は第三区分を加えるべきかどうか思案したのである。けれども又、私は時というものは後戻しの出来ないものであること、スパルタに還るわけにはいかないことを考慮した。物事の現状があり、現実の民衆が存在する。おそらく、意志のままになるより強力な機械が、民衆に自由を与えるかもしれない。この自由こそは、私の抱く唯一無二の政治的、社会的理念である。さればこそ、この自由のために、第三の区分を加えようではないか。 肉体のために、わがこの腕のために、他者の優美に動く四肢のために、それらに一層大きな完成をもたらすであろう何事かを、私に見いださせよ。骨格がより堅固なものになるよう、もしそれが有利ならば、いくぶん太くなるよう、むろんのこと、より強靭になるよう、また軟骨と腱とがいっそう長持ちし、筋肉がいっそう強くなるよう、それらが古代の彫像に表わされたあの理想の四肢や筋肉の様式に則ったものとなり、肉の身において現実となるように。身体の諸器官がその活動においてより強く、完全で永続的となるよう。肉体の外面がさらにさらに美しくなるよう。外形がより繊細に、動作が優美になるように。以上が、私の意図して言い表わせる最も真摯な言葉である。と言うのは、私は人体の形の美にすっかり魅せられており、しかもその完全な形を見たいものと、口に出しがたいほどあまりに熱心に祈願しているので、思いのたけを書き記すことができないのである。思いのたけを表現することができないのであるから、私はそれを最も平明な言い回しで述べるのが最善であると考えたのである。私は人体の形に信仰を抱いている。人体の形が最高の美に到達することができるための、何らかのこと、何らかの方法を私に見いださせよ。その美は矢の如くにして、弓の強さに応じてどんな遠くをも射ることができるのである。それ故、人体の形に表現されている理想は、美の際限のない拡張と高揚を可能にするのである。 精神、もしくは内的意識、または心に関して、私の祈りが願ったことは、それのための生活様式を発見することであり、その結果精神がそうした精神生活を考えるばかりでなく、実際にこの地上で享受できるようにすることである。私は、精神がそれに基づいて活動すべきである一組の、新しい、より高次の思想を探求したいと願った。心を一冊の新しい書物にたとえるならば、この意味を最もよく伝えることになる――それは過去からではなく、現在と未来から汲みとられた書物である。伝統に基づく一組の思想ではなく、驚嘆すべき現在から、まさにこの今においてじかに汲みとられた一つの新しい思想を、精神に与えさせてほしい。次いで、思想を行為に移そうとする意志を遂行する手段を、心に備えさせねばならない。言い換えれば、心は一つの力となるべきである。 以上の三点が琴座の祈りをなしており、その中で最初の二点が計り知れないほどにずっと重要なのである。私は人間というものに、その精神と肉体と、形と心に、信仰を抱いている。 私はたまたまそのすぐ後で、ペヴンジイ〔Pevensey サセックス州の小港〕へ出かけて行った。その地では、古代の城壁がたちまち私の心を一千七百年前のローマの鷲章(じるし)と、投げ槍と、短剣へと運んでいった。シーザーのローマを目にした者たちの手によって積まれた灰色の石や、薄赤い煉瓦は、日常生活と近代文明と時々刻々の瑣事の束縛から私を解き放った。灰色の石は、あたかも私が当時から今に至るまで存在しつづけたかのような感を起こさせた。それほど深く私は私の生に没入し、私自身の生がそこに反映されているかのように感じたのである。私自身の存在が、私の上に投げ返されて、焦点を結んだのである。私は私の存在の喜びと、不幸と、誕生と死と、無限の中でのその可能性と、とりわけそれが希求する大いなる問いを見た。何の故に?という問いを。わが存在をこのようにはっきりと見てとり、十七の世紀の及ぼす作用によって現在から解き放たれることによって、私は事物に満ち満ちた神秘とその深奥とを、城壁の枯れた草の根や、近くの寄せては返す緑の海において認めたのであった。私に何かをなすことができようか?神秘と可能性とは草の根の中にあるのではなく、事物の深奥は海の中にあるのではない。それらは私の存在の中に、私の心の中にある。存在することの驚異、ほとんど存在の恐怖に近いものが、海や、燦然たる日輪や、遠い丘陵によって、圧倒的な勢いで私の上に投げかけられていた。それらのどっしりした重さをまるごと受けることによって、私は私自身を感じさせられていた。すべての時代、すべての世紀が、この瞬間、私をして百倍もの大きさに、私自身を感じさせたのである。 私はそれまで長らく熟考して来たことを、何とか書き記してみようと決心し、その晩、ほんの一文ながら稿を起こしてみたのである。その文は二年間そのままになっていた。私はそれを書きつごうとしたのであるが、表現につまって立ち往生した。私は今捨て鉢に、このような古代の城壁の石を思わせる粗い思想の石を積み上げてはいるものの、やはり上手く表現できずにいるのである。 * * * 作品名:わが心の物語(The Story of My Heart)1,2章 作者:リチャ-ド・ジェフリーズ 翻訳:脩 海 (copyright: shu kai 2004) 入力:マリネンコ文学の城 |