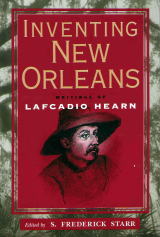ラフカディオ・ハーン(Lafcadio Hearn 1850―1904)
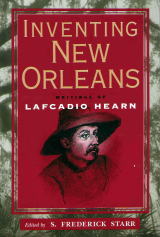
ラフカディオ・ハーン(小泉八雲)の数奇な生い立ちや人生については特に記すまでもないであろう。英国人を父とし、ギリシャ人を母として、イオニア海のリューカディオ島に生まれ、アイルランド、イギリスで育ち、フランスで教育を受け、19歳にしてほぼ無一文でアメリカに渡ったのちは、筆一管のジャーナリスト、翻訳家、評論家、小説家、紀行文作家として、シンシナティ、ニューオーリンズと渡り歩いた。その後日本に渡航してからのことは、その生活ぶりも、作品も、我々日本人には親しい。翻訳城では、比較的読まれることの少ない、アメリカ時代の作品を取り上げて行くつもりである。ニューオーリンズ時代には数千もの記事を書いており、未だにそのすべてが集められていない程の多作家である。著作集に収められた作品でも一般には目に触れることがないであろう。戦前に広く読まれた「東西文学評論」にしても、今日では完全に忘れ去られている。先ずはこの‘文学の香飯’からボヘミアンの香り高い名評論を紹介しようと思う。
(画像は Inventing New Orleans , Writings of Lafcadio Hearn, edited by S.F.Starr, University Press of Mississipi, 2001)
エポス文学館TOPへ
翻訳城へ
狂える浪漫主義者 (ヂェラール・ド・ネルヴァル)
ラフカディオ・ハーン 作
三宅 幾三郎 訳
何かの本で、シェバの女王の超自然的な血統についての不思議な伝説を読む時、フランス浪漫派の愛好者が思い出すであろう歴史物語、またフランス浪漫派時代に、欧州人によって書かれた東方の歴史物語中の出色のものはHistoire
de Balkis et Salomon (シェバの女王とソロモンの物語)である。その物語はLes
Nuits du Ramadan (九月の夜)という誘惑的な表題の下にヂェラール・ド・ネルヴァルのVoyage
en Orient (東方紀行)の中に見出される。この作家は、フランス浪漫派中でも、特に変わった人である。多くの作家達に関するいろいろの驚ろくべき事実が集められ、貴重な覚え書として、次々に発表される時に当って、ド・ネルヴァルに関して、数言を費すのも、フランス文学を愛好する人達にとって、興味のないことではあるまいと信じる。
「ヂェラール・ド・ネルヴァル」の名は、浪漫主義運動に参加した人名中では、最早掻き消すことの出来ないものとなっているが、もともと一つの筆名に過ぎなかった。ヂェラールの本名はラブリューニと云った。尚、彼はド・ネルヴァルという外に、いろいろの変名を用いた。彼は、その文筆生活の初期にあっては一論文を書く毎に、名を変えた位である。しかし、彼は遂に少数の親友の外は、彼の本名を忘れてしまう迄に、ド・ネルヴァルとして有名になった。彼の文学的冒険の極く初めの頃のことは、あまり伝わっていないが、一部分、ゴーチェの「浪漫主義史」の中に述べられている。しかし、ここでは、彼がそれによって最もよく知られており、且つ、その意想の奇と文体の不思議な美しさとによって、永遠の価値を持つところの著述以外について、云う必要はない。彼の書いたものから受ける印象は、他の浪漫主義作家のものから受ける印象とは、まるで違っている。しかし、その本質的な特異さを説明することは容易でない。それは、彼の書くものの精神的な微妙さや、彼に霊感を与えた題目の性質のみによるとは云えない。尤も、或る程度迄それら二つの理由によることは明かだが。エドガー・ポウと同様、彼は夢の中の感情や空想を書き表す非常な手腕を持っている、しかし又、ポウとは違って、彼のそうした表現の中には、読者に迫ってくる、静かな歓びと、ものうい憂鬱とがある。彼の思想の持つ睡いような美しさと、彼の文体の持つ無意識的な魅力とは、一種の睡薬のように、読者の空想を呼び起す。尚その上に何物かがある、――この世のものではないなに物かが。ポウの「リゲイア」、「エリアノーラ」、「アッシャー家」、或は「モノスとダイモノス」等をはじめて読む人も、そこに描かれているのは幻影と悪夢とに過ぎないということをさとる。(フランシス・ゲリ・フェヤフィールドの理詰めの議論を承認すれば、それらは混乱した頭の描く幻影に違いないのである。)しかし、ド・ネルヴァルの描く女には、つい迷わされ、魅せられてしまう。それらの女達は、人間の愛か憎しみかによって、身に危難が振りかかって来る迄は、霊界のものであることを現さない伝説中の妖精のように、本性をかくしている。吾々は、彼等がこの世のものでないことを見抜く為めには、リュジニヤン伯爵がメリュジーヌの一挙一動に注意した以上の目で、彼等を監視しなければならない。彼等は寔(まこと)に愛らしく、目にも実在するかのように映る。しかし、よく見れば夢の女のように正体はないものであることが分る。彼等は、はっきりとした影を落さない。彼等は、ド・ネルヴァル自身がLes Filles du Feu (火の娘)の中で云ったように、霞から出来たものであり、風か火の産んだものである。実際、吾々はよく気をつけていなければ、彼等が変化(ヘンゲ)のものであることを発見するのが困難である。狂人が不思議な絵を描いて、それが狂人の仕業であることが、最初は、余程の鑑識眼のある人でないと分らなかった。ヂェラールは言葉の絵師の中のそうした絵師だった。彼は気が狂っていた。時々は立帰る正気も、果してどれ位続いたかは、疑問とされている。彼の書いたすべてのもの――(恐らく、彼のやった「ファウスト」の訳、それはゲーテもその種の翻訳中の白眉と云ったものであるがを除いて)――は彼の心の病の影響を受けている。軽い精神病者が、醒めている時の状態は、普通人が夢を見ている時の状態に比較することが出来ると云われている。この秘密によって、吾々ははじめて、夢のような不思議な面白さと、ぼんやりした非現実性とを持ったド・ネルヴァルの作品から受ける印象を説明することが出来るのである。彼の作品のいま一つの特質は馬鹿ばかしいようでいて、又変に心を牽く支離滅裂さであって、――丁度夢中になって燥いでいるとりとめの無さといってもいい。彼は非常に面白い話をしているかと思うと、時々変な合の手を入れたり、飛んでもない外のことを云い出したりする。まあ、非常に立派な学者であり談話家である人が、酔っ払ってしゃべっているものと思えばいい。すばらしい話だと思っていると、時々、全く無関係なことを云い出すのである。こうしたことは、ただ二つの例外を除いて、ヂェラールの作品にすべて現れている。そして、その例外を為す二つの作品を書く時、彼は或る非常に手腕のある作家達の助けを借りた。それらの作品の一つは
La Main Enchantee (魔法にかかった手)で、他は Histoire de Balkis (シェバの女王の物語)である。
狂人にして、非常にすぐれた文学上の作品を生み出し得た例はあまり無い。けだし、ヂェラール・ド・ネルヴァルの如きはかかる能力を発揮した最も驚くべき例といってよかろう。彼が「ファウスト」の一部、二部を訳した時は、疑いもなく狂人であった。しかも、原著者ゲーテは、彼の訳を読んで、「今日迄、これ程余を理解したるものなし」と叫んだのである。彼が、伝説と好古趣味と、空想的な叙述とを綯い交ぜた美しい混成詩ともいうべき
La Boheme Galante (色漁り)を書いた時もやはり気がふれていた。この作品はいろいろのものを含んでいるが、中にも、十六世紀フランス歌謡によった、美しい数章と、
Le Monstre Vert (青き怪物)及び「魔法にかかった手」と題された二つの怪しき物語とがある。第一の方は、不思議に短いものであるが、それを読む者は何人も、あの兵士の出くわした、或る葡萄酒の罎が落ちて砕けると、それが鮮血の中に横たわる金髪の裸婦に変るという、酒蔵の怪の条を、忘れることは出来ないであろう。後の方の話は、相当に長くホフマンの書いたどの作よりもすぐれたもので、中古風の作品中の一傑作たるを失わない。あの魔法にかかった手が、罪人のからだから切り落されると、それが蟹のように、狭い街を走り抜け、或る奇怪な家の壁を蜘蛛のようにするすると上って、ついに魔法使が待っている窓のところへ行ってしまうという、処刑の場など、気味悪い迄に生々と書かれている。同じく不思議な混成詩に、「火の娘」がある。娘が幾人かあって、その各々の名が各章に冠してあるのであるが、それらは統一した目的の下に書かれた、性格研究を集めたかの観がある。読者はすっかり作者の手に乗せられてしまうが、決して失望させられはしない。というのは、この哲学的論文と、ロマンスと、劇とをごっちゃにしたような作品は、愉快な程風変りで、その不合理さなどは全く忘れてしまう位だからである。「火の娘」は又、近代田園生活の挿話中、最も美しいものといっていい「シルヴィ」のような、ド・ネルヴァルの書いたものの中でも、とりわけ美しいものを含んでいる。この挿話は、テオフィール・ゴーチェも、田園詩中のすぐれたものとして、「ポールとヴィルヂニ」に比較している。又、十六世紀頃の珍らしい文献の中を物好きに漁って得たものと思われる、「アンヂェリーク」のようなユニークなものもはいっている。それは或る騎士の娘が、賤しい従僕と駆落して、そうした愚かな色恋に適わしい罰を受けるという、哀れな物語である。
ヂェラールの軽い精神異状は、時々ひどくなって、友人達を心痛さした。そして、ある時などは、彼を精神病院に入れなければならなかった。ヂェラールはその時の経験を、非常に変った著述によって、生かしている。彼は自らの狂気を自覚せる狂人の一人であったから。Aurelia;
ou, Le Reve et la Vie (オーレリア、即ち、夢と生)という物語は、精神異状の現象を科学的に、狂人が論じた稀有の著述である。彼の「東方紀行」の第二部の中にある
L'histoire du Calife Hakem (ハケム王の物語)にも、同様の病的な、夢幻状態の研究が見えている。この二部からなる東方旅行記によって、ド・ネルヴァルの名は最も知られているのであるが、彼がそれを書くようになったのは、彼の生涯に於ける最大の事件であったエヂプト漂泊によるのである。
恐らく、狂人にして、はじめてそうした旅行を遂行し得たのであろう。何故なれば、東方人は、西欧人や基督教徒を深く忌み嫌うけれども、狂人に対しては、迷信的な寛容と、親切とをさえも示すからである。ヂェラールは、隊商の宿営で眠ったり、料亭で水煙管(ナーギーラー)を吸ったり、彼にはその言葉も分らない話家が、イスラムの伝説を物語るのを聴いたり、結婚の宴席や、いろいろの回教の儀式に列席したりすることを許された。恐らく、神聖な回教寺院にはいることさえも許されたのであろう。というのは、彼は、絵を見るような生活をしている人達と立交って行く為に、彼等の衣服を身にまとうことを忘れなかったからである。彼の書いた
Femmes de Caire (カイロの女)の中に述べられている何(いずれ)の事件も、みんな事実なのである。又、彼の結婚の話も、疑いの余地無きものである。何処かの奴隷市で、彼は「黄金のように黄な」アビシニヤの娘を購(あがな)った。そして、カイロの或る裏町にアラビヤ風の家を借りて、東方振りの生活をはじめた。その同棲生活は、うまくいかなかった。ヂェラールの東方憧憬の心にも一つの変化が来た。彼のアフリカ人の細君は、まだ若く、熱情的で、その上怒りっぽく、到底、幾時間も黙って、エヂプトの錬金術の神様のことを考えたり、ヘブライの接神学の神秘を思ったりしているような、夢想家の妻には向かなかった。彼女には、現世のものこそ望ましかったのである。彼女は可愛がってもらいたかった。おいしいものが食べたかった。金糸銀糸を織り込んだ着物が着たかった。又回教寺院の塔に上って祈祷の時刻を報ずる僧の歌や、駱駝の鈴に、狂喜しているよりも、恋の歌でも作ってほしかった。彼女は又、ヂェラールに買われたことが違法であることを承知していた。(彼は卑しむべき基督教徒ではなかったが)ヂェラールは、何時も彼女に打たれたと告白している。マクシーム・デュ・カンの云うように、彼の方から別れたのか、あるいは「東方紀行」にあるように、女の方で逃げたのか、何れとも、はっきりしたことは分らない。しかし、彼等二人が、僅かの間しか同棲しなかったことと、その美しいアビシニヤの女が、その後もっと彼女に似合ったトルコ人を夫に持ち、その男との間に、沢山の子供を儲けたこととは、確かである。
ド・ネルヴァルが、彼の東方に於ける経験を叙したこの珍奇な本の中で、精神異状の特徴とも見るべきものがただ一つある。それは Story of Balkis, Queen of the Morning (朝の女王バルキスの物語)の中に見られる。やはり、狂気で死んだヂョン・マルチンの驚嘆すべき絵にも、同一の特徴が見られるのであって、即ち意想の絶大さがそれである。マイエルベールは曽つて 、ヂェラールの作品を歌劇に仕組もうと考えた。しかし、それがあまりにも人間離れのした大きさのもので、如何なる舞台にも、到底上し得ないことを覚った。イスラエル人が埃及(エジプト)を逃れて行くのを写したマルチンの大作も、ヂェラールの東方物語「真鍮の海」の中の大場面や、工匠アドニラムが、不思議な合図によって、労働者や、鍛冶や、大工の大群を招集する今一つの大場面等に比すれば、全く児戯に類するものがある。これらの大空想は、山を刻んで、神も模することが出来ないような巨像を造り、あるいは谷を変じて、その蔭には、日を除(よ)けて、幾万の大群も憩うことの出来るような扶壁拱(ふへききょう)に支えられた大貯水池としたとでも譬える外はないものである。そこには、黙示録からでも来るような、光りと声とがあり、アラビヤの空想も及ばないような絶大の誇張がある。・・・・しかし、その並外れたところにこそ魅力があるのであって、それらの物語を読む人は、誰しも、地球以外のもっと大きな惑星に住む人が書いたものからでも受けるような、驚異を感じるのである。
東方から帰って来たヂェラールは、前よりも尚ひどい狂人だった。そして、エジプトの廃墟が、アダム以前の諸王の宮廷の遺物であること、ピラミッドが、ヂァイアン・ベン・ヂァイアンの不思議な手楯を鍛えた鉄砧(かなしき)であること、ソロモンが本当に、ギンやアフリットの軍勢を閲(けみす)る為めに、ピラミッドの上に坐ったことなどを、本気で信じていた。残っていた財産なども、すぐ変ったことに消費してしまった。彼はつづけてものは書いたが、いよいよわけの分らないものだった。詩も書いたが、変に朦朧としていて、ところどころ意味が汲めるに過ぎなかった。ゴーチェはそうした、ところどころに閃めきを見せている彼の詩を、異境の寺院の土窖(どこう)の中の、紅玉や緑玉を鏤(ちりば)めた偶像に譬えている。彼はそれでもまだ、ある種の珍奇な品物の売立などをよく催した。しかしそうして儲けた金は、すぐ美術的な贅沢品を買うことに費してしまった。或る時彼は、その中に、或る女王が眠ったという大きな寝台を買った。彼は彼が人知れず、打明けぬ恋をしていたという女優が、何時かはその中に睡るということを空想していたのである。その寝台は随分大きかったので、それを置く為めに、わざわざ高い間代を払って、部屋を借りなければならなかった。そして、だんだん困って彼はそれを屋根裏の部屋に迄運ばせた。この費用のかかる場所塞ぎの代物を手離すことに対する、殆んど迷信的といっていい彼の恐怖も、ある意味に於て彼の為めになった。それは彼に一つの安静の場所を与えたことだった。彼は間代だけの金が得られ、あるいは借りられる限り、その寝台に執着していた。しかし、とうとうそれも、他の珍奇な品物と同じく、売払われなければならなかった。ヂェラールの頭は、もう余程狂っていて、更に新しく文学的成功を収め得る望みはなかった。彼はテオフィール・ゴーチェその他の、彼の破滅した思想の美しさと、この上もない心の善良さとを愛する人々の情けにすがって行くことになった。しかし、そうした生活は、彼の如く、現実を偽りと考え、空想を真実と見做す人間にとっては非常な苦痛であったに違いない。彼は、時には飢餓を訴えんよりは、飢えに甘んじ、時には、友達に迷惑と費用とをかけまいとして、嘘をついた。彼は亡霊のように、冬のパリの凍るような夜の街を、空しく不可能事を夢みながら歩き廻った。彼は又、きっと、彼の見てきた東方を、巨大な熱帯の太陽を、曾て雨降ることなき緑の空を、遠く響く隊商の鈴の音を、カイロの夢のような街を、回教僧の美しい歌を、麝香と乳香とのにおいをこめた衣服をまとい、薄絹をかぶった女たちを、ソロモンの帳のように黒く美しかった彼の花嫁を夢みていたのであろう。或る凍るような朝(それは1855年1月27日のことだった)彼はヴィエイユ・ランテルヌ街の或る鉄格子にかかる縊死体となって発見された。かくしてこの世の味気ない現実に倦み疲れた、美しい夢を夢みる人は、自ら進んで、善き夢も悪しき夢も知らない永遠の眠りを求めて行ったのであった。 (1884年2月24日)
――――――――――
著者: ラフカディオ・ハーン
作品名: 「狂える浪漫主義者」
翻訳者: 三宅幾三郎 (1897〜1941)
底本: 「東西文学評論」 (昭和25年第12刷、昭和6年初版、岩波文庫)
入力: 甲斐修二 (エポス文学館)
アップロード: 2005・10・1
<入力に当たっての方針>
1.新字新かなに改める。ただし送り仮名はみだりに変えない。
2.主な変更点――
Ramayan<Ramadan /ラブリュニーン<ラブリューニ/エドガ・ポウ<エドガー・ポウ//其上<その上/アシャ家<アッシャー家/此世<この世/何れ位<どれ位/馬鹿々々<馬鹿ばか/い丶、か丶る、たゞ、等<いい、かかる、ただ/蓋し<けだし/而も<しかも/出会わした<出くわした/横わる<横たわる/ヴァヂニヤ<ヴィルヂニ/這入って<はいって/或時<或る時/或は<あるいは/変つこと<変ったこと/
3.難読と思われる漢字に振り仮名をつけた。ただし(ヘンゲ)は訳者のもの。鉄砧にかんしては、テッチンでは分かりにくいので(かなしき)とした。
|