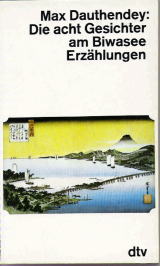 マックス・ダウテンダイ(Max Dauthendey 1867-1918) マックス・ダウテンダイ(Max Dauthendey 1867-1918)ドイツの詩人・作家。フランケン地方の都市ヴュルツブルクに生まれ育つ。二十代で詩人として認められ、ボヘミアン生活を送る。二度の世界旅行で、、メキシコ、エジプト、インド、中国、日本などを巡り、第一次大戦中にジャワで抑留され、マラリアで死んだ。 世界旅行の体験から多くの作品を著わした中に、日本での滞在をもとに自在な空想力(想像力というよりは)を発揮して創作したDie acht Gesichter am Biwasee (琵琶湖の八つの顔・近江八景)がある。 この種のオリエンタリズムの作品の常として、誤認や誤解が、当のオリエンタルである読者にとって、作品の評価を妨げがちである。とり上げた「粟津の晴嵐」においても、西洋人にとってはエキゾチックな虚実のない混ぜが、まま興をそぐことがあるにしても、ホフマンの小説から抜け出したような主人公が琵琶湖畔を闊歩する幻想的なシーンは、ドイツ怪奇メルヘンの魅力を存分に味わわせてくれるであろう。 (画像はDeutscher Taschenbuch Verlag 1980 版) |