 �@�@
�@�@ �@�@
�@�@
�o���G�u�W�[���v�F�@�e�I�t�B�[���E�S�[�e�B�G�^��{�@�A�h���t�E�A�_���^���y�@�i�P�W�S�P�N�j

![]()
�@�W�[���̓_���X����D���Ȕ����������B�ޏ��ɂ̓��C�X�Ƃ��������̖܂ł��Ă�����l���������A���̓��C�X�̓W�[���̈��邽�߂ɔ_���ɕϑ��������݃A���u���q�g�������B�y�����͂��̎��n�Ղ̓��ɃW�[���ɉ����炷��X�ԃq�����I�������C�X�̐g����\�����āA�ʂĂ͔��������M�ȍ���҂܂ł��邱�Ƃ��킩��A�V���b�N�����W�[���͐��C�������A����ł��܂����B
�@�W�[���̑��ɂ́A�x��̍D���ȎႢ���������O�Ɏ��ʂƃE�B���Ƃ�������ƂȂ�閈�ɕ�ꂩ�甲���o���ėx�苶���A�ʂ肩�������Ⴂ�j�����ʂ܂ŗx�点��Ƃ����`�����������B�����ē`���ʂ�W�[�����E�B���ɂȂ����B
�@�W�[���̎��Ɏ��ӂ̔O��������A���u���q�g�͐[��ɃW�[���̕��K��A�����Ńq�����I�����E�B���ɂ��܂��ĎE�����̂�ڌ������B�����ăA���u���q�g���g���E�B���ɂ��܂��Ă��܂����B����ƂȂ��Ă��Ȃ��A���u���q�g��������W�[���́A�A���u���q�g�����Ƃ������悤�Ƃ����B
�@�������E�B���ƂȂ����W�[���͗⍓�ȏ����~���^�̖��߂ŗx�炳��Ă��܂��A�W�[���̗x��ɖ��f���ꂽ�A���u���q�g���ꏏ�ɗx��o���Ă��܂����B�x�炴��Ȃ��E�B���̐��ƈ�����A���u���q�g�������悤�Ƃ���C�����̔��݂ƂȂ��ėx�葱����W�[���́A���x���~���^�ɃA���u���q�g�������Ă����悤�ɂƏ������B�������~���^�͗e�͂Ȃ��W�[���Ɉ�����j�����ւƒǂ����U�f�̕����𖽂����B
�@�W�[���Ƌ��ɗx�葱�����A���u���q�g�͒i�X�Ǝ���čs���A���ɓ|��Ă��܂����B�����ʖڂ��Ǝv�������̎��ɖ閾��������������Ȃ�A��͂��������E�B�������͕��ւƈ����߂���čs�����B
�@�A���u���q�g�͏��������B���������̐��Ȃ�ʌ`�ň����m���߂������W�[�����܂����A��Ȃ���Ȃ�Ȃ������B��l���c���ꂽ�A���u���q�g�͐[�����Ɖi���ɃW�[�����������r�����ɐS���������̂������B
�i�I���j

![]()
����ꖋ��
�@�́X�A�����̂��b�ł���B�V���W�A�i���݂̃|�[�����h�쓌������`�F�R�k�����j�̂̂ǂ��ȑ��͂Ԃǂ��̎��n�����}���Ă����B�����͎��n�ՁB�_�v�����͒���������Ԃǂ��̎��n�ɔ��������Ă����B
�@����Ȓ��A�_���X����D���ȏ����W�[���͌����̖��������l�̃��C�X���U���ɗ���̂�҂��Ă����B���C�X�͍ŋߑ��ɂ���ė��Č������̏����ɏZ�ނ悤�ɂȂ�����҂����A�C�����Ȃ����̔_�v�����Ƃ͈���Ă��āA�������U�镑������������҂��B
�@�W�[���̏Z�ޏ����̑O�ɐX�Ԃ̃q�����I��������ė����B�W�[���ɋC������q�����I���̓��C�X�̑��݂��������낭�Ȃ��B�������ǂ������C�X�͑��̑��̎�҂Ƃ͗l�q������Ă��Ă�����L���B�c�����ɂ͉����閧�������Ȃ����낤���c�ƃq�����I���͏�X�v���Ă����B��Ŏd���߂��l�����W�[���ւ̑��蕨�Ƃ��ď����̑O�ɂԂ牺���A�����閧��\���Ă�邼�A�Ǝv���Ȃ���q�����I���͐X�֖߂��čs�����B
�@�q�����I������������A�����}���g��Z�����������N���W�[���̏����̑O�Ɍ��ꂽ�B�ォ��]�҃E�B���t���[�h������ė����B�N�̓}���g�ƍ��ɑттĂ������h�Ȍ�����苎���ď]�҂Ɍ������̏����ɒu���Ă���悤�ɖ������B
�@�e���Ȑg�Ȃ�����Ă͂��邪�A�i�i�ƈЌ�����������̔������N�̓V���W�A�̌��݃A���u���q�g�ł���B�E�B���t���[�h�͌��݂ɁA����Ȏ��͂悢���ʂ������܂���A�ǂ������~�߂��������A�Ɨ@�������A�A���u���q�g�͎�荇��Ȃ������B�����ċB�R�Ƃ��ċA��悤�ɃE�B���t���[�h�ɖ������B�]���ȏ]�҂͎d���Ȃ����݂̖��߂ɏ]���A�p���������B

�@��l�ɂȂ����A���u���q�g�͗�����N�̊�ɂȂ����B�����ăW�[���̏������m�b�N���Ă���A�������Ă�낤�Ƃ����ƕ��A�ɉB�ꂽ�B���̓W�[���̗��l���C�X�Ƃ͂��̌��݃A���u���q�g�Ȃ̂ł���B���������ȃW�[���̈������Ɗ肤�ނ͂����̔_�v�̂ӂ�����ăW�[���ɋ߂Â����̂ł������B
�@��������͒e�ނ悤�ɃW�[������яo���ė����B���炭�T������Ă���łꂽ���ɂ���ƃ��C�X�i�A���u���q�g�j���o�ė����B���������C�X�����āA����P��������͂ɂ��肵�Ă����W�[�������A��錩���߂������̘b���n�߂��B���̓��C�X�͋M���Ŕ������M�w�l�������Ă���A�W�[���ł͂Ȃ��A�ޏ���I��ł��܂��Ƃ������̂��B
�@�����{���ɂ���Ȏ��ɂȂ����玄�͎���ł��܂���A�ƃW�[���͌������B��u�h�L���Ƃ������C�X�i�A���u���q�g�j�ł��������A����Ȏ�������A�l�͂����ƌN�������Ă����A�Ɖi���̈��𐾂����Ƃ����B
�@�W�[���͂�����Ԑ肢�Ŏ������̂��ꂩ���肢�܂��傤�A�ƃ}�[�K���b�g��E��ł����B�����Ĉ����Ă���A�����Ă��Ȃ��c�ƉԐ肢���n�߂����A�r���܂ł�����Ƃ���ň����ĂȂ��A�ŏI��邱�Ƃ��킩���Ă��܂����B
�@�W�[���͐^�����ɂȂ��ă}�[�K���b�g�����o���A�����o���Ă��܂����B�W�[���̏Ί�����߂����߂ɁA���C�X�i�A���u���q�g�j�̓}�[�K���b�g���E���A�Ԃт�̖��������܂��H���āA�ق猩�Ă����A�ƈ����Ă���ŏI���悤�ɂ��Ă�����B���M�[�������ɂ��Ί炪�߂����B�����ăW�[���̓��C�X�i�A���u���q�g�j�ƈꏏ�ɑ�D���ȃ_���X���n�߂��B

�@�����֍Ăуq�����I�����߂��ė��āA�f���̂킩��Ȃ�����Ȓj�Ɖ������Ă���A�ƃW�[�����Ƃ��߂��B�W�[���͎��͂��̐l�������Ă���̂����A�����������Ƃ����Ă���킯�ł͂Ȃ��A�Ɨz�C�ɓ������B����ƃq�����I���́A�ǂ����Ă���̑z�����킩���Ă���Ȃ��A�Ƃ������W�[���ɔ���n�߂��B
�@���C�X�i�A���u���q�g�j�̓q�����I���Ɏ~�߂�悤�Ɍ����A�Ȃ����������q�����I���������̂����B�����藧�����q�����I���̓i�C�t�����o���ă��C�X�i�A���u���q�g�j�Ɍ��������A���C�X�i�A���u���q�g�j�̋B�R�Ƃ����ԓx�ɋC������āA�o���Ă���A�Ǝ̂ă[���t���c���ė����������B
�@�q�����I���Ɠ���ւ��ɔ_�Ƃ̖�����������ė��āA�ꏏ�ɂԂǂ��̎��n�ɍs���܂��傤�A�ƃW�[����U�����B�������W�[���͍����͊y�������n�ՂȂ̂����A�Ԃǂ��̎��n���݂�Ȃňꏏ�ɗx��܂��傤��A�Ɩ�������U�����B����������ˁA�Ɩ��������J�S�⓹��ނ������A�W�[����C�X�i�A���u���q�g�j�ƈꏏ�ɗx��n�߂��B�������Ă݂�ȂŖ����ɂȂ��ėx���Ă���ƁA�W�[���̏����̃h�A�������āA��e�̃x���g���o�ė����B
�@�W�[���͂���ĂĖ������̉A�ɉB�ꂽ�B�_���X����D���ȃW�[���ł��邪�A�ޏ��̐S���͏�v�Ƃ͌������A���܂�x��߂�����V���b�N�����肷��Ǝ~�܂��Ă��܂��̂ł͂Ȃ����A�Ə�X�x���g�͐S�z���Ă����̂ł���B
�@�x���g�͂����܂��B��Ă���W�[���������A�������̊Ԃ����������o���ď������������B�u�g�̂��ア�����ɁA����Ȃɗx���Ă��肢����A����ł��܂���B����������E�B���ɂȂ��Ď���ł�����x���Ă��邾�낤��B�v�������͂т����肵�āA�ǂ��������ƂȂ́A�Ƌ��鋰��x���g�ɐu�˂��B
�@�x���g�͂��̒n���ɓ`���`����b���n�߂��B�c�x��̍D���ȎႢ���������O�Ɏ��ʂƃE�B���Ƃ�������ɂȂ��Ă��܂��B�E�B�������͐��O�ɖ�������Ȃ������_���X�ւ̗~�����}�����ꂸ�ɖ�Ȗ�ȕ�ꂩ�甲���o���ė��ėx�苶���B�����ĕs�^�ɂ��߂���ʂ肩�������Ⴂ�j���������肱��Ŏ��ʂ܂ŗx�点��̂��ƌ����c�B
�@�A�T�Ȓ��q�̃x���g�̘b�ɎႢ�������͋������B�����Ċy�����C�����������ł��܂��A�ĂуJ�S��w�����ē���ނ���ɂԂǂ��̎��n�ɍs���Ă��܂����B�W�[���͎��͂���ȓ`���͋C�ɂ��Ȃ���A�ƒ�R�������A�x���g�̓W�[���������֘A��ē����Ă��܂����B
�@��l���c���ꂽ�A���u���q�g�̎��ɋM������̎��Ɏg���p�J�̉����������Ă����B����͂܂������ɂȂ����A��̒N�������̂��낤�A�ƃA���u���q�g���v���Ă���ƁA�E�B���t���[�h���삯���āA�N�[�������h����ƃo�e�B���h�P���M���������]���Ă���ė��������������B�������A���u���q�g�͂���Ăă}���g���H�D�肻�̏ꂩ�痧���������B

�@�N�����Ȃ��Ȃ����Ƃ���Ƀq�����I��������ė����B���A�Ń��C�X�i�A���u���q�g�j�ƃE�B���t���[�h�̂��Ƃ�𓐂��Ă����q�����I���͎v�����B�c����ς肠���͂����̔_�v�ł͂Ȃ��A����Ȃɗ��h�ȕ����������l���i�E�B���t���[�h�j�������ɐb���̗���Ƃ��Ă����ł͂Ȃ����B�悵�A�����Ƃ����������������̐��̂�\���Ă��c�B
�@�����ăq�����I���͏؋���T�����߂Ƀ��C�X�̏����ւ�������ƐN�������B���̒��Ńq�����I���͋M�����������Ȃ����h�Ȍ��������A���̖�͂����Ăق����B�c�悵�A����ł����̐g���͊��ꂽ�B�����̓V���W�A�̌��݂��B���̌��ݗl���_�v�ɕϑ����ăW�[�������Ă�����ł���Ƃ����킯���B�z�̐g����\�I���ăW�[���̂̂ڂ��������������₵�Ă�낤�c�B
�@�q�����I���͑����������������ăW�[���Ƀ��C�X�̐��̂������悤�Ə������m�b�N���������B���̎��Ăъp�J�������A�M�������̎�̈�s���߂Â��̂��������̂ŁA�q�����I���͈�U�͕��A�ɉB��ėl�q�����邱�Ƃɂ����B
![]()
�@�����ċM�������̎�̈�s���W�[���̏����̑O�ɓ��������B�����z�˂�������ċx�e�ł���Ƃ����T���Ă����̂��B�r�������s��擱���Ă����E�B���t���[�h���h�A���m�b�N���A�o�ė����x���g�ɃN�[�������h����̂���s���x�e�ꏊ�ƈ��ݕ������]���Ă�����|��`�����B�x���g�̓W�[�����Ă�ň�s�ɂł������̂��Ƃ����Ċ��҂����B
�@�M�������ɋ��d�����ĉ��Ȃ���A�W�[���̖ڂ͍��M�Ŕ������o�e�B���h�P�ɓB�Â��ɂȂ����B�܂�ŊG�̂悤�Ȕ�̑ł����̂Ȃ����������B�����ăo�e�B���h�P�̒��Ă���h���X�B�W�[���͐j�d�������Ă���̂����A����Ȃɔ��������̂͌������Ƃ��Ȃ��B�����Ƃ肵���W�[���͎v�킸�����݂���ŕP�N�̃h���X�̐��ɂ������Ǝw�����ׂ点���B
�@�o�e�B���h�P�͉������ƐU��������B�����ĉ��Ƃ����Ȕ��������������̃h���X�ɐG��Ă���̂����Đ������������Ȃ����B�c���O�̖��O�͉��Č����́A�����������ĕ�炵�Ă���́H���l�͂���́H�c
�@�W�[���͂�����Ƃ͂ɂ��݂Ȃ���A���M�ȕP�N�Ɏ����̖��������A�Ԃǂ��̎��n��j�d���A�����đ�D���ȃ_���X�����ĕ�炵�Ă��鎖��b�����B�����ė��l�Ƃ͍�������Ă���A�����̂Ă�ꂽ�肵����A�����Ǝ��͎���ł��܂��ł��傤�A�Ɠ������B
�@�o�e�B���h�P�͔���ŁA�����f�G�ȕ��ƍ��Ă���̂����ǁA���Ȃ��̂悤�ȉ����l�̍���҂������Ƒf�G�Ȑl�Ȃ�ł��傤�ˁA����Ă݂������̂���A�ƌ������B�W�[���͂��̕ӂɂ���̂ł͂Ȃ����Ǝv���ĒT����������A���C�X�̎p�͂ǂ��ɂ���������Ȃ������B�W�[�����C�ɓ������o�e�B���h�P�͎����̎������W�[���ɗ^�����B�W�[���͍��M�ȕP�N����̎v���������Ȃ����蕨�ɗL���V�ɂȂ����B
�@�z�˂��͈ˑR�Ƃ��ċ����A���Ă��܂�������ƃo�e�B���h�P�̓W�[���̏����ł����x�ނ��Ƃɂ����B�����ċM�������Ɏ�𑱂���悤�Ɍ����āA�p�J�������̑O�ɂ��������āA���������͏����֓����čs�����B

�@�܂��Ȃ����n���I�����_�v�►����������ė��āA���n�ۂ̃_���X��x��n�߂��B�M�������������������̂��m���߂����C�X�i�A���u���q�g�j���߂��ė����B�W�[������������o�ė����B�W�[���͎��n�Ղ̏����ɑI��A�Ԃǂ��̖��ŕ҂���������ꂽ�B�����Ĕ_�v�►�����͔M���I�ɗx��n�߂��B�W�[���ƃ��C�X�i�A���u���q�g�j���������т������ς��ɕ\���ėx�葱�����B
�@�����փq�����I�������������ė������A�y�������Ղ葛�����Ԃ����B�q�����I���̓W�[���Ƀ��C�X�͖{���͌��݂ł��邱�ƁA�W�[���͂��Ă�����Ă���̂��Ƃ�������\�I�����B�W�[���͏�����A�M���Ȃ������B����ƃq�����I���͖�͂̓��������h�Ȍ����W�[���̖ڂ̑O�ɓ˂��o���A����͂����̏����̒��Ō������A�ƌ������B
�@�W�[���̔]���ɂ��̔߂���������݂��������B�����ă��C�X�i�A���u���q�g�j�ɖ{���Ȃ́A�Ɛ^�����ɂȂ��Đu�˂��B���C�X�i�A���u���q�g�j�́A����Ȏ�������킯�Ȃ�����Ȃ����A�l�͂����̔_�v����A�ƌ�������悤�Ƃ����B
�@�W�[���̓��C�X�i�A���u���q�g�j�̌������Ƃ����Ƃ��M�������Ǝv���A���C�X�i�A���u���q�g�j�Ɋ��Y�����B����������v�����q�����I���́A�ؐl������A��������Ȃł�����̂��A�Ƃ���ɏ����ɂ�����ꂽ�p�J����ɂƂ��Đ����炵���B
![]()
�@�p�J�͋����n��A����̂��Ăт��Ǝv�����M���������A���ė����B�����ă��C�X�i�A���u���q�g�j�������A���₤�₵�����A�������B�����o�e�B���h�P����������o�Ă��đe���ȂȂ�������A���u���q�g�����ċ����A��̂ǂ��������Ƃ��Ƃ킯��u�˂��B�A���u���q�g�́A��l�Ŏ�����Ă��܂����ƌ����āA�����o���ꂽ����҂̃o�e�B���h�P�̎���Ƃ�A�ڕ������B
�@���͂�q�����I���̌������Ƃɋ^���͂Ȃ������B������肩���̔߂������̒ʂ�o�e�B���h�P�Ƃ������M�Ŕ���������҂܂ł����̂ł���B�Ռ������W�[���͔���I�ɃA���u���q�g�ƃo�e�B���h�P�̊ԂɊ����ē������B�����ăo�e�B���h�P�Ɍ������Ă��̐l�͎��̑�ȍ���҂ł��A�Ƌ��B�o�e�B���h�P�͂�����āA���������Ă���́A���̕��̓V���W�A�̌��ݗl�ŁA���̍���҂Ȃ̂ł���A�ƌ������������B
�@��������W�[���̓��C�X�i�A���u���q�g�j�ɂ���������Ƃ����B���������C�X�i�A���u���q�g�j�̓W�[���̖ڂ�����ĉ����������܂܉����������Ƃ��ł��Ȃ������B��]�����W�[���̓o�e�B���h�P���������������������������Ēn�ʂɒ@�����A������|�ꂱ�B
�@�������o�e�B���h�P�́A����͂ǂ��������Ȃ�ł��A�ƃA���u���q�g�Ɏߖ������߂��B�������A���u���q�g�͉����������܂܁A�o�e�B���h�P�ɑ��Ă��ꌾ�������邱�Ƃ��ł��Ȃ������B
![]()
�@��]�����W�[���͂��łɐ��C�������Ă����B�Ԑ肢�₻�̑��̊y���������v���o���C�̋������W�[���̔]�����삯�������B�����ăW�[���͒n�ʂɗ����Ă����A���u���q�g�̌����Ђ�����A�����̋��ɓ˂����Ă悤�Ƃ��A�q�����I���Ɏ~�߂�ꂽ�B�����č��������܂܁A���ă��C�X�Ƌ��ɓ��_���X�̃X�e�b�v����l�œ��B���ꂪ�v���I�ł������B����ȃW�[���̐S���͂��łɐ���������Ă����B�ꂵ���ȃW�[���͏��������߂ĊF�̊Ԃ����������B
�@�ƁA�������̐��Ȃ�ʗ₽�����̂��W�[������������ĂԂ悤�ȋC�������B���������Đk���Ă���W�[���ɁA�q�����I���͂��ꂳ��͂���������A�ƃW�[�����x���g�̕��ɗU�������B��x�̓x���g�̘r�̒��ɓ|�ꂱ�W�[���ł��������A����I�ɑ���o���A�Ō�̓��C�X�i�A���u���q�g�j�̘r�̒��ɔ�э���ő��₦���B
�@�����M�������͂��܂�̎��Ɍ��t�������A�o�e�B���h�P�������Ȃ��痧���������B�߂��݂Ɉ����ꂽ�A���u���q�g�́A����ɉՂ܂��q�����I���ɂ��O�̂����ŃW�[���͎��A�ƐH���Ă��������B�q�����I�����܂������̂͂��O���ƌ����ē�l�͌��������ɂȂ����B
�@�A���u���q�g�͎����̌����E���ăq�����I�����a�̂Ă悤�Ƃ������A�E�B���t���[�h�Ɏ~�߂�ꂽ�B�x���g�́u�������Ă��W�[���͐����Ԃ�Ȃ��B��������������o�čs���Ă��������B�v�ƃA���u���q�g�ɂ͂��̂Ă�悤�Ɍ������B��҂����̎������s���A���u���q�g�ɓ˂��h�������B�E�B���t���[�h�ɑ�����A���ꂪ�����Ȃ����A���u���q�g�͓�����悤�ɂ��̏�𗧂��������B
�@�Q���߂��ރx���g�A����ɂ����q�����I���B���ɂȖʎ����̔_�v�A�������B�������W�[���̖ڂ��J����邱�Ƃ͓�x�ƂȂ������B
�����
�@�@�W�[���͑��̂͂���̐X�ɑ���ꂽ�B����|�v���A�����Ȃǂ̋����T���Ɩ��Ă���A�����̎��X�͋߂��̐����ł�ǂr�̒��܂ł��̂˂����ꂽ��������L���Ă���B�W�[���𑒂����ꏊ�ɂ͔����嗝�̏\���˂����Ă�ꂽ���A�w�̍����쑐��쐶�̉ԁX������B�������ɖ��Ă����B�\���˂ɂ̓W�[�������n�Ղ̊ԓ��ɍڂ��Ă����Ԃǂ��̖��̊����������Ă����B���Ԃł����C��������������ꏊ�ł��������A���̌��ɏƂ炳��Đ��������яオ�������̌��i�́A���̐��̂��̂Ƃ��v���ʕs�C������Y�킹�Ă����B
�@���̂悤�ȏꏊ�̕�����ɓK���Ă���Ǝv�����̂��A�X�Ԃ����͂����Ŗ�c�����鎖�ɂ����B�����ăT�C�R����U���ĉɂ��Ԃ��Ă������A�q�����I�������̓W�[���̕�ɉԂ������Č���̗܂ɂ���Ă����B
�@�������邤���ɁA�P�Q������������������B���̌����`���ɂ��A�E�B�������͂��̎��Ԃɕ�ꂩ���S����x�苶���̂��ƌ����B�����Ă���͔ޏ���̗�͂������钩��4���܂ő����̂��B
![]()
�@�₪�Đ��S�����������Ǝv���ƁA�X�Ԃ�����ǂ��n�߂��B�X�Ԃ����͋��|�ɏP���A�U��U��ɂȂ��ē����o�����B�q�����I�����^�����ɂȂ��ē����o�����B
�@���̌�A�����ʂ�������e�̂悤�ȃE�B���̏����~���^�����ꂽ�B�w���������������~���^�͂��̐��Ȃ�ʔ������łЂ�Ђ�ƒ��Ԃ悤�ɗx�葱���A�ޏ����ʂ����Ƃ���ɂ͐���̔�����_��I�ȋ�C���������߂��B�����Ă�������̃E�B���������W�܂��ė����B�~���^�����[�Y�}���[�̎}����Ɏ����č��}������ƁA�E�B����������ł����r�߂͈�Ăɗ����A�����������ԉňߏւ�Z�����p�ƂȂ��Ē��Ԃ悤�Ɍy�X�ƁA�d�����܂ł̔������ŗx��o�����B
�@�₪�ă~���^�̓E�B�������ɐV�������Ԃ�����鎖���������B��̉�����W�[�����Ăяo���ꂽ�B�~���^�����[�Y�}���[�̎}���W�[���Ɍ������Ĉ�U�肷��ƁA�r�߂͂ЂƂ�łɗ����A����܂Ō����ʂ�Ȃ������葫���S�������т��ڂƂ��点�邩�̂悤�ɁA�S�g�ɗx��ւ̏�M�������点�ăW�[���͗x��o�����B
�@�������ăW�[�����E�B���̒��ԓ�����ʂ��������ɁA�l�̑��������������B�����������ĂĂ����E�B�������͊l�������߂Ĉ�ĂɈړ����čs�����B
�@
�@���̌�A�W�[���̕�̑O�Ɍ���ɑł��Ђ������A���u���q�g�����ꂽ�B�E�B���t���[�h���ǂ��ė��āA���̕s�g�ȏꏊ�͔߂��݂�[�������邾��������A�ƃA���u���q�g��悩������������Ƃ������A�A���u���q�g�͋A��悤�ɁA�Ƃ����������ăE�B���t���[�h��ǂ������Ă��܂����B
�@�A���u���q�g����ɂЂ��܂Â��A��������Ă���ƁA�ڂ̑O�ɕs�v�c�Ȃ��̂����ꂽ�B�W�[���ł͂Ȃ����낤���c�A���u���q�g�͋����A����������ɂȂ����B�����ăA���u���q�g�͋z������悤�ɃW�[���̕��Ɏ��L���A�������߂悤�Ƃ����B
����������ƂȂ����W�[���̓X�����Ɣނ̎�����蔲���Ă����B�W�[���̓W�[���ŁA�Ԃ�E��ł��ăA���u���q�g�ɓ����A�����������ɂ��鎖�Ɣނւ̕ς��ʈ�����������Ƃ����B�������ăA���u���q�g�ƃW�[���͂��炭����̂Ȃ��ǂ��������������Ă������A�₪�ăW�[���͏����Ă��܂����B
�@�A���u���q�g���ނȂ������������߂Ă���ƁA�s�g�Ȃ��̂��߂Â��ė���̂�������ꂽ�B�������A���u���q�g�͎}������̉A�ɉB�ꂽ�B
�@����̓E�B�������Ɍ�����A�x�鎖���������A���ʂĂ��q�����I�����E�B�������ɍŌ�̒n�֒ǂ����Ă��ė�����i�ł������B�q�����I���͏����~���^�ɋ���������A�₽�����₳�ꂽ�B�₪�ĕm���ɂȂ����q�����I���͎��X�ƃE�B�������ɂ��炢����A���ɂ͒r�ɓ˂����Ƃ���ĂƂǂ߂��h���ꂽ�B�q�����I�����d���߂��E�B�������͋��에�������B

�@�����ăA���u���q�g���E�B�������Ɍ������Ă��܂����B�~���^���A���u���q�g�Ɍ������ă��[�Y�}���[�̏��U��グ�悤�Ƃ������A�W�[������яo���ė��ăA���u���q�g�������A�~���^�̑O�ɗ����ӂ��������B�W�[���̓A���u���q�g���̏\���˂ɘA��čs���A�����Ă����𗣂�Ȃ��悤�ɂƌ������B�\���˂̐��Ȃ�͂��A���u���q�g�����A�E�B�������̗�͂��ʂ��Ȃ��Ȃ�̂��B
�@�~���^�̓A���u���q�g�Ɍ������ă��[�Y�}���[�̏����U�肵�����A�\���˂̐��Ȃ�͂̑O�ɏ����~���^�̏�͐܂�Ă��܂����B
�@�������X�̂悤�ɗ₽���ʎ����̃~���^�͗������������ăW�[���ɂ����������B�m���ɏ\���˂ɐG��Ă���Ԃ͈��S�ł��傤�B�������A�W�[����B�E�B���ł��邨�O�͎����x��Ɩ�����Ηx�炸�ɂ͂����Ȃ��̂ł��B�����A�N�����D��ɁA�N�������f�I�ɗx��Ȃ����B�����Ă��O�̂��̗x��ň�����j��U�f���A�\���˂��痣�ꂳ���ėx�点�A�Ō�͎��Ɏ��炵�߂�̂ł��B
�@�����ă~���^�̓W�[���Ɍ������ď����U�肵���B�ӎv�Ƃ͗����ɃW�[���̎葫�͓����n�߂��B�����~���^�ɖ�������Ηx�炴��Ȃ��W�[���B�B����ł��W�[���͉��Ƃ����ăA���u���q�g����낤�Ɛ���t�̍H�v�������c�������A�ł��邾���������Ɠ������B��������Ύ��͌o���A�₪�ĂS��������ė��ăE�B���̗�͂͏����A�������l�͏����邩������Ȃ��c�B�@
�@�������������Ƃ������J���ȃW�[���̓����͂�����������قǖ��f�I�ŁA�����܂��A���u���q�g�����\���x�z���鐢�E�ɗU�����B�����Ƃ�Ƃ����\����ׂ��A���u���q�g�̓~���^�̌����悤�ɁA��������\���˂𗣂�Ă������B�W�[���Ɨx�邱�Ƃ��ł���Ȃ�Ύ���ł����܂�Ȃ��A�Ƃł������悤�ɁB�~���^���͂��߃E�B�������́A�W�[����������j��U�f���A�j�łւƓ����x��������Ƃ���悤�ȗ₽���ŖT�ς��Ă����B
�@�W�[���͓x�X�~���^�Ɏ��߂�����B�������⍓�ȃ~���^�͂͂˂��A�X�Ɍ������x�葱����悤�ɂƖ������B���n�߂��A���u���q�g�������Ă����悤�ɂƏ��������A�~���^�͗e�͂��Ȃ������B�����ĉ��x���|��Ă͗����オ��A�A���u���q�g�̓W�[���Ƌ��ɗx�葱�����B���ɂ̓E�B�������������A�A���u���q�g�ɂƂǂ߂��h�����ƌ������X�e�b�v�ݎn�߂��B
�@�����ė͐s�����A���u���q�g�͂��ɓ|��ċN���オ��Ȃ��Ȃ��Ă��܂����B���͂₱��܂Łc�Ǝv�������̎��A�S������������̉��������n�����B�E�B�������̗�͂͒i�X�Ǝ�܂�A�����~���^�����̃E�B�����������̕�̒��ւƈ����߂���čs�����B

�@���������c�A���u���q�g�͐S����ɂ��ċ��Ɏ�����ς������Ă��ꂽ�W�Z���Ǝ����荇�����Ƃ����B�������W�[���͒i�X�Ɖ����֏����čs�����Ƃ��Ă����B�W�[�����܂�����ł���A��֖߂�Ȃ���Ȃ�Ȃ��̂ł���B�W�[���͍Ō�̗͂�U��i���ĉԂ�E�݁A��������߂ăA���u���q�g�ɓn���ĉi���̕ʂ�������A�����čs�����B
�@���Ƃ��������c���⎩���ƃW�[���̐S�͈�Ɍ��ꂽ�Ƃ����̂Ɂc���ɂ̒��Ɉ�l���c���ꂽ�A���u���q�g�́A�[�����Ƃ���ɗ��ʐ[���r�����ɐS���������̂������B
�i�I���j
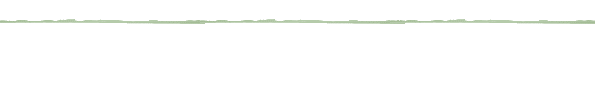
![]()
���@�W�[����{���
���@�W�[���̐����Ƃ��̌�
���@�E�B���i���B���X�j�̓`��
���@�W�[���̃h���}��
���@������{�E�S�[�e�B�G�ŁE���݂̏㉉�̑���_
���@���݂̘_�_
�@�@�@�@�@�E�@�A���u���q�g�̓W�[�������Ă�����ł����̂�
�@�@�@�@�@�E�@�s���Ȓj�������邩
�@�@�@�@�@�E�@�q�����I���ɂ���
�@�@�@�@�@�E�@�q�����I���͂Ȃ����ݗl�ɑ��Ă���Ȃɉ����Ȃ̂�
�@�@�@�@�@�E�@�o�`���h�P�ɂ���
�@�@�@�@�@�E�@�W�[���͎��E��
�@�@�@�@�@�E�@�W�[���͂��ꂩ����E�B���ł��葱���邩
���W�[����{���
�@�@�@�u�W�[���A�܂��̓E�B�������v
�@�@�@��{�@�@�@�@�e�I�t�B�[���E�S�[�e�B�G�A���F���m���E�h�E�T�����W�����W��
�@�@�@�U�t�@�@�@�@�W�����E�R�����A�W���[���E�y���[
�@�@�@���y�@�@�@�@�A�h���t�E�A�_��
�@�@�@�����@�@�@�@�P�W�S�P�N�@�U���Q�W���@���@�������y�A�J�f�~�[�i�p���E�I�y�����j
�@�@�@�����ҁ@�@�@�W�[���@�@�@�F�@�J�����b�^�E�O���W
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�A���u���q�g�F�@�����V�A���E�v�e�B�p

�W�[���̐����Ƃ��̌�
�@�W�[���̓��}���e�B�b�N�o���G�̑�\��ł���Ɠ����ɁA���ׂẴo���G�̒��ł��ł��l�C�̂���o���G�̈�ł��B�����閼��̒��ł����Ƀh���}�����D��Ă���_���l�C�̔閧�ł��B
�@�ŏ��Ɂu�W�[���v����낤�Ǝv�������͎̂��l�̃e�I�t�B�[���E�S�[�e�B�G�ł��B�n�C�����q�E�n�C�l�́u�h�C�c�_�v�i�܂��́u���앨��v�j�ɂ������x�鐸�샔�B���X�ɋ������������S�[�e�B�G�����B���X�̓o�ꂷ��o���G�����Ȃ����낤���Ǝv�����̂����[�ł��B
�@�������Ȃ����l�̃S�[�e�B�G���o���G�̑�{���������Ǝv�����̂ł��傤���i����]�Ȃ�O���珑���Ă��������ł����j�B���̓S�[�e�B�G���̓W�[���̏����҂ł���J�����b�^�E�O���W�ɔM��ɍ��ꍞ��ł����̂ł��B���̃O���W���I�y�����ɐ����Ɏ���Ƃ��ăf�r���[�����邽�߂ɉ��������o���G�͍��Ȃ����A�ƍl�������ʂȂ̂ł����B���ǃS�[�e�B�G���̗��͎���Ȃ������悤�ł����A�ނ̗��̏�M�͑f���炵����i�ݏo�����̂ł��B�����Ă��̌�������ȃo�����[�i�ɔM�������Ȃ�����S�[�e�B�G���̓O���W�Ƃ����Ɨǂ����F�B�ł����炵���ł��B
�@�S�[�e�B�G�͂܂��ꖋ�ŗx�肷������l�������𗎂Ƃ��A�����ēŃ��B���X�ƂȂ��ėx�苶���Ƃ����\�z�����Ă܂����B�����Ă��̂��߂ɂ͂����ɂ��Ď�l���̏����Ɏ���ł��炤�����v�Ă̂��ǂ���ł����B�S�[�e�B�G�̍ŏ��̈Ă͕�����Őg�̂��ΏƂ�����l�����閾���̗�C�ɐG��Ė��𗎂Ƃ��A�Ƃ������̂ł����B�i���B�N�g���E���S�[�̎��u�t�@���g���v�i�u�������W�v�Ɏ��^�j���q���g�ƂȂ��Ă��邻���ł��j����������ł͈ꖋ�ɂقƂ�ǃh���}�Ƃ������̂�����܂���B����ł͂�����Ɓc�Ǝv�����S�[�e�B�G�̓��F�e������{��Ƃ̃T�����W�����W���ɑ��k���܂����B�����ăT�����W�����W�����ꖋ�����������A���݂̂��̂ɋ߂��`�ɂȂ����̂ł��B�����ēɂ��Ă͂قƂ�ǃS�[�e�B�G�̍\�z�ʂ�ƂȂ�܂����B
�@�����ăW�[���͏���������听�������߂܂����B�O���W�̓}���[�E�^���I�[�j�ƕ��я̂����قǂ̐l�C�҂ƂȂ����̂ł��B�������O���W�̈��ނƂƂ��ɃW�[���̓I�y�����̃��p�[�g���[��������Ă����܂����B���v���o�����悤�ɏ㉉����܂������A�₪�đS�������Ă��܂����̂ł��B�Ăу��p�[�g���[�ɖ߂����ɂ͂P�X�Q�S�N�ł����B�����₦�邱�ƂȂ��㉉�������㐢�ֈ����p���ł����̂̓��V�A�ł����B���V�A�ł̓v�e�B�p���U�t�Ɏ�����Ă��邻���Ȃ̂ŁA�ǂ��܂ŃR������y���[�̌��U�t���c���Ă���̂��͂悭�킩��܂��A�Ƃ��������V�A�ŃW�[���������邱�ƂȂ��x��p����ė����������ʼn�X�͍������̖�������邱�Ƃ��ł���̂��A�Ƃ������Ƃł��B

�E�B���i���B���X�j�̓`��
�@�O�q�̒ʂ�A�S�[�e�B�G�̓n�C�l�́u�h�C�c�_�v�i�܂��́u���앨��v�j����q���g�܂����B�Q�l�܂łɈ��p���Ă����܂��B
�@�u����͂��̒n���i�I�[�X�g���A�̂���n���j�ɂ̓��B���X�Ƃ������Œm���Ă���H��`���ł���B���B���X�͌�������������O�Ɏ��ԉłł���B���̉��z�ȎႢ�������͕�̒��ł����Ɩ����Ă��邱�Ƃ��ł��Ȃ��B�ޏ������͎�����S�̒��Ɏ����鑫�ɐ��O�����ŏ\���ɖ��������邱�Ƃ��ł��Ȃ��������̃_���X�̊y���݂����Ȃ����������Ă���B�����Ė钆�ɒn��ɏオ���ė��āA��ʂ�ɌQ�ꐬ���ďW�܂�B����ȂƂ���֏o���킵���Ⴂ�j�͈��ꂾ�B�ނ̓��B���X�����Ɨx��Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�ޏ���͂��̎Ⴂ�j�ɕ��c�ȋ��\���ŕ������B�����Ĕނ͋x�މɂ���������A�ޏ���Ɨx��ɗx��ʂ��Ă��܂��ɂ͎���ł��܂��B����̐��ꒅ�ɏ����āA���ɂ͉Ԃ̔��������ƂЂ�Ђ�Ȃт����{�������āA�w�ɂ͂��炫��ƋP���w�ւ��͂߂āA���B���X�����̓G���t�F�����Ɠ����悤�Ɍ����𗁂тėx��B�ޏ���̊�͐�̂悤�ɐ^�����ł͂��邪�A��X�����Ĕ������B�����Ă����Ƃ���悤�Ȗ��邢���ŏ��A�`���I�Ȃ܂łɈ����邵���B�����Đ_��I�Ȉ������ōK�������悤�ɂ��Ȃ��������Ă���B���̎������_�̛ޏ������ɋt�炤���Ƃ͂ł��Ȃ��B�l���̉ԍ炭���Ȃ��Ɏ���ōs���ԉł��������O�͐t�Ɣ�������ȂɓˑR�Â��j�ł̎�ɗ����邱�Ƃɔ[���ł��Ȃ������B����ʼnԉł͎�ɓ����ׂ����ē�����Ȃ�������т�����ł�����T�����߂�̂��Ƃ����M���e�Ղɐ��܂ꂽ�̂ł���B�@�i�u���Y�̐_�X�E���앨��v�@�n�C�����q�E�n�C�l�^���@����r�v�^��@�i��g���X�j�����p�j
�@�I�[�X�g���A�Ƃ���܂����A�ǂ�������̓X���u�N���̌����`���̂悤�ł��B�n�C�l�̎���ɂ͂܂��n�v�X�u���O�鍑�����݂ł������烈�[���b�p�A���ɓ����̂��Ȃ�̕������I�[�X�g���A�ƌĂ�Ă����̂ł��傤�B
�@���āA���̃��B���X�`���ł����A�n�C�l�̋L�q��f���ɓǂތ��胔�B���X�����͎���ł�����x��ɖ������̂Đꂸ�ɖ�Ȗ�ȕ�ꂩ�甲���o���ėx�苶���Ƃ��������ŁA�j�ɍ��݂��͂炷���߂ɂƂ���ĎE���Ƃ����̂ł͂���܂���B�v�͗x��Ƃ����̂͐��I�G�l���M�[�̔��U�̏ے��Ȃ̂ŁA���I�ȗ~�����������ꂸ�Ⴂ�j���������݂��̐����z���s�����Ƃ����̂��{���Ȃ̂��Ǝv���܂��B�@
�@���̕���̗��ɂ̓J�g���b�N�I�Ȍ����O�̏����̎v�z������悤�ł��B���ꂪ�����O�Ɏ��ʂ̂ł�����A��������Ȃ��������ւ̗~������̉��̎��̂�����قƂ���o��Ƃ����킯�ł��B�c������Ė{���ɕ|���ł��ˁB
�@���ꂪ�u�W�[���v�ł͒j�ɍ��݂������Ă���A�E���̂��ړI�ɂȂ��Ă��܂��B�E�B�������̂悤�ɐ������鎑�������邱�Ƃ͂���悤�ł��B�u�W�[���Ƃ������̃o���G�v�̒��Ń{�[�����g���̓��B���X�ɂ��ď����ꂽ�{�͂قƂ�ǂȂ��Ƃ��Ȃ�����A�B��u�}�C���[�̕S�Ȏ��T�v�����B���X���u���Ă��Ȃ���s���Ȓj�ɗ���ꂽ���ߎ���ł��܂������̗삪�z���S�ƂȂ������́v�ƒ�`���Ă���A�Ə����Ă���̂ł��B
�@�u�W�[���v�ɂ����Ă̓E�B���̐������z���S�I�ɐݒ肵�����Ƃ��h���}�ɐ[�݂�^���A�e�[�}���͂�����ƕ����яオ�点��̂ɗL���������̂��Ǝv���܂��B�����u���I�ȗ~���v�����������Ȃ�A����������֍s���Ă��܂��܂�����ˁB���Ƃ��{���I�Ȃ��̂ł����Ă��A�u���I�Ȃ��́v�͕\�ɂ͏o�����A�ς�҂ɏ�������A�������[������������̂���Ԃ����Ǝv���܂��B

�W�[���̃h���}��
�@�h���}�����D��Ă���Ƃ��Đl�C�́u�W�[���v�B����ł͈�̂ǂ����D��Ă���̂ł��傤���B�܂������Ă���̂́A�x��ւ̏�M���h���}���т��Ƃ����\�z���̂��f���炵���A�Ƃ������Ƃł��B���R�Ɨx��̏�ʂ��W�J����܂�����A�f�B�x���e�B�X�}����������������K�v���Ȃ��A�h���}���Ïk����ĕ\������A�ϋq���������݂܂��B
�@
�@�����Ă�����w�E����Ă���̂́A�ꖋ�Ɠ͑ΏƓI�ɍ���Ă���A�ꖋ�ɂ�����o�����͓ɂ�����h���}�̑O��ɂȂ��Ă���Ƃ������Ƃł��B�u�Â������Ė��������яオ��v�B���̍\���ɂ���ĉ�X�̓h���}�Ɉ������܂�A�Ɋ������܂��B����ł͂��̑ΏƐ��Ƃ͂ǂ̂悤�ȂƂ���Ɍ���Ă���̂ł��傤���B
�@�܂�������ے�����̂��N���X�B�u�W�[���Ƃ������̃o���G�v�Ń{�[�����g���������Ă����܂������A�����t���܂ɂ���Ə\���˂ɂȂ�̂ł��B�܂�ꖋ�͗��h�Ȍ����x�z����g������̌����̕����Љ�B�����ē͏\���˂��ے������I�Ȑ��E�ł��B�ꖋ�̌����Љ�ł͖��ƂȂ炸�j�ꋎ���������̗�I���E�ł͏��̋����z���ɂ���Đ��A����B�ꖋ�Ɠ�ΏƓI�ɕ`���A�ꖋ��O��Ƃ��邱�ƂŁA�̈��̐��A���ς�҂̐S�ɔ����ė�����̂ƂȂ�̂ł��B�i���A�ƌ����Ă��A�����ɂ͔ߌ��Ȃ̂ł����A�����ł̓W�[�����A���u���q�g�̐S����̈���A�Ƃ����Ӗ��Ő��A�ƌ����Ă��܂��B�j
�@�܂��͈ꖋ�̌����̐��E�B�����Ƃ͒m�炸�ɐg���Ⴂ�̗��������������l�̕s����m��A�܂��S�����Ă��̌��ʐg�̂����A����ł����܂��B���̉�X�ɂ͂��܂�s���Ƃ��܂��A�������̒����ł�����A�g���̍��͐�ΓI�Ȃ��̂������̂ł��B����Ȃ̂ɐS�̂��ׂĂ����������҂��u�ϑ������M���v�������Ȃ�āc�B���S�ȏ����W�[���͖{���ɉ��z�ł��B
�@�����ēB�ꖋ�ł���Ȃɉ��z��������ɁA�`���ʂ苰�|�̗H��E�B���ɂ܂łȂ��Ă��܂��A�ǂ��܂ł����z�ȃW�[���B�Ǝv���Ă�����A���z�͂����ŏI���B�W�[���ɂ͏����~���^�ɋt����Ă܂ň�����A���u���q�g����낤�Ƃ��鋭�������܂�Ă���̂ł��B
�@�ꖋ�ł͐g���Ⴂ�̗��ŃV���b�N�������̂ɁA�ł̓W�Z���̕�����������B�����ăA���u���q�g�͗�I���E�ł̓E�B���̊l���ɂ����Ȃ��ł�����ˁB�܂�A���ꂪ�t�]�����̂ł��B�ꖋ�ł̓W�[����苭������ɂ����A���u���q�g�̓N�[�������h�����o�e�B���h�P�ɏo������Ȃ�u�j�͎Љ�I�����v���̂��̂ƂȂ�A�W�[�����ނ��I��ł��܂��܂��B���ꂪ�ł̓W�[���͏����~���^�ɋt����Ă܂ŃA���u���q�g����낤�Ƃ���̂ł��B���̂�����A�j���̗����ɑ���p���̈Ⴂ����������ɂ���Ă���A�����[���ł��ˁB
�@
�@�������W�[���͈ꉞ�E�B���B�����ɖ�������Ηx���ăA���u���q�g��U�f���j�łւƓ�������܂���B�ꖋ�ł̓A���u���q�g���������߂悤�Ƃ���ƒp����ē����Ă����������x��Œj��U�f����̂ł��B���������̒��ł��\���˂ɓ�������A���ԉ҂���������A�����ɏ�������A�|�ꂽ�A���u���q�g�������N�����ė�܂����肵�āA���ɑ̂̔ނɊ��Y���܂��B�����͂܂������h���}���ō��ɐ���オ��Ƃ���B�A���u���q�g�������悤�Ƃ��鈤�̐S�Ɨx�炸�ɂ͂����Ȃ��E�B���̐��̖����ɋꂵ�݂Ȃ���A�W�[���̓A���u���q�g�Ƌ��ɗx��ɗx��̂ł��B�������Ă��邤���ɁA�A���u���q�g�ƃW�[���̐S�͈�ɁB�����ĂS���̏�����E�B�����������������A�ꖋ�ł͒j�̃G�S�Ȗ{�\���ނ��o���ł������A���u���q�g�́A�Ɍ���Ԃŋ��ɂ̐��������ɑ̌�������A�W�[����S���爤����悤�ɂȂ��Ă����̂ł��B
�@�������S���̏��Ƌ��ɃE�B����������͂������ċ���ƁA�W�[���ƃA���u���q�g�ɂ��܂��Z�ސ��E���Ⴄ���̂Ƃ��āA�i���̕ʂꂪ����ė��܂��B��ΓI�Ȍ��Ђɋt����Ă��A���u���q�g����낤�Ƃ����W�[���̐[���z���B�����ĐS����ɂ��Ď��������z���ċ������ꂽ��l�̐S�B�ł����ꂪ�킩�������͉i���ɃW�[�����������B�����[����ΐ[���قǁA�r�������[���̂ł��B������A���u���q�g�����������Ǝv���Ȃ���E�B���Ƃ��Ĕނ�U�f���j�ł֓����W�[���̊����Ƌ��ɁA���̃��X�g�V�[���͊ϋq�̐S��h���Ԃ�h���}�ł���Ǝv���܂��B
���ꖋ�Ɠ̑ΏƐ���
�ꖋ �� �ꏊ ���n�ۂɂ킭�� �͂���ɂ��锖�C�������X ���i���ԑсj �������璋�ԁ@�i���邢�j ��@�i�Â��j �Z�ސ��E �g���Ƃ����g�g�݂����݂��錻���̎Љ�i��Ə����j ���삪�x�z�����I�Ȑ��E�i���R�j ��Q �Љ�I�Ȑg���ƍ���� �����~���^�Ɨx�炸�ɂ͂����Ȃ��E�B���̐� �W�[���̐g�� �g���̒Ⴂ���� ��͂����E�B�� �A���u���q�g�̐g�� �g���̍����M�� �E�B���̊l�� �W�[���̐��� �G�L�Z���g���b�N�ł��낢 ���̂��߂ɂ͏����ɏ|�˂��قNj��� �A���u���q�g�̈� ���� �����݂̂Ȃ炸���_�I�Ȉ��ɂ܂Ŏ��� ���̐��� �Ԑ肢������킩��j�̈��̂��邳�E���������� �����ɋt����Ăł������т����̈��̋����E��ΐ� ���͂ǂ��Ȃ����� ���̔j�]�@�i�A���u���q�g�哱�j ���̐��A�@�i�W�[���哱�j �N���X �M���̐g���������� ��I�Ȑ��E�������\���� ��l�̒ǂ��������� �y�������̂���ꂠ�� �Ⴄ���E�Ɉ��������ꂽ�ނȂ���
�@
������{�E�S�[�e�B�G�ŁE���݂̏㉉�̑���_
�@�u�W�[���v�̕���́u����݊���l�`�v��u�����̌��v�Ɣ�ׂ�Ƃ���قǔłɂ���Ă̈Ⴂ�͑傫������܂���B�������W�[���̎��ɕ����Ƃ��A���u���q�g�̑ԓx�Ȃǂł��Ȃ�Ⴄ���̂��������肵�܂��B�傫�ȉ���͂Ȃ��Ƃ͌����A�e�[�}�����͂�����ƕ\�����邽�߂ɏ�����{��ύX�����_�A�������͌��̋����S�[�e�B�G���̍l���ȂǁA����Ȃ�Ƀ��@���G�[�V�����͂���܂��̂ŁA����Ⴂ�̖ڗ��_�����Љ�Ă����܂��B
�Ȃ��A�u�W�[���v�ɂ����Ă͕�����܂Ƃ߂�ۂɂ͓���́`�łł͂Ȃ��A������{����{�Ƃ��Ȃ���A��������ύX����Ă��܂����ӏ��͌��ݑ����s���Ă��鉉�o�ɕύX���܂����B
������{ �S�[�e�B�G�� ���݂̏㉉ �A���u���q�g�̓W�[���������Ă����̂� �����Ă��� �����Ă��� �����Ă������M���������� �W�[���̌��N��� �S�������� ���N �����Ă��͐S�������� �W�[���̎��� �x��ɂ��S������ ���ɂ�鎩�E �S�����삩���E���������� �q�����I���̐��� ���i�[�����\�B�W�[���̎��ɍۂ��Ĉꉞ����͂��邪�A�W�[���̕�𔖋C�������v���B �A���Ŏc�E�A���S�Ȉ��� ����������W�[�������ɒǂ���������ƌ�����A�Ԃ�������p�^�[���������B �o�e�B���h�P�̐��� �D�������e �D�������e �M���̖��炵���C�ʂ�������ʂ������� �W�[���̎��̏�ʂɂ�����A���u���q�g�̍s�� ���Ŏ��E���悤�Ƃ��đ���Ɏ~�߂���B�C����������ʼn��̎҂ɘA����đޏ� ��]�ƔߒQ�ɂ���Ă��� �q�����I����ӂ߂Ďa�肩����B�����ڂ��������ē�����悤�ɑޏ� �E�B�������̑ԗl ���E������W�܂��ė��Ă���A�����ߑ��Ŗ������x��x��i�h�D�E�E�B���ɂ̓Y�����ƃ��C�i�Ƃ����Ƃ������O�����Ă���B�j ���E������W�܂��ė��Ă���A�����ߑ��Ŗ������x��x��i�h�D�E�E�B���̓Y�����ƃ��C�i�j
���E�B���ɂȂ�͎̂��E�҂݂̂Ƃ��Ă����S���������̃��}���e�B�b�N�`���`���œ������^�B�����x���x�� ���X�g�V�[���ɂ�����W�[���̏����� �Ԃ̑��̒��ɖ�����čs�� �ԂƑ��̒��ɖ�����čs�� ��Ɉ����߂���� ���X�g�V�[�� �E�B���t���[�h���o�e�B���h�P��A��ēo��B�A���u���q�g�̓W�[���Ƀo�e�B���h�Ɉ��������ƌ����A�P�Ɍ������Ď�������L�ׂ� �A���u���q�g�͒T���ɗ����E�B���t���[�h�ƃo�e�B���h�̘r�̒��ɓ|�ꍞ�� �A���u���q�g�ƃW�[���̓�l�����̉i���̕ʂ�̃V�[��
�@�����̕����Â����}���e�B�b�N�ł��ˁB���ɏ����̌�ɃS�[�e�B�G�����������W�[������͕��i�Ȃǂ̕`�ʂ��ׂ����������Ɩ��̐��E�ɋz�����܂ꂻ���B�������S�[�e�B�G�ł��������낢�̂́A�������������I�ȕ���̒��Ɂu�������J�����b�^�͌����ɉ����������̂ł���B�����A���̌��t�ɂȂ�Ȃ�������I�v�݂����Ȓ��q�̃J�����b�^�E�O���W�^�̂��͂���Ƃ���ł��B��قǔM�������Ă����̂ł��傤�B
�@���ꂪ�i�X�Ǝ��I�ȐF�ʂ͔���Ă����A�ꖋ�Ɠ̑Δ䂪���͂����肵�ăV���v���ȍ��ƂȂ�܂����B���̗���̒��œo��l���̐��i��s���p�^�[���������Âω������̂ł��B
���݂̘_�_
�@�����Č��݂ł͓o��l���̐��i�A�S��ɂ���������߂��㉉���ɔ����Ɉ���Ă��܂��B�ǂꂪ�������Ƃ��Ԉ���Ă���ł͂Ȃ��A���ꂼ��̃_���T�[�≉�o�Ƃ̌��ł�����A�D�݂̖��Ȃ̂ł����B�ȉ��A�݂�Ȃ��y�����ӌ����킹�Ă���_�����������Ă����܂��B
�@�@�A���u���q�g�̓W�[���������Ă����̂����Ă����̂�
�@����̓Y�o����l�C�̘_�_�ł��B������{��S�[�e�B�G�łł́u�����Ă����v�ƂȂ��Ă��܂��B������{�́u�B��̈���̑Ώہv�Ə����Ă܂����A�S�[�e�B�G���Ȃǂ́u���A���O�ɑ���͋��������������ׂĂ��A�W�[����I�v�Ƃ܂ŏ����Ă����܂��B���݂ł��E���W�[�~���E�}���[�z�t���̃A���u���q�g�͂��̃^�C�v�ł��B
�@���̍l�����͂ƂĂ����}���e�B�b�N�B������������Ɛ�������ɋꂵ���_���B�Ȃ��Ȃ�A���u���q�g�͎����̑z���ɖ����ł��W�[���̂��Ƃ܂Ő[���v������Ă͂��Ȃ�����ł��B���ӂ�����邱�Ƃ��ł��Ȃ��̂ɐl�̐S��~������̂͂����Ȃ����ƁB�A���u���q�g�͍��M�Ȑg���̍���҂܂ł����M���ł�����A�W�[���ƌ���邱�Ƃ͂���܂���B����ł���Β����ȏ]�҃E�B���t���[�h�����������悤�ɁA�_���ɕϑ����Ĕޏ��̏��^�ȐS��D�����肵�Ă͂����Ȃ��̂ł��B����ł�����ς�ޏ��ƈꏏ�ɂ������Ƃ����̂Ȃ�A�M���炵�����Ƃ��Ĉ͂��悩�����̂ł��B�ŏ�����M���Ə��Ƃ��Ă���Ȃ�̈������Ă���̂悤�Ȕߌ��͋N����Ȃ������Ǝv���܂��B�����M���Ƃ킩���Ă���A�W�[��������Ȃ�ɉ������ē�l�̊Ԃɂ͍ŏ�����ǂ��ł��Ă��܂��܂�����A�����ƃA���u���q�g�͂��ꂪ���₾�����̂ł��傤�B���������ȏ������g������苎�����f�̎����ɖ����ɂȂ��ĐS�̂��ׂĂ������l�q�ɁA�ނ��܂������ɂȂ蓩�����Ă����̂��Ǝv���܂��B
�@����ȕ��Ɏ����̗��ɖ����ɂȂ��Ă��āA�W�[���̗���������߂���̂��Ƃ܂ł͍l���Ă��܂���A�v���������N�[�������h�����o�e�B���h�P�������ƁA���]���Ă��܂��đΏ����ł��Ȃ��Ȃ��Ă��܂����̂ł��B�u�����Ă����v�̗���ɂ������Ƃ��Ă��A���̈��̐����͖����ɂȂ��ė����Ă���Ƃ������̂ŁA�̍Ō�Ɍ����悤�Ȑ[�����_�I�Ȉ��Ƃ͈Ⴄ���̂��Ǝv���܂��B
�@����ɔ�ׂČ��݊���Ƒ����u���Ă�����ł����v���ƈꖋ�Ɠ̃R���g���X�g�͂��N���ł��B�N�[�������h�����o�e�B���h�P���o�ꂵ�����̔������[���ł��܂��B�̌��I���ʂ������邽�߂̍����I�ȉ��߂ł��ˁB
�@�����������I�ł���Ɠ����ɃS�[�e�B�G�����������Â����郍�}���e�B�V�Y�������Ȃ�g�[���_�E�����Ă��܂��܂��B�Ԑ肢�̏�ʂ��������C���`�L�L�����Y���܂��B�p�炤�W�[�������C�X�i�A���u���q�g�j���ǂ�������Â����̃V�[�����u�Ԃ������Ƃ������݂���v�݂����Ȋ����ɂȂ肩�˂܂���B�������̉��߂��ƃW�[���������̃A���u���q�g�̔����Ƃ��ẮA�q�����I���ɔ������肵�čŌ�͓����o���Ƃ����̂��҂����肫�܂��ˁB����ɂЂ������q�����I�����E����ăA���u���q�g��������͔̂[�����ɂ����Ȃ�܂��B�����Ė{���Ɉ����̂́u�_���ɕϑ��v���āu���S�ȏ����̐S��D�����v�M���̃A���u���q�g�Ȃ�ł�����B
�@�����ł́u�ڂ�������v���܂Ƃ߂�ɂ��A���݂̉��o�ƈ�ѐ����������邽�߂Ɂu���Ă����v�ɋ߂����_�ł܂Ƃ߂܂����B�������ɒ[�ɂǂ��炩�A�Ƃ������͂�����ƞB���Ɉ����Ă���悤�ł��Ă܂ݐH�����Ă���悤�ł������āc�Ƃ����̂��\���Ƃ��Ă͂������ȂƎv���܂��B�����Đl�Ԃ͂��������B���Ȃ��̂����A���̕����j�̂��邳�ƐF�C���悭�o�ăA���u���q�g�����͓I�ɂȂ�Ǝv���܂�����B
�A�@�s���Ȓj�������邩
�@�����Ă���Ԃ͏����������Ƃ�ƃq���C���ɂȂ��Ă��܂����A����ꂽ�ƂȂ�ƌ����ɖ߂��ė��܂��B�����Ȃ�Ə����͎������g����邱�ƂɔM�S�ɂȂ�܂��B�����āu����ł����Ȃ��������Ă��v�Ȃ�Č�������A���ꂱ���j����y�������ĂƂ��Ƃp�����̂��I�`�ł�����B�����ɂƂ��Ēj���͈����ׂ����݂ł͂���܂����A�Â��݂Ă��Â₩���Ă������܂���B�j���̈��Ƃ͂��Ƃ��Ǝq�����c�����߂̂��̂ł���A���̂��߂ɂ͌����Ȃ���Ȃ�Ȃ��̂ł��B����̏o�����������蔻�f���Ď���������Ɍ������悤�ȍs��������c�����Ɏq������Ă����A�����������܂��������������߂ɂ͕K�v�Ȓm�b�ł��B
�@���āA�W�[���̂悤�Ɉ����鍥��҂��g�����U���Ă���A���ꂩ�Ȃ�Ȃ��悤�ȑ���Ɠ�҂������Ă����c����Ȏ��ɂȂ�����N�����ăV���b�N�ł��傤�B�����̓��I���E���j��Ă��܂��܂�����A�������g��ۂ��Ƃ������Ȃ�܂��B�C�������Ă��܂�����A���E���Ă��܂�����B���Ƃ��������������ė����������Ƃ��Ă��A�Ȃ������𗠐����̂��A�Ƒ����ӂ߂����Ȃ�܂��B����ȕs���Ȓj�Ȃǂ������̕��ł��f�肾�Ǝv��������̂ł����A�Ȃ��Ȃ������������܂���B�N�̍��Q��i�������Ōܐ��B��łł��j��������A���ȃX�g�[�J�[�ɂȂ鎖���B�����܂ł����Ȃ��Ă������Ă��̐l�͂���ς葊������݂܂�����A�s���ł������j�����n�ɗ������ꂽ�ꍇ�A�g�̂��Ăł����������Ǝv���l�͋H�ł��傤�B�u���𗠐�������v�Ǝv���l�������̂ł͂Ȃ��ł��傤���B�܂��A�s���Ȓj�̂��ƂȂǑ�Ȏv���o�ł͂���܂���A�����o�ĂΖY��Ă��܂��Ǝv���܂����ǂˁB
�@����Ȃ�A�Ȃ��W�[���͂���ȂɃA���u���q�g���������́H�Ǝv�����������������ł��傤�B�m���ɃW�[���̂悤�ȏ����������ɂ͂��Ȃ��ƒf�����邱�Ƃ��ł��܂��A����ς肱���͂ЂƂA���̃S�[�e�B�G���̂����t�����Љ�Ă��������Ǝv���܂��B
�u�o���G�͂܂�����������{���Ƃ��A���������ނ��떲�z���琶����̂ł���B�����܂Ō��z�I�Ȃ��̂ł���A���������X�ŏo��悤�Ȍ������Ƃ����̂łȂ���A�o���G�͂قƂ�Ǒ��݂��Ȃ��B�o���G�͎��l�̖���^���Ɏ~�߂����̂��B�v�i�u�P�X���I�t�����X�E�o���G�̑�{�E�p���I�y�����v�@���ѐ��i�^���@�c���`�m��w�o�ʼn�@�����p�j
�B�@�q�����I���ɂ���
�@���݂̏㉉�ł̓q�����I���͂���ȃ��c�����ǁA����ȂɈ����킯�ł͂Ȃ��A�ŎE����Ă��܂��̂͋C�̓ł��Ƃ����ӌ�������܂��B�m���Ƀq�����I���̖\�I�̎d���͎v����肪����܂���B�����{���ɃW�[���������Ă���̂ł���A�W�[���ɂ͖ق��Ă����āA�A���u���q�g�Ɂu�ޏ��ɂ͖ق��Ă��̂܂�����v�ƌ����悩�����̂ł��B�i�������ł������郍�C�X�����Ȃ��Ȃ����Ȃ�A�W�[���͔߂��݂̂��܂莀��ł��܂�����������܂��j���i�ɂ���ꕜ�Q�S�ɔR���Ďc���ȍs�ׂɏo��̂͐l�Ƃ��Ēp�����������Ƃł��ˁB
�@����ł��E�����قǃq�����I�������������Ƃ͎v���܂���B�����ƌ����ΐg�����U���ăW�[���̐S��~���������A���u���q�g�̕�������ۂLj������A���̓G�Ƃ��ăE�B���Ɏ��E����Ă��d�����Ȃ��Ǝv���܂��B�Ȃ̂ɁA�Ȃ��c�B
�@���̓����͂�͂�S�[�e�B�G���ɂ���̂ł͂Ȃ����A�Ǝv���܂��B�O�q�̒ʂ�A�ꖋ�ɂ̓T�����W�����W���̕M���啝�ɓ���܂������A�͂قڃS�[�e�B�G�̍\�z�ʂ�ɂȂ����A�Ƃ������Ƃł��B�����ăS�[�e�B�G���̓q�����I�������l�Ƃ��Đݒ肵�Ă����̂ł��B�u�h�C�c�̓`���̒��ł��A�_��I�Ŏc�E�Ȏ�l�̈�l�ł���q�����I���v�Ƃ��u�q�����I���̋]���ƂȂ����D���������ׂ����v�Ȃǂƕ\�����Ă��܂��B���Q�S�ɔR�����q�����I�����W�[���ƃA���u���q�g���a��E�����Ƃ����Ȃ炱�̕\�����[���ł��܂����A�q�����I���̓A���u���q�g�����Ă������Ƃ��W�[���ɓ˂����������Ȃ̂ɁB
�@�v�̓S�[�e�C�G���́u�W�[���v��O���O�����}���e�B�b�N�ȁu�M���̐N�Ɖ��ȑ����̗�����v�ɂ����������̂ł��傤�B�ł�����S�[�e�B�G�łł͍ŏ�����A���u���q�g�̓W�[���������Ă������ƂɂȂ��Ă��܂����A�W�[��������ł��܂��������u��]�ƔߒQ�ɂ���Ă���v���ƂɂȂ��Ă��܂��B�܂�S�[�e�B�G���̓W�[���̎��Ɋւ��ăA���u���q�g�����҂ɂ������Ȃ��̂ł��B
�@���ꂶ�Ⴀ�N�������́A�Ƃ������ƂɂȂ�܂����A�S�[�e�B�G���̓����́u�q�����I���v�Ȃ̂ł��B������Ńq�����I�����E�B���ɎE�����͈̂��̓��R�̕Ƃ������ƂɂȂ�悤�ł��B�S�[�e�B�G�łɂ́u���̗҂����l�����ꂽ�ꏊ�ɒ��Ԃ��猩�̂Ă��A�ЂƂ�ڂ����ɂȂ����q�����I���ɍ����������̎�������ė����A�ƍ߂̈ӎ������̎����ɂ����₭�̂��v�Ƃ���܂��B
�@�������Ĉ��l�q�����I���͓ŃE�B���ɂƂ�E����܂��B�q�����I���̐l�������̂��͎̂���Ƌ��ɕω����Ă����̂ł����A���̏�ʂ͂ǂ������킯���A�ς����Ȃ������̂ł��ˁB
�@���݂́u���}���e�B�b�N�ȗ�����v�����V���v�������ʓI�Ƀh���}��\�����邽�߂Ɉꖋ�Ɠ̃R���g���X�g���͂�����ƕ\�������悤�ɂȂ��Ă��܂��B�����ăA���u���q�g�͋M���̗V�тƂ��ăW�[����U�f���Ă���A�W�[���̎��ɍۂ��Ă��q�����I���ɔ������肵������ɂ��̏ꂩ�瓦���o�����o�������Ȃ�܂����B
�@���̕��q�����I�������l�ł���K�v�͂Ȃ��Ȃ�܂����B�����ăq�����I���͌���ɂ���A�W�[���̕�ɂ��ԑ��������悤�ɂȂ��Ă��܂��B�W�[�����A���u���q�g�̌��Ŏ��E���悤�Ƃ��������A�q�����I�����~�߂鉉�o�������ł��B�i������{�ł͕�e�̃x���g���~�߂Ă��܂��B�j
�@����Ȃ̂ɑ��ς�炸�ł̓q�����I�����E�B���ɎE����Ă��܂�����A�����Ƃ����̂͂��ׂĂ��Ȃ��܂Ƃ߂�͎̂���̋ƂȂ�ł��ˁB
�@���݂̉��o�ł͓��R�̕Ƃ��Ăł͂Ȃ��A�E�B���̋��낵�����������{�Ƃ��ăq�����I�����]���ƂȂ��ʂ������Ă���̂��Ǝv���܂����B
![]()
�C�@�q�����I���͂Ȃ����ݗl�ɑ��Ă���Ȃɉ����Ȃ̂��H
�@�q�����I���̓��C�X�����͌��݃A���u���q�g�ł��鎖���킩���Ă������������ȑԓx���Ƃ��Ă��܂��B���ˉ���ł���A���Ă������������ł݂�ȁu�͂͂����v�A�ƂЂꕚ���̂ɁB�Ȃ��c�H
�@��������Ȃ�ɍl���Ă݂܂����B��߂̓����́A�u�ǂ����o���G�̂��b�Ȃ���A���ł�����v�Ƃ����P���Ȃ��́B�����Ă�����́A���̒n��̐����I����l�������̂Ȃ̂ł����A�X�ԃq�����I���͌��݃A���u���q�g�Ɍق��Ă���킯�ł͂Ȃ��A�Ƃ����l�����ł��B
�@�V���W�A�͂��̗̗L�����߂����đ������₦�Ȃ������y�n���B�P�O���I�ɂ̓|�[�����h���Ƃ��x�z���Ă����̂��A�_�����[�}�鍑�Ƃ����ɂ₩�Ȗ��_�卑�̊����A���̎x�z���̓{�w�~�����ƁA�����ă{�w�~�����ʂɂ����n�v�X�u���N�ƂɈڂ��Ă������̂ł��B
�@�������A�_�����[�}�鍑�Ƃ����̂́A�t�����X�Ȃǂ̐�Ή����Ƃ������āA�c��Ɛl���̊Ԃɂ�������̂�₱�������Ԍ��͂���݂��钆���I�Ȑ����`�Ԃł��B�ł�����A�V���W�A���̗L�����{�w�~�A���Ƃ�n�v�X�u���O�ƂɈڂ��Ă��A���ۂ̓|�[�����h�̉��Ƃ��������Ă����悤�ł��B
�@�Ƃ����킯�ŁA�q�����I�����{�w�~�A���ƁA�n�v�X�u���O�ƁA�|�[�����h���Ƃ̂ǂ��Ɏd���Ă����̂��A�킩��܂��A���炭�A���u���q�g�̓q�����I�����d���Ă����̂Ƃ͈Ⴄ�n���̎x�z�ҁA�����钆�Ԍ��͂Ȃ̂ł��傤�B�Ⴆ�Ό��݃A���u���q�g���|�[�����h�n�Ȃ�A�q�����I���͐_�����[�}�鍑����C�����ꂽ�X�ԁA�݂����Ȋ����ł��傤���B
�@�����l����ƁA�u�ӂ�A�M���߁B�v�Ǝ����ɕ�V��^���Ă����ł��Ȃ��A�����В����Ă��邾���ŁA��肽������̃A���u���q�g���y��̂��m����C�����܂��B
�D�@�o�e�B���h�P�ɂ���
�@
�@���l�̃S�[�e�B�G���̓o�e�B���h�P��D�������e�ł���A�Ƃ��܂����B���M�Ŕ������P�N���D�������e�ł���̂Ȃ�A�Ȃ�ŃA���u���q�g�ɂƂ��ăW�[�����u�B��̈��̑Ώہv�ɂȂ�̂��Ȃ��A�ƕs�v�c�Ɏv���̂ł����B�S�[�e�B�G���̓��}���e�B�b�N�E�o���G�̎^���҂Ƃ��āA�O���O�������ɖ���ǂ����߂Ă�����ł��傤�ˁB
�@�����ēŃW�[�����ԂƑ��ɖ�����ď�������̓A���u���q�g�̓E�B���t���[�h�ƃo�e�B���h�P�̘r�̒��ɓ|���A�܂��̓W�[���Ɂu���̕��ɐ����Ȉ�������Ă��������v�ƌ����ăo�e�B���h�P�Ɏ�������L�ׂē|��܂��B���ۂ̃S�[�e�B�G�����r��邱�ƂȂ��������o�����[�i�ɔM�������Ă����悤�ł�����A�j�̖��Ƃ��ăA���u���q�g�ɂ����z�I�ȏ������W�[���̌�ɗp�ӂ�����ł����˂��B
�@�S�[�e�B�G���͍�������̔����D���ŁA�u�֕P�v�̃��f���Ƃ��ėL���ȃ}���[�E�f���v���V�̋q�̈�l�ł��������悤�ŁA�u�����͔������Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�v�ƁA���������Ă����悤�ł��B
�@���x�������Ă���ʂ�A���オ�i�ނɂ�ăh���}�̓V���v���ɐ�������Ĉꖋ�Ɠ̃R���g���X�g�͂͂�����Ƃ��Ă��Ă��܂�����A���̒��Ńo�e�B���h�P�̐��i���ς���Ă��܂����B�M���̖��Ƃ��Ă̋C�ʂ̍������\�������悤�ɂȂ��Ă����̂ł��B
�@�s�[�^�[�E���C�g���o�̉p�����C�����o���G�łł͋C�ʂ�����������Ƃ킪�܂܂Ȋ����ɕ\������Ă��܂��B���ꂶ�Ⴀ�A���u���q�g���W�[���ɖ��������߂�̂��킩��Ȃ��A�Ǝv���悤�ȃo�e�B���h�P�ł��B
�@�l���Ă݂�Α���Ƃ����̂͌N��܂��͂��̈ꑰ�̒j���̂��ƂȂ̂ŁA���̖��ł���o�e�B���h�P�̓{�w�~�A���Ƃ��n�v�X�u���O�Ƃ̌��������P�N�Ȃ̂�������܂���B�����l����ƋC�ʂ������Ă����Ȃ����邵�A�A���u���q�g�����ꂵ���������ăW�[���ő������������Ǝv���̂������ɂ����肻���Ȃ��Ƃł͂���܂��ˁB
�@���̂悤�Ɏ���̗���̒��ŋM���炵������������Ă����o�e�B���h�P�ł����A�S�[�e�B�G�����m������Q�����Ƃł��傤�B����A�{�邩���B�Ȃ��Ȃ�S�[�e�B�G���̓o�e�B���h�P�Ɏ��܂ŕ����Ă���̂ł��B�u���Ă���������̏��l��v�Ŏn�܂邻�̎��͔������̍^���Ńo�e�B���h�P���^�����Ă��܂��B
�@���q�d�v���̉���ɂ��ƁA�W�[�������������J�����b�^�E�O���W�Ɏ��������S�[�e�B�G���́A�o�e�B���h�P���������t�H���X�e�[���Ƃ����o�����[�i�ɈԂ߂Ă�����Č��C�����߂����̂ŁA���̊W������̂�������Ȃ��A�Ƃ������Ƃł��B
�E�@�W�[���͎��E��
�@������{�͔���I�Ɏ��E���悤�Ƃ����Ƃ�����e�̃x���g�Ɏ~�߂��Ă��܂��B�����Ă��Ƃ��Ǝォ�����S��������Ď���ł��܂��̂ł��B�ŋ߂̏㉉�����̃p�^�[���������悤�ł��B�i���E���~�߂�̂̓q�����I�����A���u���q�g�ł����j�������S�[�e�B�G�͈Ⴄ�ӌ��ł��B�S�[�e�B�G�̓��ɂ͂����܂ň�Ӓ��x��ʂ��قnj��C�ȏ����̃C���[�W�������������̂ł��傤�B���������������S���爤���鍥��҂ɗ���ꂽ�Ƃ͂����A���ꂾ���Ŗ��𗎂Ƃ��Ƃ����͕̂s���R�ł��B������S�[�e�B�G�̓A���u���q�g�̌��Ŕ���I�Ɏ��E�������Ƃɂ����̂��Ǝv���܂��B
�@�l���Ă݂�A�������_���̖����x�肪��D���Ȃ̂ɐS��������Ƃ����̂͂�����Ɩ���������C�����܂��B��ʓI�ɋM���̖�������Ŕ_���̖��͂͂�ƌ��C�Ƃ����p�^�[���������ł�����B�������x��̑�D���Ȗ��Ȃ̂ł�����ˁB������S�[�e�B�G�̕������R�Ƃ����Ύ��R�Ȃ̂ł��B���������͓̏\���˂̃V�[���ɂ���̂��Ǝv���܂��B�\���˂�����Ă����Ƃ����̂͌h�i�ȃL���X�g���k�����炾�Ǝv���܂����A���E�̓L���X�g���ł͋ւ����Ă���͂��ł��B�ł����玩�E�҂��\���˂ɏ��������߂�̂͂܂����̂ł͂Ȃ��ł��傤���B�W�[�����n��ꂽ�P�X���I���ƌ����L���X�g���͂܂��܂��l�X�̐����������������Ă����̂��Ǝv���܂�����B
�@�Ƃ����킯�ŁA����ς�u�W�[��������{�S��������v�̕����܂����͏��Ȃ��̂��Ǝv���܂��B�x�肪��D���ŐS�����ア�����c�Ӂ`��B�������ȁB�������A����Ȃ̂�����I�c����ȂƂ���ł��傤���B
�F�@�W�[���͂��ꂩ����E�B���ł��葱���邩
�@������������N�͍��̂Ƃ���ǂ̖{�ł��C���^�[�l�b�g��ł��ǂ��Ƃ�����܂���B���������̊����̃��X�g�V�[���̌�A�v�킸�l���Ă��܂��̂ł��B�ʂɃ~���^����j�傳�ꂽ�Ƃ����V�[�����Ȃ��Ƃ��납��l����ƁA�W�[���͂��ꂩ����E�B���Ƃ��ĎႢ�j�ɂƂ���ĎE��������̂��낤���c�B
�@�������u�}�C���[�̕S�Ȏ��T�v�I�ɍl����ƁA�E�B�������͗����č��݂ɔR���A�j�ɕ��Q���Ă���킯�ł��B����W�[���͓ł̏o������ʂ��ăA���u���q�g�ɐS���爤�����悤�ɂȂ����̂ł�����A�W�[���̍��͂������薞�����Ă��͂≻���ďo��ȂǂƂ������Ƃ͂Ȃ��Ȃ����̂ł͂Ȃ��ł��傤���B���Ƃ��Ɠ̍ŏ����畜�Q�S�ɂƂ����Ă͂��܂��B�����Ƃ��̂܂ܕ�̉��ւƈ����߂��ꂽ�W�[���͈��炩�ȉi���̖���ɂ����̂��Ǝv���܂��B
�@�@�Ƃ܂��A���͂��̂悤�ɍl�����̂ł����A���̂�����͐l�ɂ���čl�����͂��ꂼ��ł��傤�B����ȕ��ɂ��̊����̃��X�g�V�[���̌��z�����Ă݂�ƁA�܂�������y���݂��L�����Ă����܂��B�B�����Ȃ�A���̒N�̂��̂ł��Ȃ��A���̐l���g�́u�W�[���v���S�̒��ɖL���ɍL�����čs�����Ƃł��傤�B
�W�[���Ƃ������̃o���G�@�@�@�V�����E�{�[�����g�^���@�@�����a�Ɓ^��@(�V���فj
�@�@�@�@�i������{�����^�j
�P�X���I�t�����X�E�o���G�̑�{�p���I�y�����@�@���ѐ��i�^���@(�c���`�m��w�o�ʼn�j
�@�@�@�@�i������{�����^�j
���Y�̐_�X�E���앨���@�@�n�C�����q�E�n�C�l�^���@����r�v�^��@(��g���X�j
�o���G�a���@�@��؏��^���@(�V���فj
�@�@�@�@�i���́w�u�W�[���v�͂ǂ������o���G���x�͂ƂĂ��[�����Ă��Ă������낢�ł��j
���X�o���G�Ȃ�قǂ�������ǖ{�@�@���q�d�v�^���@�i�������y�Ёj
�@�@�@�@�i���^�́w���ꂪ�u�W�[���v���x�͂l�h�x�t�f���R�����ŎQ�l�ɂ����S�[�e�B�G�łł��B�o�e�B���h�P�ɕ����鎍�����^�j
�c�u�c�W�[���@
�@�@�@�@�~���m�E�X�J���������i�P�X�X�U�N�j�@�@
�@�@�@�@����U�t�@�@�@�p�g���X�E�o�[��
�@�@�@�@���y�@�@�@�@�@�@�A�h���t�E�A�_��
�@�@�@�@�z���@�@�@�@�@�@�W�[���F�@�@�@�@�A���b�T���h���E�t�F��
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�A���u���q�g�@�@�}�b�V���E���b��
�@�@�@�@�������@�@�@�@�@�V����
�c�u�c�W�[��
�@�@�@�@�~���m�E�X�J���������i�Q�O�O�T�j
�@�@�@�@����U�t�@�@�@�C���F�b�g�E�V�����B��
�@�@�@�@���艉�o�@�@�@�t���[�����X�E�N���[��
�@�@�@�@���y�@�@�@�@�@�@�A�h���t�E�A�_��
�@�@�@�@�z���@�@�@�@�@�@�W�[���F�@�@�@�@�X���F�g���[�i�E�U�n����
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�A���u���q�g�F�@���x���g�E�{�b��
�@�@�@�@�������@�@�@�@�@�s�c�j�R�A�������
�c�u�c�W�[��
�@�@�@�@�p�����C�����E�o���G�����i�Q�O�O�U�N�j
�@�@�@�@����U�t�@�@�s�[�^�[�E���C�g
�@�@�@�@���y�@�@�@�@�@�A�h���t�E�A�_��
�@�@�@�@�z���@�@�@�@�@�W�[���F�@�@�@�@�@�A���[�i�E�R�W���J��
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�A���u���q�g�F�@�@���n���E�R�{�[
�@�@�@�@�������@�@�@�@�n�o�t�r�@�`�q�s�d
�@�@�@
�W�[���@�i�m�g�j�|�p������^��j
�@�@�@�@�`���C�R�t�X�L�[�L�O�����o���G�c�@�i�Q�O�O�U�N�@���@����������فj
�@�@�@�@����U�t �@���I�j�[�h�E�������t�X�L�[�A�E���W�~�[���E���V�[���G�t
�@�@�@�@���y�@�@�@�@�@�A�h���t�E�A�_��
�@�@�@�@�z���@�@�@�@�@�W�[���F�@�@�@�@�@�A���[�i�E�R�W���J��
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�A���u���q�g�F�@�@�}�j�G���E���O��
�W�[���@�i�N���V�J�W���p���ɂĕ����j
�@�@�@�@�A�����J���o���G�V�A�^�[�i�P�X�U�V�N�j
�@�@�@�@�U�t�@�@�@�@�@�f�B���B�h�E�u���A�[
�@�@�@�@���y�@�@�@�@�@�A�h���t�E�A�_��
�@�@�@�@�z���@�@�@�@�@�W�[���F�@�@�@�@�@�J�����E�t���b�`
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�A���u���q�g�F�@�@�G���b�N�E�u���[��
�W�[���@�i���C���j
�@�@�@�@�`���C�R�t�X�L�[�L�O�����o���G�c
�@�@�@�@�Q�O�O�W�N�@�X���P�Q���@���@�䂤�ۂ��ƃz�[��
�@�@�@�@����U�t�@�@���I�j�[�h�E�������t�X�L�[�A�E���W�~�[���E���V�[���G�t
�@�@�@�@���y�@�@�@�@�@�A�h���t�E�A�_��
�@�@�@�@�z���@�@�@�@�@�W�[���F�@�@�@�@�@�ē��F�����@�@�@�@�@
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�A���u���q�g�@�@�}�j�G���E���O��
�W�[���@�i���C���j
�@�@�@�@�~�n�C���t�X�L�[����o���G�c�i���j���O���[�h�����o���G�j
�@�@�@�@�Q�O�O�X�N�P���X���@���@�I�[�`���[�h�z�[��
�@�@�@�@����U�t�@�@�j�L�[�^�E�h���O�[�V��
�@�@�@�@���y�@�@�@�@�@�A�h���t�E�A�_��
�@�@�@�@�z���@�@�@�@�@�W�[���F�@�@�@�@�@�C���[�i�E�y����
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�A���u���q�g�F�@�@�A���h���C�E���t�j���[�N�@
�E�B�L�y�f�B�A�u�V���W�A�v�̍���


���̃y�[�W�̕ǎ��A�摜�̓T�����E�h�E���r�[����i���łɕ��j���炢�������܂����B
Copyright (c) 2009.MIYU