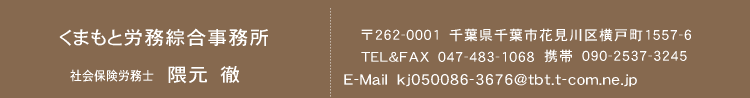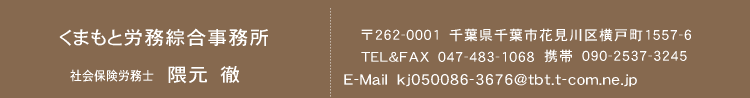| 1.労働契約時の労働条件の明示について |
「事業主が人を雇用する際には労働条件を明示しなければならない」と聞きました。
当社では、従業員を雇用する際に、賃金や労働時間、休日などの労働条件について口約束だけで合意し、契約書などの書面は交わしていません。口約束だけでは問題があるのでしょうか。 また、当社では従業員が10人もおりませんので就業規則を作らなくてもよいと聞いたのですが本当に作らなくてもよいのでしょうか。
|
使用者と労働者が合意していれば、仮に口約束だけでも労働契約としては有効に成立します。しかし、口頭のみでの労働契約の締結は、将来のトラブルの原因となりますので、書面で行われることが望まれます。
労働基準法では、使用者が労働者を雇い入れる際には、労働条件を明示する義務を定めていますし、そのうち、賃金、労働時間、休日、退職など一部の項目は特に書面で明示することが義務づけられています。
ご質問のケースでは、事業主は法律に違反していることになりますので、従業員を雇用する際には、必ず労働条件を明示するようにしてください。
また、従業員が10人未満の事業所では就業規則の作成義務はありませんが、労務管理上、就業規則を作成することをおすすめします。 |
| 2.作成義務のある労務関連資料について |
| 従業員5人の会社を経営しています。法律上作成が義務づけられている労務関係書類にはどのようなものがあるのでしょうか。そして、その書類はどれぐらいの期間保存しなければならないのでしょうか。 |
| 労働基準法では、使用者は、各事業場ごとに労働者名簿と賃金台帳を作成しなければなりません。また、労働者名簿、賃金台帳及び雇入、解雇、災害補償、賃金その他労働関係に関する重要な書類については3年間保存しなければならないとされています。 |
| 3.就業規則の意義と作成について |
私は、従業員数20名の会社を経営しています。
従業員には、入社当初に各自に対し賃金額、勤務時間などの労働条件を提示しておりますが、会社全体としての決まりはありません。月日の経過とともに、採用時期によって労働条件が微妙に異なるケースも発生しており、従業員の中には少なからず不満をもつ者もいるようです。
従業員に安心して働いてもらうためにはどうすればよいでしょうか。 |
就業規則は、そもそも労務管理の基準となるものであり、労働者の労働条件を明確かつ公平にするとともに、企業秩序を維持するためのルールとしての役割があります。
また、常時10人以上の労働者を使用している使用者は、労働者の労働条件等を定めた就業規則を作成し労働基準監督署に届け出ることが義務づけられています。早期に就業規則を作成して届け出るようにしてください。 |
| 4.法定労働時間と時間外勤務等について |
当社は、従業員30名で事務機の販売業を営んでいます。
休日は土曜日と日曜日で、勤務時間は朝9時からタ方5時までとし、そのうち12時から1時までが昼休みと就業規則で定めています。
従業員から、タ方5時以降については残業(時間外勤務)となり、割増賃金を支払う必要があるのではないかと言われましたが、割増賃金を支払わなければならないのでしょうか。 |
労働基準法では、1日の労働時間は8時間以内、1週の労働時間は40時間以内と定められています。労働時間とは、休憩時間を除く実労働時間のことです。従って1日の実労働時間が8時間を超えず、1週の実労働時間が40時間を超えなければ労働基準法上の割増賃金の支払義務は発生しません。
ご相談のケースでは、昼休み休憩の1時間を除く実労働時間が7時間であるため、法律上1時間以内の残業時間についての割増分の支払い義務は生じません。ただし、法定労働時間内でも1時間あたりの通常の賃金又は就業規則等で定められた賃金は支払わなければなりません。
また、1週の労働時間は40時間以内とされていますが、10人未満の事業場については一部の業種では1週44時間以内が特例措置として適用される等、例外的な取扱いもあります。 |
| 5.裁量労働について |
| 当社には、約15名の開発部があります。開発技術者以外に事務担当の社員もいますがほとんどの社員は各自の仕事の進め方を自分で決定できるので開発部全体に裁量労働制を導入したいと考えていますが可能でしょうか。 |
業務の性質上、その業務の具体的遂行方法については大幅に労働者の裁量に委ねる必要があるため、使用者の具体的な指揮監督になじまず、通常の方法による労働時間の算定が適切でない場合も多くあります。このような場合には、「その業務を通常、処理するためにはどの程度の時間を労働するとするのが適当であるかについて労使で協定をしたときは、その時間、労働したものとみなす」という制度があります。これは「裁量労働制」又は「裁量労働によるみなし労働制」と言われるもので、「専門業務型裁量労働制」と、「企画業務型裁量労働制」の2種類があります。
ご相談のケースは、専門業務型裁量労働制に該当します。
(1)専門業務型裁量労働の対象業務
1.)新製品、新技術の研究開発等の業務
2.)情報処理システムの分析又は設計の業務
3.)記事の取材又は編集の業務
4.)デザイナーの業務
5.)プロデューサー又はディレクターの業務
6.)1.)から5.)のほか、厚生労働大臣の指定する業務
主な業務は次のとおりです。
コピーライターの業務
システムコンサルタントの業務
インテリアコーディネーターの業務
ゲーム用ソフトウェアの創作の業務
証券アナリストの業務
金融工学等の知識を用いて行う金融商品の開発の業務
学校教育法に規定する大学における教授研究の業務(主として研究に従事するものに限る)
公認会計士、弁護士、建築士(一級建築士、二級建築士、木造建築士)、不動 産鑑定士、弁理士、税理士、中小企業診断士の業務
(2)専門業務型裁量労働の対象労働者
(1)の対象業務に従事する労働者です。
対象業務に従事しない事務職などは開発部に所属していても裁量労働には該当しません。
専門業務型裁量労働制を導入するためには、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合と、ないときは労働者の過半数を代表するものと、労使協定を結ぶことが必要です。なお、この労使協定は、所轄の労働基準監督署長に届け出なければなりません。 |
| 6.出張における労働時間の取扱いについて |
| 当社では、社外への出張が頻繁にありますが、このような場合労働時間はどう取り扱ったらよいのでしょうか。 |
| 出張では、労働者が事業場外で業務に従事する場合が多く、労働時間の把握が難しいものです。出張業務が, 出張先の自社事業所での指揮監督下におかれていないのであれば、「みなし労働時間」として取り扱う方法が考えられます。ちなみに、この「みなし労働時間」とは、事業場外労働として就業規則や労使協定などによってあらかじめ決められた所定労働時間を労働したものとみなすというものです。また、出張中の休日や往復に要する時間の取扱いについては、その時間中に具体的処理用務が命じられていないのであれば、労働時間としてみなさなくてもよいとされています。 |
| 7.残業命令(時間外勤務の範囲、三六協定など)について |
| 残業(時間外勤務)を命じる際には「三六協定」が必要と聞いたのですが、どういうものか教えてくだい。また、残業やそれに伴って支払われる残業手当(時間外割増賃金)についても教えてください。 |
労働時間は、原則として1日について8時間、1週間について40時間を超えて労働させてはならないこととなっていますが、労働基準法第36条では、使用者が労働時間を延長したり、休日に労働させる場合は、当該事業所の労働者の過半数で組織する労働組合または過半数を代表する者と書面による協定を結び、所轄の労働基準監督署に届け出ることが法律上義務づけられています。
この書面による協定が「三六協定」といわれるものです。
また、同法第37条において、時間外に勤務させた使用者は、労働者に2割5分以上(休日労働の場合は3割5分以上)の割増賃金を支払わなければならないとされています。 |
| 8.パートタイム労働者の社会保険について |
| 近くのスーパーでパートタイマーとして働いています。1日の勤務時間が当初より長くなったので社会保険(健康保険・厚生年金保険)に加入することになると会社に言われました。ところで、パートタイマーであっても社会保険に加入しなければならないのですか。 |
会社が社会保険の適用事業所であれば、パートタイム労働者であっても次の二つの要件を満たせば被保険者になります。
ア)1日の勤務時間が、その事業所で同種の業務を行う通常の労働者の所定労働時間のおおむね4分の3以上(ただし、1日の所定労働時間が日によって異なる場合は1週間の平均で判断する)。
イ)1ヶ月の労働日数が、その事業所で同種の業務を行う通常の労働者の所定労働日数のおおむね4分の3以上。
なお、あなたの配偶者等が既に健康保険に加入しており、その被扶養者になっている場合、あなた自身が新たに健康保険に加入すべきときは、配偶者等の被扶養者として認められなくなります。 |
|