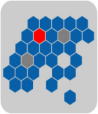仲田邦穂技術士湘南事務所のヘッダー
ナノバイオ
| 1. ナノバイオとは(知恵蔵2011からの引用) |
|---|
2011年8月9日 |
|
通常のナノテクノロジーは、小さな機械を用いて、さらに小さな機械をつくろうとするトップダウン方式で進められるが、ナノバイオテクノロジーは、原子から分子を合成し、その分子が自己集合して超分子のナノマシンができるボトムアップ方式を目指す。バイオ分子は精巧な認識能力、均質性、自己集合性などの特徴を示す。このようなナノマシンは、現在の工学技術では製造不可能であり、ナノバイオテクノロジーは新しい技術分野となる。 病気の診断や治療などの医療分野、環境汚染モニタリングなどの環境分野、電子材料分野などで研究が進められている。( 川口啓明/菊地昌子氏による) |
|
| |
| 2.特許の紹介;インフルエンザウイルス結合能を有するグリセロ糖脂質 |
|---|
2011年8月14日 |
||||||||||||||||
ウイルスレセプターはその末端にシアル酸(N-アセチルノイラミン酸およびN-グリコリルノイラミン酸)を含む特徴的な構造をもっており、さらに各宿主により異なった糖鎖で修飾されている。ヒトのレセプターは末端のシアル酸にα2→6結合でガラクトースが結合した糖鎖であるが、宿主依存性の変異によりα2→3結合を認識するヒトのウイルスも分離されることがある。ウマやブタから分離されたウイルスはN-グリコリルノイラミン酸を末端に含む糖鎖も認識するが、ヒト由来のウイルスは主にN-アセチルノイラミン酸のみを認識すると言われている。 これらのレセプターを模倣した糖鎖や糖脂質を用意すれば、ウイルスの宿主感染を阻害することが期待される。最近シアル酸を含まない糖脂質スルファチドにウイルス結合能が報告されてから、ヘマグルチニンの結合能にかなりの許容範囲が推測された。シアル酸を含まない糖脂質はウイルスのシアリダーゼに分解されず安定であり、インフルエンザ治療剤として期待される。 リンク先 http://www.patentjp.com/13/L/L100244/DA10010.html
|
||||||||||||||||
| |