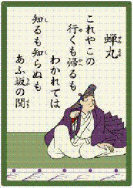仲田邦穂技術士湘南事務所のヘッダー
江の島浦々のミステリーより抜粋
| 「いろはにホイヘンス」の蝉丸の開眼より |
|---|
「これやこの 行くも帰るも 分かれては 知るも知らぬも 逢坂の関」蝉丸が百人一首に残した和歌である。この歌は、「これがあの、東国へ旅立つ人も見送って京に引き返す人も、知っている同士も知らぬ同士も、出逢いを繰り返すという逢坂の関なのだなあ」という風に口語訳されている。逢坂山に一人捨てられた彼は生きながらえ、見えない目で関所の人の出会いや別れを見つめてきた。
不思議なことにこの歌は、今日のナノバイオの世界を予感させている。生体分子の多くはナノサイズ(一ナノメートルは一ミリメートルの百万分の一)であり、ナノテクノロジー(ナノサイズの物質を自由に観察したり、自由に組み立てていく技術)で、生体組織を観察したり、生体組織を構築したりする領域をナノバイオと呼んでいる。要するに、病気の組織を分子レベルで顕微鏡検査したり、壊れた部分を分子レベルで修理したりするような領域といってもいい。
この歌に含まれる四つの反語が、最近になってやっと実現した生体分子の動態の研究手法に、みごとに合致しているのである。まず最初に、無数にある生体分子の中で目的とするものだけにマークを付けない。
と、動的環境の生体ではすぐ行方不明になる。まさに「これやこの」で標識の必要性を訴えている。具体的には、光を発する分子を観察対象に結合して光を追跡したり、放射能分子を結合して放射能で追ったり、酵素活性を有する分子を結合して酵素活性を追ったりする。車にナンバープレートを付けることで車が特定できるのと同じことである。
「行くも帰るも」では生体分子は動的であることを示している。また車で例えると、さっきまでここに駐車していたからといって、今もそこにいるとは限らない。さっきまで隣にいた車は今は全く違う場所にいるよということで、ナノバイオではビデオ撮影が活躍することになる。
「分かれては」と「逢(あう)」では、生体分子同士はくっついたり離れたりすることを表している。生体分子は結合し皮膚や目などの組織や器官を作る。生体分子は酵素反応で会合したり解離したりしている。そうした現象を顕微鏡観察するには平面的だけではだめで、三次元観察せねばならないのである。
知るも知らぬも」では、例えば分子レベルの位置のゆらぎを示している。難しくは不確定性と呼ばれ、確率的にはここにいるはずだということはわかるが、正確な一分子の位置は原理的に確定できないと説明される。分子構造もすべてが同じではないこともゆらぎと考えていい。プリウスのこの型といえば車は決まるが、実際は部品レベルのばらつきで一台ごとに少しずつ異なり、耐久性も異なっている。不確定性なものを確定することはできないのである。
これら四つの視点は、最近になってやっと科学者に理解され始めたものである。蝉丸は生まれつき見えない目でありながら、観察することの大切さ、観察する手法を知っている。彼の物を見る目の正確性を、この歌から感じとるのである。