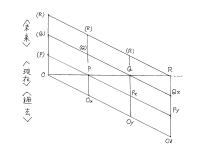| 2018年12月23日(日) |
| 人類史の悪夢 2 |
|
|
|
(1)
人類社会はある種の家畜経営であると述べたが、そのことから人類社会の階級・身分制が十分に説明できるであろう。古代ギリシャ・ローマの奴隷制では、<人間>として認められたのは自由民だけであり、奴隷は単なる家具や道具にひとしいものであった。すなわちまさに家畜であって、自由に売買された。あらゆる労働は生ける機械である奴隷がおこない、自由民は奴隷経営の根幹である国家を守るという唯一の名誉ある任務をになっただけである。ポリス間、あるいは支配地域との関係では、支配する国家は、他の国家を集団的に囲い込んだ、一段低い人間としての家畜経営をおこなったに過ぎない。いわば国家間の身分制である、大規模家畜経営としての帝国主義である。
奴隷制に関連して、女性の地位も、ある種の家畜化がおこなわれ、自由な人間としては扱われず、(今日でもある種の国や政治家の間ではそうだが)子を産むための単なる道具とみなされた。あるいは、今日までも、男性の性的快楽のうつわとして扱われてきている。インドでは夫が死ぬと、妻も殉死することが美徳とされている。娘は家同士の間での、経済的取り引きの道具として婚姻をおこなう。アウトカーストの娘たちは、暴行されても、犯罪としてはあつかわれない。すなわち、インドでは、あるいはイスラム国でも同様であろうが、たいていの女は今日でも単なる家畜である。
日本では、江戸期に士農工商エタ非人というカースト制度が確立されたが、各階級内での差別もきびしいものであった。福沢諭吉は、封建制は親の仇と言っている。明治期に、天皇以外の四民平等がうたわれたものの、エタ非人までは解放されなかった。天皇制そのものが、日本的な家畜経営の根本であり、上にも下にも<人間>でないものを設定したのである。その他の人間と言えども、殖産興業という家畜工場に駆り立てられ、国家の弾除けとして戦場に駆りだされ、赤紙一枚の軽い命を散らせたのである(もっとも、アリストテレスによれば国家のために戦死することは最高の美徳である。家畜冥利につきるというべきか)。
今日謳歌される民主主義や自由主義はどうであろうか。そもそも政治制度以前に、人類社会の根幹である物質的生産、及びそれにもとづくあらゆる経済活動の本質を見極めねばならない。農業も家畜経営も、生命の原理としての種の持続、個体の保存の絶対の必要性から生まれている。一般に経済活動が、生命としての人類の根本の運動なのである。そのもっとも効率的なありかた、生産事情、生産様式が、ここで言う家畜経営としての人類社会なのである。社会主義、資本主義が、ある種の進歩的な社会であるとするならば、それらは最も家畜経営として成功した人類社会であるといえるだろう。民主主義や自由主義は、単なる家畜経営のためのモットーであり、手段であるに過ぎないのである。それには人類という、この特殊な家畜の考察が必要である。
(2)
動物はどのようにして人類の家畜となったのであろうか。必ずしも、ヒトが強要して動物を従わせたのではないであろう。犬の祖先である狼は、ヒトの住まいの近辺でその残飯に預かることを覚えたのであろう。人の生活の中に取り込まれることによって、より安全、確実な生活の手段を見出したのである。この異種間の共生・共同ということは、生命体一般に見られることであり、最初の家畜も、このような取り込みによって成り立ったであろう。これは異種同士の間での、いわば暗黙の、無意識の生存の取り決めであり、個体保存よりもむしろ種の持続に大いにあずかる、生命の狡知なのである。
羊や豚や鶏や牛は、たしかに毎日何百万頭、何百万羽と屠殺されているが、その数を補ってあまりあるほどの種としての繁栄を遂げているのである。個は無であって、類がすべてである。これが生命界の掟であり、根本の原理である。家畜としてもっとうまくやっているのは、犬や猫などのいわゆるペットであり、種も個もともに保存ができて、大繁栄しているのである。人間はどうか。
奴隷制では通常婚姻は認められなかった。普通の家畜のように繁殖させる必要はなく、いくらでも戦争や略奪によって、奴隷の補給ができたからである。カースト制では、カースト間の婚姻は認められず、同じ身分同士の婚姻が許された。身分間の数のバランスということが考慮されたのであろう。それを血の潔癖によて保障したのである。家畜経営においては、最終的に食糧として処理するまえに、家畜を成育させ、養わねばならない。それには環境条件などによって数に制限がある。同じことは人類社会の人口についても言えるであろう。人口をおさえつつ、家畜経営をすることが求められるのである。個々人ではなく、種としての社会全体が存続するような家畜間のバランスが必要なのである。
このような人類社会の家畜経営は、単なる動物の家畜経営とは違って、独特の様相を見せることになる。まず、ヒトを食糧とすることが目的ではなく、食糧生産を中心とした<労働力>としての家畜の飼育、いわば役畜としてのヒトの飼育を目的とするのであるから、種だけではなく個の保存もまた考慮しなければならない。それだけやっかいであり、むやみに数を増やすわけにはいかない。かつておこなわれた嬰児殺し、間引き、姥捨てなどが、その本能的処置である。また、人類社会の需要の多様化による階層・身分の分化が役畜としてのヒトの間で生じる。士農工商が典型的である。
さらに、人間は根本においてその心身において同等であり、家畜化以前には、そのような<原始共同体>に生きていたのであるから、家畜としての扱いにおいてはつねに<反抗>の惧れがあるのである。それに対する政治的その他の対処・予防がつねに必要となる。そのひとつは言うまでもなく力の誇示、すなわち軍事力である。家畜社会における支配者はつねに軍事を握っていなければならない。古代ギリシャ・ローマでは、軍務につけたのは自由民だけであり、彼らがポリスや帝国を支配したのである。日本でも、中世以来、支配者はつねに<軍事政権>であった。カースト制では実質の支配者は王侯武士(クシャトリア)であった。中世ヨーロッパは、王侯貴族の軍事同盟であった。中国では、軍を握るものが帝位に就き、官僚制による専制国家を築いた。明治以降の日本は、統帥権を持つ天皇のもとでの軍事・警察国家であった。
もうひとつの、家畜としてのヒトの反抗に備えるいわば精神装置は、宗教及びそこから派生した道徳や倫理であった。宗教ほど家畜としての人間の心理を端的に表わすものはない。権力や暴力にひれ伏すのは単なる肉体的惧れであるが、宗教的畏怖はヒトの心を支配するのである。動物特にペットは人間の心に取り入るすべを心得ている。人間のペットであることにどっぷりと満足しているのである。同じ心理を、人間もまた宗教的、精神的権威に対して抱くのである。そのたとえとして、羊の従順さや、家畜の境遇がひかれる。キリスト者は羊飼いである神の羊なのである。ヒトの心の宗教的支配は、政治権力と結びつく。軍事だけではなく、神の崇拝、あるいは自ら神となることによって、家畜としてのヒトの群を支配することは、最も初期の国家のあり方であり、また今日でも天皇制や王制のような<伝統>となって家畜社会を支えている。
(3)
先に述べたように、生命体には共生・共存の本性がある。そうならば生命体の家畜化もまた、生命によって本来仕組まれているものではないか、と考えられうる。ヒトもまた本来家畜化の素質を持っているのである。その根源は、これまでにも考察したように、生への意志の類的本質にあるといえよう。同種ばかりでなく、異種との共生・共存が類の繁栄に役立つならば、それは生への意志の本流であるといえよう。人類が進んで、みずから人類社会という類的本質の現れである集団の中に、家畜として適応しようとするのは、まさに人類そのものの生命的本質の現われなのであると言えよう。であるから、実は家畜であることの快適さの中に、たいていの人間は、犬や猫と同様に、どっぷりとひたっているのである。人類社会の階層性、階級や身分、その他の格差が決してなくなることがないのは、人類が知らずして、あるいは無意識に、家畜であることに満足しているからである。権力の脅しや、法律や、宗教や道徳の戒めも、犬や猫が悪さをしてたしなめられるのと同様な、調教のためのちょっとした不快に過ぎないのである。
このような生命体としての人類、すなわち<人間>の類的本質を見るならば、人類の家畜化は起こるべくして起こったことであり、これがそもそもの人類の<文明>の意味なのである。文明とは人類の家畜化の謂いである。人類史はヒトの家畜化の歴史なのであり、すなわち単なるヒトが<人間>となる発展の過程なのである。かつて、唯物史観というものが流行り、原始共同体から、奴隷制、封建制、資本制(資本の家畜)と、家畜化の歴史をたどり、最後に総体的労働家畜としての共産制にたどりつくものとした。いみじき家畜史である。この家畜としての人間の基本的な道徳は、主人(社会体制、法の調教)への服従であり、さらには愛(同胞愛、家族愛、民族愛、神への愛)であり、すなわち類的存在への全面的依存である。このことを、以前に<全体への意志>すなわち類的意志の観点から考察したが、基本的にはまったく同じことを意味している。個としての存在の、全体すなわち類に対する内的・外的依存、服従の衝動・心理が、その根底にある。それを形而上学的に見れば<全体への意志>であり、経験的・歴史的に見れば、家畜化という現象として現われるのである。
国家は家畜経営の形態である。何らかの形での支配者、すなわち経営者もしくは管理者のいない国家はない。牛馬のような家畜は、烙印を押されて数が管理されるが、人間の場合にはもっと徹底した管理が、官僚制によってなされる。江戸時代には各村に徹底した戸籍(人別帳)が作られて、農業生産物の徴収を石高によっておこなった。今日ではそれを納税番号がおこなっている。各個人の<義務>としての労働の成果から、家畜経営の運営費としての税を取り立てるのである。確かに義務という言葉ほど、家畜にふさわしい道徳的用語はないのである。一般に動物は家畜として、人間に食われるために生きる<義務>などはないのであるが、人間だけは、単なる強制や暴力によっては、家畜化できない場合に、心理的な説得や洗脳によって、進んで家畜となる意欲を起こさせうるのである。これが民主主義や自由主義の時代における、家畜化の手段である。個人が互いに同等の立場において、自由に競い合い、かつ社会体制や制度を維持してゆく、この一見いかなる強制もないかに見える国家や社会においても、家畜制度は厳として個人を縛っており、あたえられた制度や組織の外で生きてゆくことは不可能に近いのである。法律や契約は、まさに家畜としての服従を強要するのであり、それに逆らえば、刑罰という調教を食らい、よくても社会から追放されるのである。人間は家畜となる<義務>があるのである。それを拒否するかどうかは<自己責任>である。それに逆らうものが<非国民>である。すなわち国民という家畜の資格を奪われるのである。
すべての家畜が家畜として平等であるというのが、現代の民主主義・自由主義の原則であるが(これは家畜の価値が同等である場合は、他の動物でも同様であるが)、人類社会で必ずしもそういかないのには理由がある。ひとつには、家畜経営の形態の異なる社会が並存するからであり、いまひとつには、国家は経営であるからには、互いに競い、争い、征服しあうからである。身分制のある社会(インドなど)、階級制のある社会、資本制や、共産主義(アパラチキの支配)や、独裁制の国、政教一致の国家(イスラム諸国)など、国家形態の違いが、異なった家畜経営のもとに、国際経済や覇権を争わせる。食肉が国際化するようには、人類の国際的家畜化は、スムーズには進まない。かつての奴隷貿易をまねるわけにはいかない。この矛盾が高じると、国際的家畜経営をめぐっての紛争や、帝国主義戦争が起こるのである。
(4)
遊牧民が農耕民を家畜化した当初には、支配者は家畜民を飼育し、役立てることを考えるだけでよかった。しかし家畜経営が制度化し、固定化すると、その中に取り入れることのできない群が存在するようになった。相変わらず遊牧をつづける民や、放浪民である。遊牧民が、すでに出来上がっている<遊牧国家>を征服する時には、<王朝交代>が生じる。遊牧民の作った国家は、農業に特化することによって、遊牧民の新たな侵略を受けねばならなくなったのである。これは農業民どうしの局地的な戦争を、全世界に拡大するものであった。<帝国>の誕生である。帝国はまた、つねに新たな遊牧民の侵略に備えねばならないのである。国家がつねに他国に対して防衛的であり、時に侵略的になるのは、この国家の起源における征服・非征服の事情が、いわば本能として遺伝しているからである。
国家の<敵>は国外ばかりでなく、国内にも向けられる。ドイツにおいて忠実な家畜であったユダヤ人は、経済的格差という目に見えない身分制の下で、他の家畜民の嫉妬と憎悪を受けるようになった。民族主義・国粋主義は家畜民の一致団結を図るための心理的道具である。この家畜間の争い・内紛は徹底した殲滅への憎悪となる。家畜としての身分制の下では、家畜同士が分断され、互いに憎み合う状況が生まれる。それぞれが類的・集団的本能によって、集団の利益を最優先するようになる。これは国家的家畜経営を危殆におとしいれる。スケープゴートとしての家畜の群が必要となるのである。こうした家畜の大量処分が、ナチスによるユダヤ人虐殺であった。しかも家畜経営の合理性から、ドイツ人は単に殺戮しただけではなく、死体の製品化を考えたのである(死体から石鹸を作るなど)。
あらゆる民族紛争は似たような事情にある。最終的に国家経営が分離するか、<敵>の殲滅以外にないのである。歴史的身分制においても、つねに最下層の家畜民が、社会の紛争のスケープゴートとされた。日本ではエタ非人がそれであり、皮革業という支配層にとっては必要な産業をになってはいても、農工商の家畜制を確固とするために、彼らの憎悪や差別の的とさせたのである。今日の民族差別、ヘイト・スピーチにおいても、家畜民の不満が、特定の民族や階層に向けられる憎悪となることによって、家畜社会のバランスが保たれていると言えよう。家畜は家畜であることによって、その憤懣を他の家畜に向けるほかはないのである。決して主人に逆らってはならない。主人とは類的本能であり、その現われである国家や、天皇や、民族や、宗教や、神やの、あるいはさらに小さいレベルでは、親や、上司や、経営者や、会社やの、<目上のもの>であり、それらへの服従は絶対である。<汝の主人の命じるところをなせ>―これが家畜民のカテゴリカル・インペラティヴ(範疇命令)である。 |
|
|
| 2018年12月17日(月) |
| アートマンについて |
|
|
|
ウパニシャッドで説かれるアートマンとはなんであるか。さまざまなウパニシャッドの中で説かれるアートマンは実に漠然としていて、ましてやそれがブラフマンと同一である(梵我一如)などどいわれても、同語反復に過ぎないような印象を受ける。この古代人の思想においては、いまだ概念のはっきりとした区別がなく、今日単純に自我として明白にとらえられるものと、混沌としたアートマンとを同一視するわけにはいかない。
「1.ブラフマンは実にこのすべてである。寂静となった者はそれを『わたくしが知るべきもの』として念想すべきである。つぎに、人間は実に意向よりなる。人間はこの世界において意向のままになるように、この世界を去ってからそのようになる。かれは(そのために次のように)意向を作るべきである。
2. 思考作用よりなり、気息を身体とし、光を姿とし、真実をその思索とし、虚空をアートマンとし、すべてのものをその行為とし、すべてをその欲望とし、すべてをその香りとし、すべてをその味とし、このすべてを包含し、言葉をもたず、関心なきもの。
3.これは、心臓の内部にあるわたくしのアートマンである。それは米粒よりも、大麦の粒よりも、からしの粒よりも、きびの粒よりも、あるいはきび粒の核よりもいっそう小さい。これは心臓の内部にあるわたくしのアートマンである。それは地よりもいっそう大きく、虚空よりもいっそう大きく、天よりもいっそう大きく、もろもろの世界よりも大きい。
4.すべてのものをその行為とし、すべてをその欲望とし、すべてをその香りとし、すべてをその味とし、このすべてを包含し、ことばをもたず、関心なきもの、これは、わたくしの心臓の内部にあるアートマンである。これはブラフマンである。この世界を去ってから、わたくしはこれに到達するであろう。このように考える者には、疑念はまさにありえないと、シャーンディリヤはかたった。シャーンディリヤは語った。」
――「チャーンドーギャ・ウパニシャッド」第三編・第11章・第1−4節(「ウパニシャッドの哲人」松濤誠達著より)
古代のインド・アーリアンの思想家にとって、今日われわれが頭脳と言うべき部分を、心臓においているのであろう。心臓が考えたり、知覚したり、意欲したりする働きの中心なのである。そしてこれらの働きは明白に区別されることはなく、すべてがアートマンとして一括されるのである。そのアートマンは同時に、この宇宙の見えざる根源的存在であるブラフマンと死後において、あるいは観想において同一であることが認識され、あるいは同一物として一体化するのである。これはショーペンハウアーの世界意志の学説と類似した点がある。アートマン=ブラフマンは認識においてとらえられることがない。どんな粒よりも小さく、天地よりも大きい。要するに人間の知覚や思考の及ぶところではない、叡知的・超越的存在なのである。それが万物ばかりか、人間自身をもつらぬいている。
「1.つぎに、ウシャスタ・チャークラーヤナがかれ(ヤージュナヴァルキャ)に質問した。
『ヤージュナヴァルキャよ』とかれは言った。
『目の前に、まぎれもなく存在しているブラフマンなるもの、〔すなわち〕すべてのもののうちに内在するアートマンなるもの、それをわたくしに説明してほしい』
〔ヤージュナヴァルキャは答えた。〕『あなたのこのアートマンがすべてのもののうちに内在しているのである。』
『ヤージュナヴァルキャよ、すべてのもののうちに内在するものとは、いったいどのようなものなのだろうか』〔とチャークラーヤナがたずねた。〕
〔ヤージュナヴァルキャが答えた。〕『プラーナ(気息の一つで、吸気)によって息づくもの、それがすべてのもののうちに内在するあなたのアートマンである。アパーナ(気息の一つで、呼気)によって息づくもの、それがすべてのもののうちに内在するあなたのアートマンである。ヴィヤーナ(気息の一つ)によって息づくもの、それがすべてのもののうちに内在するあなたのアートマンである。ウダーナ(気息の一つ)によって息づくもの、それがすべてのもののうちに内在するあなたのアートマンである。サマーナ(気息の一つ)によって息づくもの、それがすべてのもののうちに内在するあなたのアートマンである。』
かのウシャスタ・チャークラーヤナが言った。
『〈そこに牛がいる〉、〈そこに馬がいる〉と人が言うのとまったく同様にそのことが説明された。(まるで実物を見るように明確に説明された)。ほかならぬ目の前に、まぎれもなく存在しているブラフマンなるもの、〔すなわち〕すべてのもののうちに内在するアートマンなるもの、それをわたくしに説明してほしい』
〔ヤージュナヴァルキャは答えた。〕『あなたのこのアートマンがすべてのもののうちに内在しているのである。』
〔チャークラーヤナがたずねた。〕『ヤージュナヴァルキャよ、すべてのもののうちに内在するものとは、いったいどのようなものだろうか』
〔ヤージュナヴァルキャは答えた。〕『あなたは視覚作用の視る主体を目に見ることはできないであろう。あなたは聴覚作用の聴く主体を耳に聞くことはできないであろう。あなたは思考作用の思考の主体を考えることはできないであろう。あなたは認識作用の認識の主体を認識することはできないであろう。それが(視覚作用、聴覚作用、思考作用、認識作用の主体)すべてのもののうちに内在するあなたのアートマンである。これ以外のものは〔苦悩に〕さいなまれているのである。』
そこでウシャスタ・チャークラーヤナは質問をやめた。」
――「ブリハッド・アーラニヤカ・ウパニシャッド」第三編第5章(前掲書より)
視覚・聴覚・思考・認識などの見えざる主体の中にアートマンがあるという洞察は、近代の認識論に通じるものがある。いわゆる超越論的主観である。これはもはや意識のレベルでの話ではないのである。したがってわれわれの経験的自我とは異なったものである。しかし、アートマンを気息としてとらえている点に、古代的思考の即物性が表われていよう。気息は五種類に分かれて、全体としては得体の知れないものであるが、これをアリストテレスの霊魂論に比較することが出来るであろう。
アリストテレスによれば、霊魂(psyche,anima)は、植物的と、動物的と、人間的との三種の段階がある。人間霊魂の中にはこの三つの段階が存在している。
「生魂(プシュケー)を持つものの中の或るもの、すなわち生物の或るものは、栄養能力、感覚能力、欲求能力、場所的運動能力、思考能力の全部をもっているが、或るものはその中の幾つか、また或るものはその中の一つしか持たないというものもある。」(「霊魂論」414a29-32。「アリストテレス」今道友信著より)
プシュケーは生命体と結びついており、この引用では生魂と訳されている。植物の霊魂は、栄養と感覚の能力に限られるであろう。動物ではそれ以外に、欲求や場所的運動能力、さらには思考能力が加わるであろう。この思考能力を理性を頂点として高度のレベルで持つのが人間の霊魂である。この総体としての霊魂は、身体とは異なったものであり、「瞳と視力とで眼であるように、プシュケーと身体とで生物である」(霊魂論413a2-3)。
「『プシュケーとは、可能的に生命(zoe)を持つ自然的物体の第一の完全現実態(entelecheia)である。』(霊魂論412a27-28) この場合に生命とあるのは、括弧内にも示したように、ギリシャ語ではゾーエー(zoe)と言い、アリストテレスの説明によると、それは『それ自らによる栄養摂取、成長、衰弱のことである』(412a14-15)。それは・・・自らの生成変化を、自らの内部からの力で類種的規定性に於いて展開してゆくことという意味なのである。このような生命を有する物体はプシュケーではないと言われるのは、プシュケーがこの生命を持つ物体の実体として一応その肉体とは別個のものと考えられているからである。このようにして生物体を質料、霊魂的生命を形相とみているのがアリストテレスの特色ということができる。」(前掲書p.239)
もちろんウパニシャッドには、形相(イデア、エイドス)、質料(ヒューレ)という考え方はない。しかし知性や理性を一方ではアートマンという総称の中に、他方ではプシュケーという生命と結びついた実体の中に、包括する点においては、古代的思考の類似性をみることができよう。インド・アーリアンにおいては、さらに無機的自然と、有機的自然との区別もないようである。アートマンは、人体や生命の中ばかりでなく、風や、火や、虚空や、天体や、とりわけ太陽の中に内在するとされる。それらはまた、身体以外の自然界から出発した場合の、神的存在であるブラフマンでもある。これは原始信仰における、マナの観念に近いものであろう。あるいはその発展と見ることができよう。万物に神霊が宿り、人間自身の心身もそれに連なっている。ウパニシャッドは、その点では、アニミズムやアニマティズムからそれほど離れてはいないのかもしれない。
ウパニシャッドはさらに、四種のヴェーダに付属することから、祭儀的要素や、神話的物語性、呪術的要素が渾然となったものであり、純粋な精神性と現世利益とがともに見られる。このような背景の下では、自我を純粋に探究するというレベルの思想は見られない。そもそもアートマン自体を、その最も広い意味で<自我>とすべきなのであるか。アートマンを身体的自我と、宇宙的自我と、二重に使っている(アートマンのアートマン)テキストも見受けられる。
「30.自己(アートマン)の中に存続しつつ自己とは別のものであり、自己がそれを知ることなく、自己がそのものの肉体であり、内部にあって自己を統制するもの、それがあなたの内部の統制者であり、不死なる、アートマンである。
29.精液の中に存続しつつ精液とは別のものであり、精液がそれを知ることなく、精液がそのものの肉体であり、内部にあって精液を統制するもの、それがあなたの内部の統制者であり、不死なる、アートマンである。
13.月と星の中に存続しつつ月と星とは別のものであり、月と星がそれを知ることなく、月と星がそのものの肉体であり、内部にあって月と星を統制するもの、それがあなたの内部の統制者であり、不死なる、アートマンである。」
――――「ブリハッド・アーラニヤカ・ウパニシャッド」第三編第7章(前掲書より)
このように使われるアートマンは、むしろ近代人の考える自我よりも、アリストテレスのプシュケーに近いのではないか。ただアリストテレスとは違って、全宇宙に生命を満ちわたらせた、古代的なVitalismus(汎生命論)なのであるが。これはデミウルゴスが創造した世界を、ひとつの有機体と見る、プラトンの宇宙論とも類似していよう。しかしインド・アーリアンでは、世界原理ブラフマンは不可知、不可視の存在であり、それが全宇宙をつらぬく点においてアートマンなのである。個体の本質が全宇宙の本質と全面的に一致する、これが梵我一如なのであり、インド・アーリアンの楽天観が率直にあらわしだされたものといえよう。ちなみにインド的肉体観にもとづいたこの宇宙原理としてのアートマンを否定した、釈迦のアンチテーゼとしての教説は、実に大胆な試みであったと言えよう。仏教がインドから脱出したのも、バラモン、クシャトリアと言う支配層の生みだした、このヴェーダ=ウパニシャッドの強固な楽天的思想に打ち勝てなかったからであろう。 |
|
|
| 2018年12月11日(火) |
| 不可知の真理とWerden |
|
|
|
どのような学術であれ、人間知性に限界がある限りは、その見いだした真理が絶対である保証はない。少なくともポジティヴに主張しうる真理には、人間知性にとってという限定がつくのである。これは形而上学においても同様である。世界意志がなんであるか、それがどのような本質を持つものであるか、それが単に理知にとって考えられうるという相対的な真理性しか持たないものである限り、不可知であると言うほかはない。基本的には世界意志の存在は、人間知性もしくは理性の限界から来る、単なるもっともらしい要請(Postulat)に過ぎないのである。
イデア界についてはどうか。今日のもっとも有力なイデア論である自然科学を例にとると、自然法則がこの宇宙の絶対的真理であるという保証はどこにもないのであり、単なる普遍妥当性の要請に過ぎないのである。宇宙のほかの場所で、それが成り立っていないという可能性は否定できないのである(*注)。人間の認識が探究したこの現象界の法則が、イデア界の法則そのものである保証は、どこにもないのである。そうとするならば、プラトンはこの直観的世界をイデアの影であるとしたが、理知が客観的にとらえた概念的世界もまたイデアの影に過ぎないのであるから、人間の認識は、さらには知識そのものが、影や影の影を相手にしていることになる。イデアそのもの、イデアの本体が何であるかは、人間知性にとっては不可知の領域にあるのである。それが人間的理知に適合するものである保証は、どこにもないのである。
(*たとえば宇宙の平坦性問題という謎がある。この宇宙空間が平坦一様である理由として、我々の知る宇宙が極端に小さな領域に限られているからであるという解決がなされている。大地が平面に見えるのと同様であり、この宇宙全体はでこぼこした空間でありうるのである。)
それでは、人間の認識が相手にしているこの世界、このWerden(ヴェルデン)の世界は、この生成消滅の世界は、一体どのような本質を持っているのか。それは現象である限りは、世界意志とは本質を異にしており、すなわち物自体である世界意志とは、次元をことにした存在のありようであり、またイデア界の影や影の影である以上は、イデアの本質とは異なった存在のありようである。そもそもWerdenは単なる存在ではなく、存在から存在への変化なのである。この存在のあり方は、本質に対して偶有性と呼ばれる存在のあり方であり、本質が不変であるのに対して、変化と消滅にさらされている存在のあり方である。本質もしくは実体は不変であり、それの偶有的性質は変化し、生成し、消滅する。これがWerdenの本質である。すなわち生成消滅を不変の本質とするものが、Werdenなのであり、この現象界のあり方である。
この現象界の認識は、カントが先験的認識論において確立したように、人間知性にとってもっとも確実な知識のありようである。人間の知識は基本的に現象界に限られるといってよい。それは物自体にも、イデア界にも直接及ぶことはないのである。Werdenが人間にとってもっとも確実な知識の対象であることは、そもそも人間自体がこのWerdenの世界に(ショーペンハウアーの用語を用いれば)投げ出されたgeworfen存在であるからだ。右も左もわからずにこの世に生み出される幼い生命体の、闇雲の行為を導く認識は、この現象界にいかに適応するかを唯一の原理として形成された、先天的形式によるものいがいにはないのである。人間の基本的認識はそれ以上でも、それ以下でもない。自然科学も、またあらゆる学問も、それ以上には出でないのである。
自我もまた、身体的現象としておのれを見いだし、身体として生きていく限りにおいて、現象的存在(いわゆるDasein)のありようを免れることはない。すなわち生命的人間としての存在を、自己の存在とする以上は、このWerdenのなかに身をおき、生成し、消滅する存在として、自己を認識するほかはないのである。その限りにおいて、自我は自己自身について、現象的知識を得るに過ぎない。そのことは、この宇宙や物質に関して得る知識と、なんら本質的に違ったものではない。そこには何ひとつ不可知なものはない。カントが言うように、現象そのものに、おのれ自身の法則を与えるようなものだからである。
それならば、自我もまた現象そのものとして、なんらの本質を持たずに、存在から非在へと移り行くだけのものなのであるか。ここに自我の特異な性質が注目されるべきである。
世界意志も、イデア界も、その本質においては不可知であり、なんら直接的認識が与えられていないのに対して、自我は自我であることによって、ある種の直知がそこに与えられていることである。そもそも現象界が成立するためには、カントの言う先験的統覚の条件である、<私の意識>があらゆる対象にともなっていなければならない。この自己意識は、それが明瞭に自覚されるとき、独特の存在の意識となって、私自身を私の内面へと向かわせる。私の存在を私は疑うことが出来ない。それが現象的にいかにひよわで、不安に満ち、また、さまざまな欲望に動かされるものであろうとも。この身体的Daseinを直知することが、私の自己意識なのである。この自己意識は、どこまでも私の内面へと自己を探究していくことが出来る。しかし私が私をとらえる限りでは、私は私の身体をとらえているのであるが、ある平面でふと私の存在の不可解性が目覚める。私が私の本質をつかもうとすると、もはやそこには私の理知が及ばないのである。私は私自身にとって不可解な存在、すなわち不可知者として現れる。直知によってこれほどよく知られている私が、究極において不可知であるということ、これはどのようなことなのか。もはや私の本質が現象界に属していないことの表われではないのか。以前に、私すなわち純粋自我の本質は、意欲でも、思考でも、意識ですらもないだろうと述べたが、思考によってはとらえられず、意識そのものも、それが現象の認識の条件であるかぎりは、私の存在そのものの本質にまでは及ばないのである。私もまた不可知の存在者(the Unknowable)なのである。
世界意志とイデア界と、そして純粋自我としての私の存在も、それぞれに不可知である。この宇宙の本質には、三体の不可知の存在、スペンサーの用語でいえば、the
Unknowable(不可知者)が存在する。この三者が、この現象界に、統一して発現している姿こそが、Werden
にほかならない。自我は、以前に述べたように、この空漠とした無限の宇宙において、唯一の実在的点をなしている。もし宇宙に中心というものがあるならば、この実在的点としての自我のほかにはないのである。あらゆるWerdenは、この実在的点を中心にして展開されるのである。その原理は時間であることもすでに明らかにした。自我は時間のイデアによって、世界意志の本質の発現であるWerdenを現象させる。それによって不可知なもの(the
Unknowable)を知りうるもの(the Knowable)とする。この現象としての世界創造に参与することによって、自我は何を得るのであるか。少なくともなにかを得るからには、自己自身においてはないものでなければならない。たとえ自己自身に自足することが、自我にとっては最高の存在のあり方であったとしても、そこから揺り動かされるには、なんらかの欠乏がなければならない。その意味では自我は絶対者ではない。同様にして、世界意志も、それが世界創造への渇望であるかぎりは、絶対的に自足した存在ではない。イデア界も、それ自身にとどまることが出来ないならば、なんらかの要因によって、現象界にその影を映す必要に駆られているであろう。この三者の条件が、何らかの形で一致した現われが、この現象界、すなわちこの生成消滅、万物流転の世界であると言えよう。
自我はおのれに欠けているものを、世界意志、およびイデア界に見いだしていると言えよう。一つには生成の喜びなのであり、一つには自己認識の欲求である。これらはともに世界意志から出でて、イデアによってなしとげられることである。この世界がいかに苦痛に満ちた、地獄の相を見せようと、ライプニッツが言うように、あらゆる不協和音にもかかわらず、むしろその故に、全体としては調和した壮大な交響曲をなしているのである。このイデアと世界意志との壮大な音楽である、Werdenの波うつままに、その流れに乗って存在を謳歌することが、自我にとってのこの世界でのつかのまの存在の意味なのである。それは、もはや生への意志の肯定と否定という二者択一を超えた、この現象界を永遠の見地から見る超越的観点である。そして、このWerdenとの遊戯に遊び疲れたならば、自我には帰るべきおのれの世界があるのである。それはみずから見いだすことも出来るし、死という最終の秘儀を待ってもよい。 |
|
|
| 2018年12月9日(日) |
| 人類史の悪夢1 |
|
|
|
個人の人生において、その幸不幸が、単に人格の内面の統御によって決まるばかりでなく、身近な環境や境遇や、ひいては国や民族や世界やの、すなわち人類全体のあり方に強く影響されることは、個の人生の悪夢の付随的要素としてふれておいた。ここでは、その見地から、人類の歴史的運命について考察する。
人類史を単に生命の歴史の中での孤立した現象としてあつかうことは可能であり、普通の歴史書はそのように書かれる。人類史はたかだか数百万年の歴史として描かれるのであり、さらにはもっぱら文明の歴史としてだけとらえるならば、せいぜい数万年の歴史である。しかし人類の本質を探究するには、それでは不充分であり、せめて生命の歴史の中でそれを考察することによって、人類の性格やその歴史的運命も見えてくるのである。生命現象は、この地球という、この銀河系でわずかな数の生命の発生する条件を備えた、天文学的に恵まれた環境にある惑星において、さまざまな偶然的要素をクリアーして発生した、特殊な現象なのである。すでに40億年前の冥王代に、生命は太陽(または地熱)と大気と水と地殻(岩石)の交互作用によって、有機体として発生したと考えられている。その後数十億年の雌伏をへて、五億年前のカンブリア紀に生命進化の大爆発が起こったのであった。その進化の根底にあるのが、細胞という個としての組織と、それを複製的に存続させるDNAやRNAという遺伝のメカニズムであった。これによって個体保存、種の維持という生命現象およびその進化の基本原理が完成したのである。
生命体はしかし、その異化作用、すなわち物質循環によってその存在を維持しているのであるが、原初の生命発生においてはいざしらず、しだいに異種の生命体同士の間でそれを行なうようになり、そこに生存競争が発生した。直接無機物から栄養を摂取するよりも、他の有機体からそれを行うことが、個体保存にも種の持続にも有利であることが、その原因である。それによって進化はさらに加速されたのである。強者が生き残り、弱者が滅びる。別の言葉でいえば、生存環境によく適応できたものが、そうでないものを犠牲にして生き延びたのである。これが原始生命から、生命の頂点にある存在に至るまでの、全生命界を貫徹する、進化すなわち種のより効果的な存続の根本原理である。
このようにして見られた生命界は、宇宙意識にまで達した知的生命体の、生命現象に対する価値判断においては、あたかも地獄のように映るであろう。生命現象の頂点に達した知的生命体にとっては、そのもっともはなはだしい地獄が、ほかならないその知的生命体自身の歴史において現われるのである。生命が知的に進化を遂げたこと自体が、まさにこの生命の根本原理に基づいているからである。
ネアンデルタール人はホモサピエンスよりも大きな脳を持っていたとされる。どちらも知的生命体であったが、前者は肉体にすぐれ、後者は肉体において劣ったぶん、集団的に狩をしたとされる。その集団生活によって言語が発達し、情報の伝達によって環境への適応を有利にし、それのできなかった家族単位のネアンデルタールとの生存競争に打ち勝ったのであるとされる。知性の進化が、他のライバルの種を滅ぼすことになるのである。(もっとも両種の間にはある程度の混血が行なわれたようで、それが遺伝子解析によって明らかにされている。)
人類の知性は、種としての進化の大きな要因となったが、その根本には生存競争に打ち勝つための有利な道具を発達させる生命の必要が働いている。知性という道具は動物界のいたるところで見られるが、それをいち早く開発した人類が、生命界を支配する頂点に立ったのである。人類で唯一生き残った種としてのホモ・サピエンスは、その集団性と道具的知性によって、狩猟の技術や言語を発達させたのであるが、次に大きな人類史の画期的出来事は、家畜の飼育であった。他の種の動物を集団の中に生きたまま食糧として取り込むこと、これは昆虫の社会では見られるが、哺乳類においては知性がなければ出来ないことである。人類以外の動物を家畜として集団の中で飼育し、それを食糧の外、さまざまな用途において使用すること、この着想がその後の人類社会に決定的な影響を及ぼすのである。
家畜を集団の中に取り込み、管理することは、すぐさま人間社会そのものに応用が可能であることがひらめいたであろう。いま一方で、植物を栽培し管理する、農耕社会が生まれてきた。知性の用い方としては類似しているが、家畜とは違って、植物は土地と結びついている。植物栽培は土地を離れることが出来ないのである。ここで二種類の人類社会が生まれたのである。一方は家畜飼育の、他方は植物栽培の社会である。人間自体は動物であるから、人間を支配するには、家畜を支配している集団が、より適していることは明白である。遊牧民の農耕民支配の歴史がそこに始まる。農耕民自体は、土地の奪い合いによって戦争を繰り返したが、得るものは土地であり、被支配民はそう必要ではなかったであろう。今日でも、農耕民同士の争いは、一方による他方の殲滅である。これにより漁夫の利を得るのは、もちろん遊牧民である。文明は、すなわち都市国家の成立は、遊牧民による農耕民の支配、いわば家畜化によって、始まったのである。道具的知性による家畜の飼育が、国家の淵源であり、その人類集団への適用が起源である。この家畜としての人類のありかたが、その後の人類の全歴史を特徴づけている。
家畜飼育の合理性は、国家の支配体制の基本プランとなる。飼育するものと飼育されるもの、この支配関係がまずあり、飼育するものの飼育されるものに対する管理の基本として、集団化、さらには役割に応じての階層化が図られる。飼育される家畜に種類があるように、支配されるもの、またはその集団には、それぞれ役割が与えられる。これが身分制もしくは階級制の起源である。身分制や階級制は、それぞれの社会の主要な生産事情によって、異なった制度が生まれる。ギリシャ・ローマでは奴隷制が、インドでは四種のカーストと賎民の制度が、中国では官僚制にもとづく専政制度が(日本はこの模倣である)、エジプトやアンデスでは祭司王による支配が、中世ヨーロッパやロシアでは農奴制が、家畜としての民を飼育したのである。家畜に食糧としての家畜と役畜があるように、人間の場合は食糧を生産する階級と、商業・工業に使役されるもの、軍役につくもの、官吏といった、国家を維持するための職能の分化に応じた組織化が必要であった。この大規模な家畜経営が、人類社会であり、国家なのである。
(つづく) |
|
|
| 2018年12月1日(土) |
| 総体人格について(2) |
|
|
|
総体人格と性格
総体人格の形成がエゴイストの基本的な自己に対する倫理であると述べたが、これから帰結する行為のあり方を、具体的に人生の原則として立てることが出来る。この世界に身体を持った存在者として生み出されたことが、自我の最初の悲劇であるが、その存在のありようを、最小限の苦悩と苦痛で済ませようという、流刑者の心掛けが、いわば自我の処世訓であり、心術である。このことに気づくまでには、多くの悲惨な体験をへて、純粋自我の自覚に達するのであるが、ひとたびこの自覚に達したならば、まず自己の混乱した人格を立て直すことが、何よりも肝要である。無知蒙昧な青春期にはこのことは不可能であり、放蕩無頼な社会人生活においてはなおさら不可能である。人生の半ばを越して、初めて到達しえる自覚なのである。
人格を考えるには、行為の源にある性格 Charakter というものを考察しておかねばならない。人格は行為において初めて認識されうるものであり、その行為を生みだす源が性格と称される、身体的自我の、すなわち人間の、根源の属性ないし性質である。この性格は生得的であり、変えることができない。科学的に言えば、遺伝子すなわちDNAによって決定されており、すなわち祖先の性質をそのまま受け継いでいるのである。人格の多元性の理由の一つは、この遺伝子が両親という二方面から受け継がれることによる、性質の乖離がある。ショーペンハウアーが言うように、両親の性格が異なるほど、個人の人格の不調和は大きいのである。ショーペンハウアーはこの変えることのできない根本の性格を、カントに倣って<叡知的性格der intelligible Charakter>と呼んでおり、その根底には世界意志、すなわち生への意志をおいている。その時空における現われを<経験的性格>としており、このものも基本的には不変であり、単に偶然的要素や、理知の認識が変化するに過ぎないとする。性格が不変であるかぎりは、行為は、物体が自然法則に従うのと同様に、動機によって必然的に決まるのである。ただし、この性格の認識はa priori(先天的)には与えられていないのであり、したがって、性格も人格も、行為の結果として経験的a posterioriに認識されるほかはないとされる。
自我は何よりもまず、おのれの経験的に知られた性格の把握に努めねばならない。たいていは、遺伝子の混合からなるための、矛盾と対立において現われており、たとえば大胆と臆病、尊大と卑屈、内向と外向、攻撃性と甘え、躁と鬱などの衝動的行為に典型的に見られる。これらの矛盾・対立した性格の中から、行為においてもっとも有利なものを発現させることによって、環境、とりわけ社会環境の中での、人格は選択的に形成されてゆく。どれか一つの性格に偏ってしまうと、環境の中での適合性が失われ、衝突と敵意によって、社会の中で不利な立場におかれる。それを避けるには、いわば自己の性格という手駒を、うまく使いこなすほかはない。さもなければ、そもそもそうした人格転換を必要とする社会環境をぬけだすほかはないだろう。
自己の性格の多様性から行為の多様性が生まれ、それらに応じて心情の常ならぬ動揺が生まれる。自己にとってどの性格が最重要であり、どの性格を抑えるべきであるかという判断の目安となるのが心情のあり方であり、その心情もまたどのような動機によって生じたものであるかによって、また評価が分かれるのである。卑劣なことをしたことによって心情が乱れるならば、卑劣な性格を呪うであろうし、しかしそれが自己の利益にもとづくものであったならば、それをよしとする判断が生まれ、心情も説得によって落ち着くであろう。こうした多様な性格ないし性質や、心情の動揺を、理知によってコントロールするためには、ある一定の原理がなければならない。それは自我にとってもっとも根本的な原理でなければならない。同時に、世界意志に属する叡知的性格のなかでも、最も強力なものでなければならない。それはすべての性格の根源にあるものであり、すべての性格を貫いているものでなければならない。すなわち、それはこれまでにも生への意志の本質であるとした個体保存と、類の存続の意志にほかならない。この両者が性格の根源なのである。
自我にとって、さしあたり問題となるのは個体保存のみであって、類の存続は個の独自性の解消へと至るのであるから、ここでは前者をおもに考察する。個体保存の本能は、これを心理的に言い換えれば<自己愛amour propre>と言ってよいだろう。自我にとっての根源的性格は自己愛である。この自己愛を満たすかどうかが、あらゆる行為、あらゆる心情の基準となるのである。この自己愛を満たすために、自我はあるときには尊大に、あるときには卑屈に、あるときには大胆に、あるときには臆病に、あるときには攻撃的に、あるときには甘えるのである。もし自己愛がおのれの肉体を嫌悪したとしても、どこかでその自己愛を精神的に満たそうとしているのである。このことを忌憚なく探究したのが、フランスのモラリスト、ラ・ロシュフーコーである。
「自己愛はあらゆる追従者のなかでも最大の者である。(2)
自己愛は世間で最も有能な者よりもさらに有能である。(3)
愛はその結果の大多数から判断すると、友好よりも憎しみに似ている。(72)
真実の愛は幽霊のようなものである。誰もがそれについて口にするが、それを見た人はめったにない。(76)
自己愛が善意の鴨にされているように見える場合がある。他人の利益のために労する時に、自己愛はおのれを忘れているようにも見える。しかしながら、それは自己愛がその目的を達するために取る最も確かな道なのであり、与えるという口実のもとに、利子を取るようなものである。それは結局、巧妙で、微妙な仕方で世間を意のままにすることである。(236)
利害はあらゆる種類の言葉をしゃべり、あらゆる種類の人格を演じる。利害に関心のない人の振りさえするのである。(39)
利害は人を盲目にしもすれば、他方人の目を開かせる。(40)」
――ラ・ロシュフーコー「箴言」より
(L'amour-propre est le plus grand de tous les flatteurs.(2)
L'amour-propre est plus habile que le plus habile homme du monde.(4)
Si on juge de l'amour par la plupart de ses effets, il ressemble plus a la haine qu'a l'amitie.(72)
Il est du veritable amour comme de l'apparition des esprits: tout le monde en parle, mais peu de gens en ont vu.(76)
Il semble que l'amour-propre soit la dupe de la bonte, et qu'il s'oublie lui-meme lorsque nous travaillons pour l'avantage des autres. Cependant c'est prendre le chemin le plus assure pour arriver a ses fins; c'est preter a usure sous pretexte de donner; c'est enfin s'acquerir tout le monde par un moyen subtil et delicat.(236)
L'interet parle toutes sortes de langues, et joue toutes sortes de personnages, meme celui de desinteresse.(39)
L'interet, qui aveugle les uns, fait la lumiere des autres.(40)
―― Maximes par La Rochefoucauld)
自己愛はエゴイストにとっての、他者や社会に対する基本的倫理の原則であると言える。自己愛がエゴイストの、というよりはあらゆる人間の行動の原則であることを認識し、それに適合するかどうかが行動の倫理の基準となるのである。この場合勘違いしてはならないことは、エゴイストはただおのれの自己愛をのみ考慮して行動しては、必ず他者や社会からの反撥や抵抗を受けるのであり、常にあらゆる人間が自己愛の持ち主であることを考慮しながら、おのれの自己愛を充足させることに努めるのが、そもそも<倫理>の意味なのである。そこにロシュフーコーが描いたような、さまざまな自己愛の姿が生まれるのである。
自己愛はすでに動物において顕著に見られる。動物が求めるのは、つねに自己自身の快適さである。幼獣は飢えに襲われれば、その充足をひたすら他者に求める。決してそこには感謝などはない。親は子育ての中に自己自身の心情の本能的快適さを求めている。たとえ親の本能が類的意志にもとづくとしても、その現われ自体は自己愛そのものなのである。いわば動物は本能的にエゴイストであり、そのエゴイズムを類的意志が巧妙にあやつっているのである。人間もまた基本においては動物であるから、この無意識のエゴイズムが、その全行動の基礎となっている。ただ人間においては社会制度の複雑さが、そのことを見えなくさせており、類の意志が個の意志を支配することによって、すなわち道徳や法律や宗教が<超自我>として自我の上に君臨することにより、あたかも純粋な無私の行為が可能であるかのような錯誤におちいらせるのである。もし類的意志が、個の犠牲を要求するならば、個のエゴイズムはすすんでそこに集団への愛としての自己愛を見いだすのであり、自己愛を普遍の愛とすることによって、自己愛の絶対化をはかろうとするのである。これまた、類の意志=全体への意志が、個の自我に仕掛けた巧妙なトリックなのである。神は愛であるという言い方の裏には、私が神であるという自己愛が潜んでいるのである。
とはいえ、単なる自己愛は、自我の全面的充足とはならないことは確かである。自我の中には、他者へと向かおうとするある空虚さがつねに存在している。純粋な自己愛としてのナルティシズムは、つねにある空しさを伴っている。子供のころ、鏡に映ったおのれの姿に接吻してみたものならば、だれしもそのことに気づいたであろう。自我は他者を必要とする、これが身体的自我の宿命である。他者を必要としながらも、つねにその必要とする他者を得られない、このことが自我にとっての大いなる苦悩であることは疑い得ない。兼好のいわゆる、<同じ心の友>は、永遠に得られることはないのである。このことはしかし、自我を自己愛からはなれた純粋自我に向かわせるよすがとなる。釈迦が言うように、すべての苦悩は愛からいずるのである。ここでは、このエゴイストの究極の救済についてはさておき、煩悩の世界でのエゴイストの生き方を、さらに考察する。
他者を求める心の空虚は、世界意志の根源にさかのぼるであろう。もし知性と認識の発達が、世界原理の自己認識のために必要な条件であるならば、世界意志は、あるいはこの場合創造神(デミウルゴス)としてもよいが、自己を顕現しただけでは満足せず、それをなんらかの他者の立場から認識され、承認されることを欲したのだと言えよう。この世界は神の自己顕示であるならば、それを承認する存在が同時に必要なのである。この神もしくは世界原理と、個としての自我が、被造物としてのなんらかの共通の本質を持つならば、自我の自己顕示欲は心の空虚として表われ、その承認者をつねに求めざるを得ないことになろう。子供は回りの大人に対して、自己のしている行為を、つねに<見て、見て>というものだが、それがこの世界の認識の根本原理なのであるかもしれない。
この自己顕示と、承認願望が、自我の強力な欲望であることは、このようにして説明されうるとして、それに対して自我はどのように対処したらよいのか。それらがあまりにも強力であると、自我の独立性がつねに揺らいでしまうことになる。これらの強力な欲望に打ち克つには、他の欲望をもってしては不可能で、すべてが空であるという永遠の視点による諦観が必要になる。この世界、この宇宙そのものが空なのであるという、あらゆる欲望の空しさ、その根源である世界意志の幻影を生み出す力の洞察、それによってのみ克服が可能になる。その意味では、生者は迷いの世界に生き、死者は少なくとも無にやすらっている限り、その迷いから免れている。すなわち、とりあえず死がすべてを解消し、解決してくれる。それまでは欲望に迷いつつ生きるほかはないのであろう。
総体人格と身体
単に人格が形成されただけでは、実人生ではほとんど無力である。人格はそれだけで人間を作るものでも、生命としての全体をなすものでもない。生命の根幹をなすものはなんといっても肉体であり、身体であるからだ。肉体=身体はいわば人間のハードウエアであり、それに対するソフトウエアが、ここで言う総体人格なのである。身体の健康ということは、何よりも人間の生存の基本条件である。それは必ずしも頑健であるとか、特別の能力や力を備えている必要はない。身体・肉体の条件も遺伝的に決定されているので、その範囲で健康の維持、鍛錬や、出来るかぎりのセルフメディケーションをおこなえばよいのである。子供にはこれは困難であるが、大人としてはまっとうな人生を送るための、最低限必要な心がけである。エドガー・アラン・ポーも、この作家としては意外に思われようが、身体の健康のためのスポーツを、人生の幸福の最初の条件に挙げている。
「彼は幸福に関して四つの基本的な原理、または正確に言えば条件を認めたに過ぎなかった。彼が第一の条件と見なしたものは(風変わりにも!)、野外における気ままな運動という単純で、純粋に身体的な条件であった。その他の手段で得られる健康などは、ほとんどその名に値しない――と言うのであった。彼は例として、狐狩りをする人の爽快感をあげ、また大地を耕すものたちについて、一階層として、彼らだけが他のものたちよりもずっと幸福であると見なした。」
――E・A・ポオ「アルンハイムの地所」より
(He admited but four elementary principles, or more strictry conditions, of bliss. That which he considered chief was (strange to say !) the simple and purely physical one of free exercise in the open air. “The health,” he said, “attainable by other means is scarcely worth the name.”He instanced the ecstasies of the fox-hunter, and pointed to the tillers of the earth, the only people who, as a class, can be fairly considered happier than others.
――E・A・Poe: The Domain Of Arnheim )
自己の身体・肉体の世話ということが、この世界で自我が独立的に生きてゆくための第一の条件なのである。そのことをいかに早いうちから学ぶかということが、人生の有利不利を決める。不幸にも、そのことを誰からも学ばなかった青少年は、人生の発端から躓くことになる。自己の身体の世話ということは、何よりも自我に独立心と自信とを与える源であるからだ。もちろん自己の身体には限界がある。その限界を知り、その限界内での自我の発展を図ることが出来さえすれば良いのである。身体の不足や不満足は、いくらでも外の方面で補えるからである。最低限、身体・肉体の衛生と健康に気をくばるだけで十分である。このような身体的基礎の上に、総体人格の統合の可能性が生まれる。
身体はまた、他者に対して直接的関係を持つ、自我の客観的発現であるから、(それ故にこのような自我を身体的自我とするのであるが、)身体に付属するものにも、それなりの注意を払わねばならない。すなわち人間は裸ではなく衣装をまとっており、それが身体的自我の一部と見なされるからである。どのような衣装をまとうかが、また、人格あるいは人となりの表われとされるのである。それゆえに画一的人格を理想とする全体社会においては、だれもが同じ衣装を着ることになる。衣装が人格の代理をするのである。その点では衣装をコントロールすることは、人格をコントロールすることである。それが模倣であるならば、模倣的人格の表われであり、画一的な衣装であるならば、集団的人格、あるいはその中におのれの人格を隠そうとする人格の表われとなる。自己の総体人格に自信をもてるものだけが、衣装に自信をもてると言える。
総体人格と社会
身体を養うためには、現代では否応なしに、経済的社会に身をおかねばならない。かつては自然界が人間の身体を養う場であったが、国家が発生して以来、自我は自然的身体と、経済的・政治的組織である社会の中に、二重に身をおかねばならなくなった。自我は単に身体であるばかりでなく、経済・政治組織の中において一つの単位として存在しなければならなくなったのである。この単位については、最も抽象的な呼び名は<番号>である。自我は、現在ではこの納税番号としての身体的存在でもあるのだ。自我はこの合理的、功利的存在として、自己の身体を養うほかはなくなっている。野獣や神でない限りは、このポリス的存在(zoon politikon)としての人類の宿命を逃れえないのだ。
この自己の身体・肉体を養うという経済活動の犠牲の上に、自我のその他の活動は成り立っている。余裕があれば他者の身体・肉体(家族)をも養うであろうし、肉体以上に人生に価値をもたらすものとしての、精神的営みに時間と労力をさくことが出来る。経済的安定ということは、人生全体にばかりか、総体人格の形成にとって大きな影響力を及ぼすのである。幸福の条件の第一にあげなければならないものなのである。
しかしながらこの経済活動が、総体人格の形成には破滅的影響を及ぼしていることも、世の中の勤労者の姿を観察すれば直ぐに分かることである。それは単に資本主義や社会主義という制度の問題だけではないであろう。その点では人類はこの数千年来、何の変化も進歩も遂げていないのである。人類社会は基本的に、どのような制度であっても、全体主義社会であり、その中で行なわれる経済制度は、利害の争いであり、富者と貧者、勝ち組と負け組の階層社会であることには、大した違いはない。そうした社会全体の分裂、対立と矛盾が、個々の人間の人格に反映して、たいていの勤労者は混乱した人格の持ち主なのである。このような社会で、おのれの身を労働によって養いながら、人格の統一を保ち、総体人格を形成してゆくのは、並大抵のことではないのである。ましてや、生まれながらに、分裂した性格をもちあわせたものにおいてをやである。
エゴイストがこうした不具な社会の中で、おのれの総体人格を守りつつ、独立的に生きていくためには、出来るだけ少なく社会と交渉し、出来るだけ早く類的本能と欲望に支配された社会から卒業することを目指すほかはない。人類社会は、その<叡知的性格>が不変であるかぎり、いかなる制度や、いかなる改革や、いかなる革命によっても、<進歩>することはないのであるから。それは人類史がこの数千年来、<人間>として少しも進歩を見せていないことからも証明されるのである。単なる知識や、科学技術は、少しも<人間>を改良することなく、かえってその根本的性質や欲望を倍増させて示したに過ぎないのであるから。 |
|
|
| 2018年11月28日(水) |
| 紅葉狩り |
 |
 |
 |
毎年晩秋になると、紅葉・黄葉を求めて近く遠くへ出かける。桜やケヤキは、早めに色づいて散ってしまう。モミジのころには、山ではクヌギが、町なかではイチョウが対照的に盛りの色を見せる。紅い葉はアントシアニンが葉にたまった色で、黄色い葉は葉緑素が抜けて、黄色が浮きあがった色であるそうだ。
近くの山中のK湖では、湖岸のモミジが湖面に映える。何年か前に中禅寺湖で見た紅葉ほどではないが、一周すると、光の加減ごとに、間近から、遠くから、楽しめる。墓参の帰りによった公園でも、クヌギとモミジとイチョウが盛りであった。散り敷いた落ち葉もまたよし。ちなみに、サルビアの赤い花が花壇に一斉に咲いていたが、みな葉が小さく揃っている。家で咲かせているのは、葉ばかりがやたらに大きく、虫くいだらけになっているのはどうしたわけか。
 
  |
|
|
| 2018年11月20日(火) |
| 総体人格について(1) |
|
|
|
人格が多重的であることは、これまでにも究明したが、その実践的帰結について、さらに考察する。人格は世界意志(生への意志)に対応する部分と、イデア界に対応する部分とに従って、三分されうることを以前に述べた。一般に知情意と称されるものが、その区分に当たるが、そこでは媒介的部分である心情(Gemuet)によるものが、行為において最も重要であることを説いた。それらの点に関して、若干の補足をする。
人間はその人格の多重性によって、最も低次の動物的衝動から、心情的、理知的昂揚に至るまで、とてつもない階梯の幅を持った心的存在であると言える――通常はその可能性の幅が、なんらかの内的・外的障壁によって、全面的に直接の行為として現われることが妨げられてはいるが。いわば人間の人格は、マルキ・ド・サドとカントと聖フランシスとを、一つの身体の中に同居させているのである。このような人格的複合を、どのようにしてコントロールし、統合的人格へともたらすことが出来るのであるか。これが自我にとっての、行為における、もっとも根本的な倫理的問題(エゴイストの倫理)となるであろう。
もっとも強力な人格の衝動は、性衝動であるとしたが、もっと一般的に、第一の人格はあらゆる本能的欲動において現われる人格としておく。一言でいえば、生への意志そのものの発現である、あらゆる身体的・心的意欲を、その原動力(Ur-Antrieb)としている人格である。心情も、中間の人格としたが、厳密に言えばこれに属するのである。心情は、それ自体ではなんら本質的意欲ではなく、実のところ、意欲の表われを映し出し、質的に計量しているバロメーター(晴雨計)のようなものに過ぎないのである。しかしこのバロメーターとしての心情の役割は、行為の判断において、とりわけ理知が関係する場合に、大いなる効力を発揮する。行為は単に心情、すなわち情念を抑え、コントロールするだけでは成立しない。情念そのものは単なる表われなのであり、それがそのまま行為をもたらすわけではない。行為は情念を判断材料とするだけなのである。ビアスの皮肉にならえば、晴雨計そのものが天気をもたらすわけではない。
とはいえ、自我が自己自身の状態を察知し、または観察するためには、心情におけるおのれ自身の表われを見るほかはない。自我の動物的状態では、自我は情念とともに行動しているといってよい。それは反射的、本能的であり、恐怖は逃避へ、快感は接近へと、すぐさま行為を引き起こす。これが最も効率的な情念の働きであるが、反射的であるために、錯誤や失策におちいりやすい。さらには、無反省であるために、本能のなかでも最も強力なものが意志を支配し、暴発や残虐やの動物的行為へとおもむかせる。こうした行為が、種の持続、個体の保存にとって不利をもたらすゆえに、高等な動物では理知が発達してゆく。理知の発達とともに、自我は情念に対してある距離がとれるようになる。それを情報として見られるようになるのである。
理知的人格はもっとも非力な人格であるとしたが、情念に対してある距離をおくには、理知による反省が必要なのである。種の維持と自己保存の本能に発する盲目的、反射的行為に対して、まず情念による情報の迂回路が生まれ、それに対してさらに情報処理機能である理知が生まれることによって、人格の三機能が確立したといってよかろう。この機能の中でもっとも強力なのは、言うまでもなく、行為の直接の動因である本能的意欲である。心情も、さらには、理知も、それ自体では何の動力も持たないのであり、それらを動かし、発現させるものもまた、生への意志そのものなのである。心情ばかりか、理知も、生への意志をコントロールする本源的力を持たないのであり、その力は借り物なのである。それでは、心情や理性はどのようにして人格的独立性を持ちうるのであるか。単なる道具としての、付随的存在もしくは機能に過ぎないのではないか。
生への意志はこの世界の現象においては、因果的力として働く。生命現象として、もっとも強力な欲求である、食欲や性欲を生み出し、個体保存の原理である身体的自我を生みだす。自我の発生は同時に意識の発生であり、意識において情念は本能と分離し、さらに情念から理知が分離する。この関係はすべて因果的である。結果であるものは、フィードバックの関係においてのみ、原因に対して作用を及ぼしうる。それ自体としては道具でありながら、無意識に対して意識という優位な立場に身をおくことによって、心情も理知も、本能的人格に対して、ある独立的立場を取りうるのである。しかし、それは本源的動力においての優位ではないのであるから、その働きは必然的因果的であるよりも、カントの用語を借りるならば、統制的ないし統御的(regulatif)であるといえよう。形而上学的に言っても、生への意志の優位の立場から、それへの心情や理知の影響は、せいぜい統御的でしかないのである。
理知は理念(イデア)もしくは理想(イデアール)によって、生への意志、そしてそのモニターである心情に対して、あるべき方向へ向かわせることが可能である。その理想は人格の全体的統一であり、それを総体人格(Ganzheit-Person)と名づけておく。理知そのものは、生への意志の道具であるからには、そのような要求を持つことはできない。理知と心情をそのように統制的に働かせようとするのは、反省的自我そのものである。世界意志と根源において本質をことにするものがなければ、そのような大胆な企ては不可能であるからだ。純粋自我は理知と結びつくことにより、そのイデア界における理念の目的的働きによって、おのれ自身の統制的働きを意志に対して及ぼそうとするのである。純粋自我が人格に対して、唯一積極的に働きかけるのは、この総体人格としての身体的自我の統御の要求においてのほかにはない。それによって、少なくとも、この人生における苦悩を軽減し、幸福の実現にまでは至らなくても、我慢できる人生を送ることができるのである。さもなければ、人格の多元性の前に混乱した自我は、絶望と無謀の間で、人生を棒に振るか、マインレンダーのように、禁欲と自殺の間の選択に立たされ、後者を選ぶことにもなるだろう。
心情はこの総体人格の実現のバロメーターとして、つねに、あるべき理想の状態を自我に告げる(古代の哲学者の言うアタラクシア[心の平静])。理知はそれによって取るべき策を講じ、意志に対して理念を掲げるであろう。それにしても、人類や、人類史や、世の中の、あらゆる不合理、暴力や戦争や、悲惨や災禍が、たえず心情を揺れ動かす。たとえ内面の統一と調和が図られたにしても、外からのあらゆる刺激や情報が、それをかき乱すであろう。自我は内に対しては統制者たりえても、外に対してはまったく無力である。かといって、人格の統合をもっとも危険にさらすものは、この世界のあり方そのものなのである。人類愛や共感や集団の利益や国家目的などといったものも、人格の統合のためには犠牲にしなければならない(古代の哲学者の言うアジャホラ[どうでもよいこと])。他我がもし自我と同じものであるならば、すべての自我が総体人格を実現することによってのみ、少なくとも人類の恒久平和は可能になるであろう。それが不可能であるならば、少なくとも自我の自己認識において、その究極に見いだされる純粋自我の解脱において、この世界の解体を目指すほかはないであろう。自我の解脱と同時に、
「われわれはむしろ率直に次のことを認める――意志を完全に廃棄した後に残るものは、だれでもいまだに意志にあふれている者にとっては、もちろん無である。しかし、その反対に、意志が転向し、自己否定を遂げた人にとっては、このわれわれのはなはだ実在的な世界が、無数の太陽や銀河と共に、――無に帰するのであると。」
――アルトゥーア・ショーペンハウアー「意志と表象としての世界(第71節)」より
(Wir bekennen es vielmehr frei: was nach gaenzlicher Aufhebung des Willens uebrig bleibt, ist fuer alle Die, welche noch des Willens voll sind, allerdings Nichts. Aber auch umgekehrt ist Denen, in welchen der Wille sich gewendet und verneint hat, diese unsere so sehr reale Welt mit allen ihren Sonnen und Milchstrassen- Nichts.
----Aus Die Welt als Wille und Vorstellung abt.71 von Arthur Schopenhauer) |
|
|
| 2018年11月14日(水) |
| 続・悪夢の人生 |
|
|
|
過去は年齢を重ねるにつれ蓄積されてゆき、記憶の重荷となっていく。それに対する抵抗として、人は現在に没頭するか、未来にのがれるほかはない。動物は余計な記憶をたくわえないし、未来の意識を持たない代わりに、ひたすら現在に没入できる。現在的な欲求に悩まされることはあっても、過去に責めたてられることはない。日常の約束や予定にしても、それらを結んだり立てたりしたという過去の事実によって、すでに記憶によって責めたてられているのであるが、たとえ記憶がなんら行為を求めないとしても、記憶自体が意識の棘となって、つねに現在に生きる存在である人を苦しめるのである。
過去はたいての人間にとって、愚行と過失と不幸とのかたまりである。特に若年期においては、後年振りかえれば、その記憶は悪夢の連続のように映るであろう。楽しい記憶を少しでも残している者は幸いである。そのような悪夢のジャングルをかきわけて、まがりなりにもまっとうな人生に達したとしても、待っているのは、悔いと羞恥という悪夢の再現である。
人は若年期においては、何ゆえに愚かな人生しか送れないのであるか。若者が馬鹿げたまねをしていても、周囲の大人は笑って見まもるだけで、自分らも若い頃はそうであったと、悪く寛大な態度をとる。たとえ賢い大人が忠告したところで、人生経験の浅い若者は、理解できないであろうし、余計なお世話という反撥を抱くであろう。若者は自ら人生の悪夢を生きていくほかはないのである。そのことに本当に気づくのは、破綻した人生においてか、それを乗り越えて、安定した老年期に達してからである。しかし、そのようにして達した老年期には一体何が待っているのであるか。おのれの人生に対する、悔いと羞恥のほかにはないのである。たいていの老人は、日夜、そのような悪夢にさいなまれて生きているのである。
中年期には、そのような悪夢は酒や色欲やギャンブルなどによって紛らわすこともできよう。若者はエネルギーに任せた暴発的な行為によって、それを忘れようとするであろう。心身的に、sober(しらふ)にならざるを得ない老境においては、すでに過去となったものの、寝ても覚めても、日夜おしよせる人生の悪夢に、何をもって対抗し得るのか。その手段は、基本的に動物と同じであるといえる。
日々をなにかに没頭して、充実させて過ごすほかはないのである。現在の充実によって、過去の悪夢をふりはらうのである。しかしそれによっても、深く刻印された過去は、ちょっとした連想によっても顔をのぞかせる。現在という時は波立ち、苦渋で満たされる。過去はどのようにしても消しがたいのである。ましてそれが深刻な罪の意識であるならば、尋常の方法では対抗できない。かりに過去を何らかの形で償ってみたところで、過去の罪悪の記憶は消え去らないのである。人がゆるそうと、神がゆるそうと、記憶は消えないのである。
時が悪夢をふりはらう、悪夢から逃れる先であったのは、まだ人生の間のあるころである。逃れたと思った悪夢は、何年先になろうと、ちゃっかり存在しているのである。そしてまた未来に逃れる。そして、未来に死という先が見えてきたときにも、やはり逃げつづけねばならない。死が最後の希望になるのだ。死が悪夢からの究極の救済なのである。かといって、自殺が解決であるというのではない。生がある限りは逃げつづければよいのである。これを希望と呼んでよいであろう。人生の罪びとにも希望はあるのである。希望を抱きつつ、現在を充実させる――これ以外に人生の悪夢に対抗する手段はない。そして最後に、死という生命界の最大の秘儀が開示され、救済へと至るのである。 |
|
|
| 2018年11月9日(金) |
| 自我と今 |
|
|
|
自我と今は存在論的に同一であると述べた。そのことをさらに考察する。自我は無時間的であり無根拠であるが、単なる概念でも、先験的認識主観でもなく、れっきとした存在である。そのような自我を純粋自我あるいは超越的自我(das transzendente Ich)と名づけておいたが、その超越性は自我をとことん内観することによって、ネガティヴにもしくは無限背進的に得られるものであった。そのどこまでも後退していく<私の私>を、突如としてある平面で実在化するものが、疑うことの出来ない私の存在である。このアウグスチヌス=デカルト的な反省する私の絶対的存在は、同時にこの今の絶対的存在と重なっている。私の存在は、時間的に今として表象されるのである。
時間において真に存在するのは今でしかないことは、アウグスチヌスが、時間を<魂の延長>と考えたことにも現われている。魂(意識)には現在しかなく、それが過去と未来に伸びることによって、時間概念が生み出されるのである。このことをより厳密に考えた、現象学の時間論をここで参考にする。現象学では、意識における時間の未来方向をProtention(未来予持)、過去方向をRetention(過去把持)ととらえる。今その図式化したものを、多少変更してかかげてみる。(滝浦静雄「時間―哲学的考察」p.157)
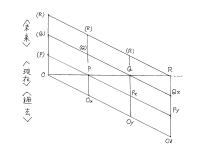
横線のO,P,Q,Rはそれぞれの今であり、Oの時点で考えると、未来にProtentionされていた(P)(Q)等が、今の中を一段ずつ現在から過去方面(下)へと移動(沈下)していく。Oであった今は、PではOxとしてRetentionされる。これで見るように、過去把持も未来予持も、推移する時間の中にはなく、今そのものの中に保持されているのである。保持されながら、O,P,Q等の今の時点において、いわばスライドしていくのである。
この図表で多少奇妙に感じるのは、意識における時間の流れが、ProtentionやRetentionといった、現在的な用語が用いられ、そのように表示されている反面、流れる時というものが、別に設定されているかのように見えることである。今は果たして流れていくのであるか。もちろんこれを単に論理的設定と考えれば問題ないのであるが。つまり、この図で横に流れるように見える<今>の順序も、時間表象にもとづいた、二重の時間ではないとするならばである。
いずれにしても、意識における時間は今から生み出されていく。時の流れは相対的であるから、今が流れに乗っていくと考えても、未来や過去が今の中を流れると考えても、大差はないであろう。問題は時間の中での、今という時点の特異性なのである。この特異性が現われるのは意識においてのみであって、今という時点を客観化すれば、単なる数列や、順序に過ぎないものとなる。意識とはすなわち自己意識であり、すなわち自我そのものである。今の特異性は、自我の特異性と一致している。しかしながら、根本の違いは、自我はその根源において、なんら時間意識を持たないことである。自我は過去や未来によっておのれを意識するのではなく、まさに己自身の存在そのものの意識によって、おのれの存在を(あるいはその不可解性を)端的に知るのである。そのような根源の自我からは、時間は生まれてこないであろう。それではどのような意識が時間を生み出すのであろうか。そもそもそれは意識であるのか。
ここで現象学でいう、超越論的自我(das transzendentale Ich)というもののあり方を考えてみる。これは個々の自我を捨象し、実体概念なども<かっこ>に入れられる。個々の自我ではないにもかかわらず、なおかつ意識を論じることが出来るとされるのであるが、意識に現われてくる現象を考察する場合に、その主観とされるものは、やはり超越論的主観であり、そのようなものが果たして具体的意識とどのようにして結びつくのであるか。ここでカント哲学での先験的(超越論的)主観との類似性を考える。統覚の先験的統一が、認識一般を可能にするとされるのであるが、この統一を行なう先験的主体が認識主観なのであり、そこから意識そのものさえ発現すると考えられる。すなわち先験的主観は意識の存在の条件と考えてよいであろう。もちろんこのような先験主義は、現象学では<かっこ>に入れられているのであるが、時間を生み出す主体を考える時、それが単なる意識ではないことは確かであろう。時間は意識に現われてくるのである。
このカント的な意味での先験的主観は、認識が可能になる条件であって、認識の対象とはなりえない。具体的な自我意識とは別のものであるが、自我意識もまた意識であるからには、この先験的主観と同一の視点をもっているばかりか、この認識主観がなければ発現することがないとも言えるであろう。自我はその意味で目覚めさせられるのである。同じことは、時間意識についても言えるであろう。内的時間を生みだすのは、無意識的機能である先験的主観であり、それゆえに時間は自我に対してあたかも自律性を持つのである(カントの時間論については補説「時間と先験的図式」参照のこと)。
先験的主観は、形而上学的に見れば、生への意志が道具として生み出した認識の機能であり、類の存続と個体保存にとって有利な世界認識を生み出すための、知性のあり方なのである。それが一方では自我=意識を生み出し、他方では時間意識を生み出す。それによって独自の表象世界を構築した知的生命体は、生命界の頂点に達し、宇宙意識にまで到達しえたのである。
先験的主観は認識の根本の形式であるから、それ自体は無時間的であり、存在ではなく単なる機能であるともいえよう。しかしその機能において意識を生み出し、時間を生み出す点において、存在や時間となんらかのつながりを持つであろう。その機能の根本にある形而上学的本体が、意識や時間において発現するための、なんらかの媒体を務めているのである。意識において自我が発現し、時間(及び空間)において世界が発現する。自我が今という唯一の時しか持ち得ないのも、この認識主観の生み出す意識の制約によるであろう。認識主観は個体に備わった機能であるために、個の見地しか持ち得ないのである。個体はその置かれた場所からしか、認識の視点を持ち得ないのである。それは生命の存続にとっては有利であるが、認識自体にとっては大いなる制約である。
しかしながら、自我の見地から見て、時間的に今という制約を持つことは、純粋な自己意識に到達するための有利な条件である。神のごとく、すべての時間がその存在の場であったならば、自我は発現することがないであろう。今という制約の中に発現することによって、自我はその存在の意識をもつことが出来るのである。今が唯一の実在であることによって、その実在にあずかっているおのれを見いだすのである。そして、この世界の存在のように、時間の中に過ぎ去ることのない、無時間的な存在であるおのれを見いだすのである。
自我が形而上学的に、この世界の産物であるのか、あるいは真の意味での超越的存在であるのか、最後に考察する。自我がもし単なる自我意識であって、意識現象と異なったものでないならば、意識を生み出すのが先験的主観であり、このものは生への意志、ひいては世界意志の産物であってみれば、自我を生み出したのは世界意志そのものに他ならないことになる。自我のもっとも顕著な現われである、動物的=身体的自我においては、自我は生への意志そのものであることを、これまでにもくり返し述べた。そこから反省的自我が目覚める時、自我はおのれの内面に向かい、そこに自我の本体とも言える不可解なおのれ自身を見いだし、それが唯一無二の、無時間的かつ無根拠の存在であることを知る。無根拠(Ungrund)であるとは、宗教者はそれをなくてもよい存在者と見なすのであるが、そうした不安ではなく、不可解な存在でありながら、それが存在することの驚異においてとらえられた無根拠である。この意識において、自我はこの世界を超越し、この世界の判定者となりうるのである。
自我は何ゆえにこの世界に発現しなければならなかったか。その条件はすべて世界の側にあり、私自身は何ひとつそれを変えることは出来ない。私自身もまたこの世界の道具として、奴隷として生み出されたのであろうか。そのような自我には自由はない。たとえ私がこの世界の判定者としての地位を与えられたとしても、それがこの世界での存在の代償に価しようか。たとえそれが私の存在の宇宙的使命であるとしても、私の存在の究極的意味ではありえない。自我が真に超越的であるためには、プラトンが概念の実在性のためにイデア界を要請したように、純粋自我のための超越的世界を、いずこかに求めるほかはないであろう。
* * *
補説・時間と純粋悟性概念の図式について
時間は、生命としての人間の意識が生み出したある種の幻影であるということを主張したが、その具体的なプロセスについては、まだ明らかにされてはいない。その一つのヒントとして、時間が認識の先天的形式であることを、その先験的認識論によって明らかにしようとしたカントの、時間に関しての考え方を、「純粋理性批判」から探ってみたい。特に、その先験的図式の理論(Schematismus)が重要であるが、その前に、先験的感性論における、直観の形式としての時間について触れておく。
時間は空間と対比されて、前者が外感の、後者が内感の、形式とされるが、いま空間はさておき、時間が内感の形式とされるのはどのような意味か、<内感der innere Sinn>の意味について考察する。カントは内感について、「心性がおのれ自身、またはその内的状態を直観するもの」(B37)と以外には、特に詳しい定義はしていないようであるが、ふつうに内感と考えられるものは、情念や感情や想像や、さらには臓器感覚や熱などのの内面の感覚、また思考や記憶なども感性を伴う限り、人間の内面として、内感に加えることが出来るであろう。すなわち、すでに対象化された用語を用いるならば、<身体>内部の感覚的意識のあり方である。それに対して<外感der aeussere Sinn>とは、やはり身体表象を用いなければ、正確に区別できない、自己の身体を始めとした、対象化された世界に向けられた感性の内容であるといえよう。先験的感性論の立場からは、すでに成立した対象を扱うわけにはいかないので、あえて定義するならば、内感とは、意識そのものとしての感覚意識であるといえよう。その場合にも、意識が成立するためには、すでにある方向性を持たねばならないので、すなわち最低でも一次元の空間が、そこに形式としてなければならない。その一次元は、同時に時間の次元でもあるので、時間がもっぱら内感の形式であると言うのは、成り立つことになる。二次元三次元の空間が成立するのは、その形式によってすでに対象化された外感、すなわち外界においてである。
時間がこのように内感の形式とされるのは、単に感性直観の特性として考察されるのみではなく、もっと根本的な問題、すなわちこの後「純粋理性批判」において展開される純粋悟性概念、すなわちカテゴリーの問題と関連してくるのである。
感性界の多様な素材を、先験的な総合的統一へもたらして、認識の対象とするためには、単に感性直観の形式である、空間と時間のフォルムだけでは十分ではなく、カテゴリーと称される純粋悟性概念が、それら直観の形式と結びつかねばならないものとされる。問題は、カントに特有な問の形式において、「純粋悟性概念はいかにして現象一般に適用されることが可能であるか」としてたてられる。ここで現象と言っているのは、感性に与えられた雑多な内容のことである。
「今や明らかなのは、一方ではカテゴリーに対して、他方では現象に対して、同種の関係にあり、前者の後者への適用を可能にする、第三のものがなければならないことだ。この媒介的な表象は純粋(すなわちいかなる経験的なものをも含まない)であらねばならず、しかし一方では悟性的(intellektuell)で、他方では感性的(sinnlich)でなければならない。そのようなものが先験的図式である。」(Kritik der Reinen Vernunft B177)
ここで注目されるのは、内界の能動的機能である悟性と、まったくの受動性である外感の中間にある、内感のフォルムとしての時間である。カント自身の説明がつづく。
「悟性概念は多様なもの一般の純粋な総合的統一を含む。時間は、内感の多様なものの、すなわちあらゆる表象の結合の、形式的条件として、純粋直観において、一つの多様なものを先天的に含む。さて、先験的な時間規定は、それが普遍的であり、かつ先天的な一つの規則に基づくかぎりにおいて、(それの統一をなす)カテゴリーと同種のものである。それはまた他方において、時間が多様なものの各々の経験的表象に含まれているかぎりにおいて、現象と同種のものである。それ故に、悟性概念の図式として、現象をカテゴリーのもとに包摂することを媒介する、先験的時間規定の媒介により、カテゴリーの現象への適応は可能になるであろう。」(K.d.R.V.B177-178)
図式は、カテゴリーに従って、分量、性質、実体、因果性、交互性、可能性、現実性、必然性のそれらが挙げられている。それらは、それぞれ時間的継起としての数、時間における連続的斉一的生産としての感覚の度、実在的なものの持続性、また規則的継起としての因果性、同時存在としての交互性、ある時間、特定の時間、あらゆる時間における表象ないし存在、というふうに、すべて<時間規定Zeitbestimmung>として定義される。時間規定とは、時間における存在の三様態である、持続性、継起、同時存在、に対応するものである。時間そのものについては、時間は流れず、時間の中において変化しうるものの存在が流れるとされる。現象においては、変化しないものとしての実体概念に対応する。時間はフォルムであるからには、自ら流れないのは当然である。
純粋悟性概念は、時間において感性的存在を規定することによって、初めて感性界の雑多な内容と関係し、それを統覚(Apperzeptionすなわち自己意識)の先験的統一のうちに、認識可能な対象(Gegenstand)として構成することが出来るのである。時間がこの現象界の成立の根本の原理であるといっても良いほどである。しかし、この現象界の基本的素材である表象を生み出すのは、悟性概念でも時間でもなく、先験的Einbildungskraft(経験的心理的想像力と区別して、構想力と訳される)であるとされる。この構想力は、文字どおりに、Bild(像、イメージ、表象)を生みだす能力であるが、それだけではいまだ対象とはならないのである。構想力によって生み出された混沌とした表象すなわち現象に、認識可能な形を与えるのが、図式によって媒介された純粋悟性概念なのである。このような形式的区別は、いかにもカントの潔癖な、悟性と経験との区別にもとづく。純粋悟性が感性界にタッチするのも、図式という手袋が必要なのである。
しかしながら、その媒介を時間に求めたところに、カントの深い洞察があるであろう。それによって機械的な認識論から、Werdenが可能になるばかりか、表象世界の創造に時間が重要な役割をしていることが看取されるのである。時間は空間的表象と結びついて発現するが、単なる空間では生まれえない、持続や、継起や、同時の観念を現象すなわち表象に対して付け加える。この点では悟性概念そのものとも見なされうるのであるが、空間的直観において表わされ、理解される点において、やはり感性界に属しており、この二重性が、単なる悟性概念とも異なるのである。この両者にまたがり、さらには変化や生成の観念を生みだす基本フォルムである点において、両者よりもさらに根源的であるといっても良いのである。構想力が世界を表象として生みだす能力であるならば、時間は世界を流転させる原理であるといってよかろう。この両者、構想力と時間とが、根源を同じくすると考えることに、特に妨げはないであろう。構想力こそが時間を介して、純粋悟性概念を一気に感性的表象に結びつけるのであると。人間精神(Seele)の、根源的動力としては、悟性や感性は単なる機能と見なされうるであろう。構想力の根底には生命の働きがあるであろう。客観的に言って、認識をつかさどる脳髄は生命の産物なのであり、その現われである人間精神は、生命の欲動によって動かされているのである。この生命が、自己に都合のよい表象界を生みだすにあたって、時間の形式を原理とする構想力の働きによって、悟性概念を駆使しながら、感性界の雑多を、現象としての統一的世界へとまとめあげているのである。その結果、実在界には存在しない、変化や生成といった現象を、生命界特有の世界のあり方として構成したのである。
カントの先験的認識論を援用したこのような考え方には、反論もあるであろうが、カント自身は、さらに果敢に、この自然界(Natur)に対して、法則を与えるのは人間精神であるとして、コペルニクスの立場におのれをなぞらえたのである。カントは現象界をNaturとしているのであるから、この言い方は当然といえば当然である。自然の根底に有るものは、人間精神には知り得ないのである。それにしても雲霞のような人の群を見ていると、これらの貧弱な脳髄の持ち主たちが、それぞれに自然に法則性を与えて、おのれの世界を構築しているのだとは信じられないであろう。天上なる星ぼしの運行が、それ自身の法則によってでなく、人間精神の与えた法則にしたがっていると考えることは、確かにめざましい発想の転換ではあるが、<汝自身を知れ>の哲学の原則に反しているであろう。人間精神の中に、ある永遠なるものを認め、それとの合一をはかった古代の哲学者はより謙虚であったといえる。カントはしかし、純粋理性批判の範囲においては、経験の批判、すなわち経験における自然科学的認識の確立、の範囲を出でなかったといえよう。それ以上に、形而上学的原理を(その<越権>の批判以外には)立てることをしなかったからである。フィヒテのような学説は論外であったのである。 |
|
|
| 2018年11月3日(土) |
| 秋バラと柚子の里 |
 |
 |
 |
先月の終わり、山裾のバラ園に秋の薔薇を見に行った。薔薇は春・秋咲くそうで、秋バラは春に較べると、やや閑散として咲くが、陽が差すと一面に香りが漂う。春と違って実をつけている。
帰りに回り道をして、柚子の実る、小さな流れに沿った散策路を歩く。ほんの小さな滝がかかっている。滝の入りという地名であるが、もとは山奥にある修験道の三滝への登山口であったようだ。柚子の里と言うだけあって、柚子畑には黄色い実がたわわに実っている。名残りのコスモスも咲いている。
   |
|
|
| 2018年10月31日(水) |
| 時空とは何か・再論 |
|
|
|
時空について無との関連で論じたが、元来は問題の難しさから、それ自体で考察すべき課題である。あらためて時空について考える。
時間と空間は、今日の物理学では、時空連続体として、不可分のものとして扱われる。そもそも空間については比較的に理解しやすく、大体において常識が通用するのであるが、時間そのものとなると、空間概念もしくは表象を通じて、具体性を与えられてきたのである。ある表象が現在であるか、過去であるか、または未来であるかという判断は、単に表象の性質であるばかりでなく、それらを時間系列に並べることによって、初めて判断がつくことである。もしそうでなければ、どれが先(前)で、どれが後かということは、単なる論理的関係に過ぎなくなる。論理的関係は、前件とか後件とかいうことが言われるが、それは必ずしも時間的に推移する事柄である必要はない。単なる思考上の規則に過ぎないのである。それは思考の方向を表わしてはいても、その点では思考の流れではあるが、流れそのものではないのである。マクタガートが言うように、流れそのものとしての時間は、また別のものである。
この流れを表わすために、空間表象が用いられる。時間は過去から未来へ流れるものとしてであれ、未来から過去へ流れるものとしてであれ、直線で表象される。たとえ天体の運行や、時計のディスクによって表象されるにせよ、やはり線には違いない。単なる線が何ゆえに時間を表象しえるのか。ここに変化とか生成・消滅とかの、表象もしくは概念が結びつくからである。それらはまた、運動の概念と切りはなせない。変化と運動、それらがなければ、そもそも時間は、線としてであれなんであれ、表象し得ないのである。表象し得ない時間として、ベルグソンは<純粋持続>のようなものを考えているが、そもそもどのような概念なのか。概念であるとすれば、なんらかの表象に還元できるので、いわば現象に対する物自体に当たる、時間現象の本体としての<時間自体Zeit an sich>のようなものであろうか。そうであるならば、それがどのようにして現象し得るのか、あるいは客体化し得るのか。そもそも時間は本体的な存在なのであるかどうかが、問題となろう。
物理学では、時間は宇宙生成において、空間とともに発生したものであるとされ、物理的法則もしくはその条件なのである。しかも空間とともに伸縮し、物質的なふるまいを見せるのである。先験的認識論では、時間は直観の多様がその中で統覚によって把握されるための内的形式にほかならない。どちらの立場でも、時間は絶対の存在物ではない。時間は異なった宇宙、または異なった知性においては、存在していなくても良いのである。それにしても、この宇宙、または人間知性において現われる時間とは、どのようなものか。すでに述べたように、変化や運動と時間の概念は切りはなせないのである。変化が知覚されるためには、時間における過現未の判断がなされていなければならない。これが論理的関係でないこともすでに述べた。しかしある種の関係の概念であるとはいえよう。それが今あること、すでにないこと、これからあること、の前後の順序で理解されることによって、独特の時間判断が生まれるのである。あるいは、今あることは、あったことになり、いまだなかったことが、いまあることになる。表象の関係はどのようであれ、時間的順序の判断が、この世界の生々流転を言い表わしているのである。ここで基準となっているのが現在である。
時間がもし本体的存在ではなく、単なる現象(あるいはその先験的形式)であるとするならば、その解明の鍵は、<今>にあるといえよう。今のみは移り行かないからである。万物は流転しても、ひとり今のみは、現存する。今は刻々時間によって移動するではないかと、反論されよう。これに対しては、今とはなんであるかを掘りさげる必要がある。人間知性にとって、時間の中で唯一実在と言えるのは、現在のほかにはない。今私が存在しているこの時が、私の唯一の存在の時なのである。もし私が今を失うならば、それは私の存在の消失を意味する。逆に、私が存在しつづける限り、今は失われることはない。私の存在と今とは、存在論的に同一なのである。この今ある私の確固とした実在性・現実性、それらが失われたものが過去であり、いまだないものが未来である。それ故に私は、私と同一でなくなった時間への愛惜と執着を抱き、いまだ同一でない時間への憧憬や願望を抱くのである。
私はなぜこの今に充足せず、過去に執着し、未来に希望を抱くのであるか。それは単に私の認識主観の問題ではないであろう。そのようにして、過現未の時を生みだすのは、私の認識の根源に生への意志が働いているからである。生への意志、すなわちその現われである生命は、類の存続と個体保存との二大原理によって、太古から連綿と存続をつづけるある種の物質の連鎖反応による現象である。生命そのものはその統一的組織によって、自然界一般よりもエントロピーの低い状態なのであるが、個体生命はその物質循環によって、やはり最終的にはエントロピーを増大させて死にいたる。そのような生命のあり方は、唯一の実在の時である<今>の中に、物理的自然界には存在しない、ある方向性を生み出すものと考えられる。生命にとって前にある状態を保持し、後にある状態を予測することは、連鎖反応を持続するための有利な条件である。とりわけそれが意識に反映することによって、不可逆的な時間意識の根源となるのである。
今という実在の時を私が持つのは、世界そのものの事情ではない。世界には、そのような唯一の実在の時としての現在などは存在していないからである。今はいたるところにあって、どこという一時点をもたないのである。この今が私にとって実在であるのは、単に私にとっての事情に過ぎない。その事情が、私にとって時間を要請させるのである。私の意識が、私の主観が、過現未をこの世界に構成するのである。その根底においては、私の意識も、私の主観も、生への意志によって支配されており、その生命の都合が、時間そのものを生み出しているのである。
時間が生命の産物であるならば、この宇宙における時間とはなんであるか。不可逆的時間は、自然界にも存在しているではないか、と反論されるであろう。その典型が熱力学第二法則であり、熱の現象は不可逆的であり、エントロピーの増大が時間の矢を生み出している。その他にも、素粒子の世界における対称性の破れや、もし宇宙が加速膨張をつづけるならば、宇宙論的時間の矢も考えられる。さらに生命進化における時間の矢は否定しようがない。しかし、不可逆的現象がそのまま時間の矢であるとするのは、果たして正しいであろうか。現象が不可逆であるということは、そのまま時間の存在を要請するのであるか。時間が存在しなくても、不可逆な論理的関係はいくらでもあるのであるし、もちろん可逆的であってもよい(注*)。たまたま時間においては、その関係がつねに不可逆であるというに過ぎないのである。
*たとえば三段論法をとってみる。
人間は死すべき存在である。
ソクラテスは人間である。
故に、ソクラテスは死すべき存在である。
これを逆にして、ソクラテスは死すべき存在である、から、人間は死すべき存在である、が結論として導出できるであろうか。それにはソクラテスという個物から、人間という普遍概念が直観できなければならないが、これは科学の方法に反している。馬や犬や鳥やの動物の中に、ソクラテスに似た生きものがたくさんいて、それらから人間という概念が抽象されるか、あるいは実在論に立てば、発見されるのでない限り、ソクラテスは人間であるという断定はできないのである。すなわち、それは帰納法であるから、三段論法としての演繹は不可逆的である。
この宇宙にはそもそも時間などはなくてもよいのである。あるいは、そもそも時間などを考えなくても、この宇宙は存在するのである。物理学でいう時空における運動である世界線は、いわば空間の一種であり、今と今をつなぐ一つの次元にほかならない。それは可逆的であり、時間のような一方的方向性を持たない。また、エントロピーの増大や対称性の破れや、宇宙論的矢なども、論理的関係に還元できるであろう。そうであるならば、宇宙はすでに全体として完成した状態で存在しているのであり、そのどこにも特殊な時点というものはないといえる。すなわち変化はおろか、発展も進化もないのである。もし造物主というものがあって、宇宙を創造したならば、始めから完成した状態で、しかも六日間などという中途半端な時ではなく、瞬時にして生み出したことであろう。宇宙は根本において無時間的なのである。無時間的で、かつあらゆる可能性が同時に現実であり、無限の存在として同時に存在しているのである。
この同時性ということは、物理学の否定するところである。観測者ごとにそれぞれの時間があり、同時性ということはありえない。しかし<永遠の視点>から見て、この全宇宙は同時的に、不動のまま、永遠に存在しているのである。それが真の意味でのnunc
stans 永遠の今であると言えよう。この今は、実はこの宇宙的nunc stans にあずかった今に過ぎない。全宇宙を貫く永遠の今があるからこそ、この私の今における存在が不動のままにあるのである。移り行かない時が、私の存在の場であると同時に、全宇宙のあり方なのである。
世界は進化も発展もしない。ただこの世界の段階的構造(Stufenbau)があるばかりである。世界意志は瞬時にして全宇宙の構造を発現させたのであり、それを時間的順序において見るのは、生命の産物である人間知性の都合に過ぎない。宇宙は非歴史的であり、そのことを認識できないのは、私が無数の今の中から、ただこの今にしか存在し得ないからである。しかし、この今の中に宇宙の本質があるのであり、それを洞察する眼が開けるならば、真の意味での永遠の今に参与できるようになるであろう。
* * *
時間は物理的にはある種の空間であると述べたが、次に空間についての考察を加える。空間は次元として考えるのが最も一般的であろう。しかし古代では、空間は空虚(真空)の問題と関連した。空間はすべて物質で満たされているという考えと、何もない空虚であるという説が対立した。デモクリトスやエピクロスの原子論は後者であり、アリストテレスや後にデカルトは前者の立場であった。これは同時に空間における運動の問題であった。物質を全宇宙を満たす基体と考えるか、原子論者のように微細な粒子と考えるかで、空間と運動の考えも異なったのである。後にニュートンが、絶対空間の中での引力の法則を立てたときにも、デカルトが渦動説で対立した。光の伝播に関しても、その媒体としてエーテルのような物質が空間を満たしているものとされたが、マイケルソン・モーレーの実験で決定的に否定された。自然界での空間は、基本的に真空なのである。
現代の物理学では、空間は何もない空虚ではなく、絶えず粒子のわきたっては対消滅をしている、物質の温床のような場所である。さらに空間自身の持つエネルギーが、この宇宙を加速膨張させている原因(ダークエネルギー)であるともされている。このように空間の性質に関しては、さまざまな理論や仮説や発見がなされたが、空間そのものの存在を疑うものはいなかったようである。この点は、その実在性が疑われうる時間と異なっている。そもそも実体としての物質の属性として、唯一<延長Ausdehnung, extension>なるものが考えられたのも、この世界の実質は空間と共にあると考えられたからである。空間を否定すれば、物質もしくは物体は、この世界から消えてしまう。
感覚に与えられている次元は、一次元と二次元であると先に述べたが、それでは知覚において生まれる三次元の空間は、単なる主観的産物なのであるか。これは三次元の運動が可能であることから、単に知覚だけの問題でなく、物体(身体)のあり方であるといってよかろう。この三次元空間が、この宇宙の物質の場であると言える。そして物質は空間的性質を持つ物体として発現する。物質自体は必ずしも空間的ではなく、たとえばショーペンハウアーが定義したように、<作用一般 das Wirken ueberhaupt>であるならば、むしろ時間的もしくは因果的なのである。それが空間に発現することによって、空間の性質を帯びるのである。すなわち限定的、個体的なものとなり、個体間で作用しあう関係に入る。
現代物理学では、物質は空間に影響を与える。物質の質量によって空間はゆがむのである。それが重力の正体である。それは光が太陽のような天体のそばで曲がることと、巨大銀河団による重力レンズの効果などによって、観測的に証明されている。空間は物質の作用を受ける点で、実在的なのである。単なる直観の形式ではない。
この宇宙は物質の世界であるかぎり、空間的構造を持っていることは間違いないであろう。しかも宇宙によっては三次元にかぎらず、もっと多くの次元の宇宙があるとされる。この宇宙でさえ、実は十次元であるとも、十一次元であるともされる。どこかに余剰の次元が畳み込まれているというのである。宇宙とその次元によって、物質のあり方も異なるであろう。あるいは次元、すなわち空間こそが、最も基本的な物質のあり方であり、それによって本来の物質のあり方も決まると言えるかもしれない。始めに空間ありと言うべきなのかもしれない。
先験的認識論が、空間を直観の形式とするのは、三次元までは正しいであろう。四次元以上はその形式を持たないのであり、したがって空間が存在しても、認識にはかからないのであり、きわめて貧弱な形式であることになる。実際に三次元空間が存在する以上は、それは形式というよりも、反映と言ったほうがよいであろう。実在を最も反映しているのが、空間認識なのだ。しかし微妙な点ではさまざまな錯視や錯誤が生じていることは、心理学が明らかにしている。人間の知覚は、実在をそのまま映すよりも、効率的、実践的なのであるから。 |
|
|
| 2018年10月27日(土) |
| 無からの非創造 |
|
|
|
無からはなにものも生じない(ex nihilo nihil)というのは、古代の哲学者の洞察したこの世界の真理である。
「まず第一には、有らぬもの(ト・メー・オン)からは何ものも生じない、ということである。なぜなら、もしそうでないとすれば、何でもが何からでも任意に生じるということになって、種子などはまったく必要でないことになるだろうから。もしまた、ものが見えなくなったとき、それはそのものが消滅して有らぬものに帰したとすれば、あらゆる事物はとうになくなってしまっているはずである。なぜなら、それらが分解されていったさきのものは、有るものではないのだから。」(「エピクロス教説と手紙」p.11-12 岩波文庫)
存在には原因もしくは根拠があるというのが、古代の哲学者一般の一致した見解である。この世界の現象は恣意的ではないのである。ある必然性が、それは運命と同義であるが、この世界を支配している。<存在>もまたそれから免れないのである。「有るものはあり、無いものはない」と、パルメニデスが言うとき、同じ思想がある。そもそも<存在>があって、この世界があるのであり、<存在>がなにも無いところから存在し始めたのではなく、<存在>が無いものに変化することもない。
変化が起こって、なにかが存在しなくなると見ることから、ある種の錯誤が生まれる。いまあったものが消滅するならば、あるいは様態を変えるならば、それは有るものが存在しなくなったことではないか、と考えられるのである。たとえば、足にある痛みを感じていた場合、それが消え去ったときに、その痛みは有るものから無いものに変わったではないかと。しかし、それは単に痛みの感覚が消え去ったのではなく、別の感覚に変化したに過ぎない。感覚そのものは、有りつづけているのである。そうでなければ、痛みが消え去ったことさえ気づかないであろう。
単なる変容は存在の消滅ではなく、いわゆる<偶有性contingens, accidentia>とされるものである。変化する様態は、いわば二次的存在であり、それ自体は確かに消滅して無に帰するものと言えようが、その本体に有るものは有りつづけるのである。しかも、その変化を引き起こす原因ないし根拠とされるものは、少しも変化しない。感覚自体がなければ、感覚の特殊な性質は、生じることも消滅することもないのである。この感覚自体を、エピクロスは原子の運動と捉えている。たとえ痛みは消えても、原子そのものはどこへ消えたわけでもない。痛みとして凝集した原子が、離散しただけのことである。
無からは何ものも生じず、本質的存在は無に帰することはない。これは、自然科学であれ、形而上学であれ、あらゆる学の基本となっていよう。人間知性の根本にある<要請>であると言えるかもしれない。原因と根拠が無ければ、人間知性は何事も思索しえないのである。この要請に対して、二方面からの<無からの創造>なるものの主張がある。ひとつは、キリスト教神学におけるそれであり、いまひとつは今日の科学的宇宙論における一つの立場である。神が無からこの宇宙を創造したというのは、キリスト教のドグマであるが、神なるものをこの宇宙とは別個の、絶対的存在と見なす立場から、この世界の相対的無が対置されるのである。アリストテレスは謙虚に、この世界のfirst mover(第一原因) としての神を設定したが、キリスト教の神は原因ですらないのである。超越的神が、おせっかいにも、この世界を何もないところから存在へともたらしたというのである。その関係は、なんらの直接的原因ではないのであるから、いわば奇蹟のようなものである。神はこの世界を創っても創らなくてもよかった。まったくの神の気まぐれである。もし直接的関係があるとするならば、神は絶対の<有>であるから、有から有が生じるのであるから、それは少なくとも無からの創造ではない。
このような神学的たわごととは別に、現代の宇宙論における無からの創造は、ビッグバンもしくはインフレーション宇宙論において、ビッグバンあるいはインフレーション以前の宇宙においては、物質も空間も時間も、あらゆる物理的原理が存在しない状態があり、そこから、すなわち物理的な無から、宇宙が発生したとするものである。宇宙発生と同時に、それらの物理的特性も生まれたのである。しかし、人間知性が知っている物理的原理が、この宇宙のすべてであるという保証はなく、ただ単に人間知性にとって無に思われる、というだけかもしれないのである。
同じくインフレーション宇宙論からの帰結として、マルチ・ユニヴァース(マルチヴァース)の考えがある。この宇宙は他の宇宙から派生したものであり、またこの宇宙もさらに他の宇宙を生み出していく。親宇宙があり、子宇宙があり、孫宇宙がある。それぞれの宇宙は因果的にはまったく無関係であり、交流することも観測することも出来ない。しかし、とにかくどこかに存在する他の宇宙から、この宇宙が生じたのであるから、有が有を生んだことになる。しかも、宇宙は無限の広さと、無限の時間を持ち、始まりもなく、終わりも無い。インフレーションを無限の時と空間において、無限につづけていくのであるから、無限数の宇宙が際限なく生まれていくことになる。空恐ろしいほどの宇宙の連鎖反応である。ここで思い出されるのは、かつてスェーデンボルグのとなえた段階宇宙論である。
「我が星辰界は、大は即ち大なりといえども、恐らく無限中に有限なる一小球をなすに過ぎざるべく、我が太陽系の渦巻は、更にその一小部を構成す。恐らく、我等の看ると同様なる世界は、外にも無数に、しかもなほ巨大なるものあり。これらに比すれば、我等の世界は、単に一つの点たるに過ぎざらん。」(「天文と宇宙」荒木俊馬著より)
スェーデンボルグの時代の星辰界とは、天の川銀河のことであり、それが外にも無数にあるということを推測しているのである。一千億個の銀河からなるとされる現代の宇宙も、さらに一段階上の、無数の宇宙の世界に包摂された、<一つの点>をなすものであることが想像される。ただこの宇宙からは、上部の段階にある宇宙は考えることはできても、見ることも交流することも出来ないのである。この巨大なレベルにおける存在の連鎖は、宇宙が空間的・時間的に無限である限りは、とどまる果てを知らないであろう。そこのどこにも<無>の入りこむ余地は無い。同じ考えは、ミクロの領域においても成り立つであろう。長さの最小の単位や、時間の最小の単位が絶対である保証はないのである。無限小の世界にも、また限りはないかもしれない。人間の知性は、単にバリオンやその他の観測可能な素粒子をあつかっているだけであるから。あるいは、この宇宙にのみ通用する物理的原理に従っているだけであるから。
* * *
そもそも<無>の観念はどのようにして生じるのであるか。その起源を解明するには、空間および時間の観念が大いに影響しているようであるから、まず時空とはなんであるかを、明らかにしておかねばならない。空間を考えるには、それを次元として捉えるのが解りやすいであろう。人間の感覚もしくは知覚は、基本的に一次元及び二次元であると言えよう。ある感覚が生じる時、たとえばそれが痛みである場合、それが認識主体から見てどの場所にあるかを知覚するには、二次元までで十分である。それがある方向で、ある広がりを持った感覚であることが判ればよいのである。これは幾何学的には、直線および平面である。それ以上の次元は感覚にとって必要ないのである。では、知覚にとって世界は何ゆえに三次元であるか。それはバークレーが明らかにしたように、身体の運動などによって、経験的に生み出された次元である。本来平面である視覚が、奥行きを持った次元として形成されるのは、そこに運動、もしくは変化を伴う運動の感覚がつけ加わるからである。
変化は即ち、アリストテレスが言うように、時間の観念が成り立つための基本条件でもある。運動と変化が、三次元の空間とともに、時間をも生み出すことになる。時間についてはさておき、このように生み出された三次元の知覚の世界が、人間知性の把握する空間なるものである。数学的には三次元以上の高次元の空間も考えられ、実際にその実在も物理的に可能とされている。ともあれこの三次元までの空間が、人間の存在する世界の枠組みであり、それ以外の空間は人間知性には直観できないのである。直観できないことは<無>もしくは空虚と同様であり、かりになんらかの想像力を働かせたとしても、結局三次元的なイメージを出でることはない。単なる認識の限界なのである。
ここで<点>について考えてみると、直線を極限にまで分割して小さくしていった所で、やはり究極の点に到達することはないであろう。もしそこに、もはや大きさを持たないものを、即ち無を、考えるならば、それはもはや空間でも次元でもない。そのような無は、不可思惟性であり、ここでの無の観念の発生とは無関係である。無が観念として発生するのは、空間概念が時間の概念と組み合わさる時である。つぎに、時間について考察しながら、その点を明らかにする。
時間は空間のような次元ではない。少なくとも空間的に表象される時間は、本来の時間ではない。これはベルグソンが明らかにしたところである。しかし時間が表象されるためには、空間的に何らかの<変化>が知覚されねばならない。この変化とはなんであるか。たとえば赤い色が黄色に変わったとする。この変化を認識するには、赤と黄色の二つの表象が、知覚において同時に存在していなければならない。しかも、一方は記憶像として、他方は現在的印象として。この現在的印象と、記憶像との比較において、初めて過去と現在という、観念間の関係、すなわち時間観念が生まれる。時間は、この限りでは、単なる比較もしくは関係の概念なのである。しかし、観念同士の間に、何の違いもなく、あるいは何の変化も生じていないならば、そこに時の経過は認識されない。たとえ純粋持続としての時が存在したとしても、認識主体は時間の存在に気づくことはないであろう。
この変化としての時間観念は、現在を基準とした観念の関係であり、現在を唯一の実在の時とし、過去や未来を、すでに存在して今はないもの、またこの先に存在可能なものとして、一次元の空間に投影することによって成立する。過去はすでになく、未来はいまだない。ここに二重の無にはさまれた、人間の現実存在(Dasein)のありかたがある。ないものがあるものになり、あるものがないものになる。この現実存在の不安定が、無の観念を生み出すのである。そしてその根底には、現在もしくは今というものの不可思議な、唯一無二の実在性・現実性がある。そこで時の観念の基準となる、この今について解明しておかねばならない。
<今>は何によって決定される時なのであるか。あらゆる時点が今であってならない理由があろうか。物理学的には、それは可能であるばかりか、今の特殊性は存在しないのである。今の特殊性を決定するものは自我にあるといえよう。自我のあるところに今が発生し、自我の無いところには今はないのである。それはニュートンの自我であっても、私の自我であっても、誰の自我であってもよい。自我の確固たる唯一無二性が、今の確固たる実在性を決定し、保証しているのである。自我をさらに一般化し、認識主観とするならば、認識主観のあるところ、すなわち認識の行なわれるところに、今が発生し、そこから過現未の時間が成立すると言って良いだろう。これは物理学の主張と一致する。時間は観測者の立場ごとに存在するのであり、同時性ということはありえない。
もしこの<今>の確固とした実在性に時間観念がもとづくならば、ベルグソンが言うような純粋持続としての時間は無くてもよいことになるであろう。時間そのものは実在性を持たないのである。もちろんニュートンのいうような絶対時間はなく、時空連続体としての時間についても、再考が必要である。時間はいま一つの次元であるとして、時空連続体としての四次元がこの物理的世界であるとされる。時間はそれ自体としては空間的表象とは異なるものであるにもかかわらず、空間的に表示されうるならば、単に運動を表わすための便宜的表象に過ぎないものとなる。運動によって時空が縮むということも、時間を空間的に実体化していることになる。このことは運動を時間概念の基本とするかぎりは、そうするほかはないのである。
今という時が、自我の無時間的実在性にもとづくならば、そこから生まれる時間は流れる存在である必要はなく、あらゆる時が、そのまま実在であっても良いのである。変化や運動に結びついた時間を生みだすのは、認識主体の働きであり、科学的にいえば<観測>が時間の流れを生み出すのである。それでは、変化や運動は何ゆえに生じるのであるか。それらを認識主観はコントロールできないし、現われるがままに甘受するほかはないのであるが。すなわち、時間が流れないならば、この世界の生成(Werden)をどのように理解したらよいのか。万物は流転しないのであるか。
必ずしも、流転を考えなくてもよいということである。物理学における時間がそうである。時間は可逆的であり、物理法則は未来から過去へ向かっても成立するのであり、時間は単なる論理的関係に還元できるのである。しかし現実には<時間の矢>と言うものがあるではないか、と反論がなされよう。エントロピーの増大の不可逆性が、その根拠とされる。それは人間の認識自体がエントロピーの法則に従っているからであるかもしれない。人間の認識が時間の流れを生み出すのも、認識そのものがエントロピーを増大させているからであろう。これは単なる仮説に過ぎないが、生成を生みだすのは、人間の認識の側であると言えるかもしれない。パルメニデスやゼノンがこの立場に立っている。変化や運動、すなわち時間は存在しないのである。
世界は永遠のイメージからなるといってもよいだろう。その一つ一つのコマが、一つ一つの今であり、nunc
stans(とどまる今、永遠の今)である。それを実在的に体現しているのが自我にほかならない。自我の無時間性はここから来るのであり、たとえ認識主観が時間を生み出して、世界を流転させようと、自我は永遠の今にとどまっているのである。世界はすでに無限の時にわたって完成されており、自我が存在する限りは、そのどの部分をも映しだすことが出来る。Werdenは幻であり、宇宙は変化することも運動することもなく、永遠に存在しつづけている。その宇宙は無限の多様性をもち、無限の領域に渡っており、すべてが可能態であるばかりでなく、現実態である(注*)。永劫回帰でさえ、永劫にくり返されるであろう。このような宇宙には流れる時間はないのである。同時に<無>ということもないのである。変化も運動もなければ、なにものも無くなることはなく、なにものも無からは生じない。そもそも創造などということもないであろう。時間というものが無ければ、創造もないのである。天地は創造されたのではなく、永劫の昔から存在しつづけているのである。「有るものはあり、無いものはない。」それがこの全宇宙の実相であるかもしれない。
*ライプニッツも無限に多様な宇宙の可能性を考えたが、その中で唯一実在する宇宙がこの宇宙であるとした。その他の無慮無数の宇宙は、神の思念の中の可能性にとどまるのである。神はこの宇宙を最善の宇宙として選択したのであると。現代宇宙論では、この宇宙の存在は単に確率的に稀な偶然によるものとされる。その他の無慮無数の多様な宇宙も実在が考えられている。偶然とはいえ、無限の時と無限の空間においては、現われるべくして現われる宇宙といえよう。
|
|
|
| 2018年10月24日(水) |
| 自我と情念 |
|
|
|
意識は感覚もしくは感性(sentience)をその質料とする働きである。この感覚的意識のなかでも、最も内面的であるといえるのは情念である。この情念という用語は、ほかに感情とか情動とか情熱とか気分とか、すべての内面の感覚の中で臓器感覚や快苦以外の、直接的な自我のあり方もしくは状態を表わすものとしておく。もちろん情念は臓器感覚や快苦の感覚と密接に結びついてはいるが、それらと切り離されて考察することが可能である。快苦や通常の感覚は、感覚器との結び付きが強い。それに対して情念は、思考と同じく、特定の感覚器を持たない。それ故に特別の扱いを受け、魂や霊魂などと呼ばれたりするのであるが、すべての感覚の働きの中心は脳の神経細胞の働きにあり、その点で情念も、さらには思考も、他の感覚と特別違ったものではない。それらは脳の階層や、部位において、区別されるに過ぎないのである。
しかしながら、脳がこのような階層や機能の部位を持つことから、ある種の質的違いが生まれてくる。単なる感覚と情念、情念と思考、情念と意志や欲望との間には、明瞭な意識の区別がある。このことが自我のあり方に密接な影響を及ぼすのである。とりわけ情念と思考との間にはある断層があり、場合によっては矛盾と分裂を起こしかねない。感覚と情念の間にはそのような断層はなく、ポジティヴ(快)であれネガティヴ(苦)であれ比較的スムーズな関係が築かれている。それは本来情念は行為と結びついており、感覚が与える情報に迅速に反応しなければ、そもそもその存在意義が失われるからである。(たとえば、恐怖や怒りや喜びが、対象に対する行動を速めたり、躊躇させたり、逃避させたりするpronpterとなる。)
情念と意志・欲望との関係は、より複雑である。欲動と情念とは時に区別しがたいばあいがあり、また逆に、情念を伴わない意志行為や欲動もある。食欲や性欲は、情念以前のより根源的な生命の働きであるからだ。そこには当然情念との矛盾が起こりやすい。しかし、たいていは情念が譲ることになる。それに対して、もっとも大きな断層のある、情念と思考との間には、共存することが不可能な場合も起こりうる。どちらがどちらを支配する、といったような関係ではないのである。
思考は本来情念や欲動とは無関係な、認識の論理的な働きである。思考がスムーズに働くためには、情念や欲望をいったん離れ、ひたすら思考にのみ意志の純粋なエネルギーを向ける必要がある。情念や欲望を犠牲にしなければ、思考はまともに働かないのである。しかし、このことをなしうるのは、思考そのものではなく、情念や欲動に対してネガティヴに働きうるなんらかの意志の力がなければならない。すなわち、情念や欲動のある勢力を、おのれの味方につけなければならないのである。それはなんらかの利害による誘導であったり(試験に受からなければ落第する、将来有利な地位につくために、などなど)、精神的目的(神の意にかなうため、等とう)であったりするであろう。いずれにせよ、そこに思考と情念の間ばかりか、情念そのものの中に矛盾や対立が生まれるのである。デカルトやスピノザが、知性によって情念を支配しようと企てたのが、実践不可能な、まったくのナンセンスであったのもその故である。
さて、このような情念の他の心的機能との関係であるが、そもそも情念とはどのような意識状態であるのか、そのことを探究してみたい。情念は意識の発生と同時に発現すると考えてよいであろう。なにかの反応として現われるのではなく、そもそも意識と同時に、いわばdefault(初期)状態としての情念が存在する。そのような情念は気分(Stimmung)と名づけられている。特に際立った感情があるわけではなく、ある種の快適さはあるが、際立った快ではなく、どこかに不快が感じられるとしても、際立った苦でもない。なにか特別に刺激するものがあるわけでも、特別な欲動が動くわけでもない。ぬるま湯にひたっているような、ある種のかすかな心地よさである。それを情念の原意識(Ur-Gefuehl)と呼ぶことにする。
自我がその状態にひたっている時には、外界からの刺激にはほぼ無関心であり、特に対象としての意識がなく、外界と意識とが溶け合うような状態にある。とりわけ、内界の状態に、この情念の原意識の状態が特徴的に現われる。自我は、この気分の中に自己自身を包みこみ、その状態そのものが自己であるかのように感じる。そこに自我の完全なる世界、全宇宙があるように感じるのである。そこからふと、自我の眼が対象の世界にそれることがあると、ある異様の感に打たれる。そこに現われているものが、無意味の世界に思われるのである。この無意味の感は、対象の世界にはかぎらない。さらに思惟が働き始める時、そのような思惟によって考えられる概念世界が、いかにも別次元の世界に思われ、現実性を失うのである。自我と一致した気分こそが、自我の本領であり、絶対の価値の世界である。その世界から、自我はどのようにして<追放>され、非我の世界へと投げ出されていくのであろうか。
情念のdefaultの状態では、心はいわば Meeresstille(海のなぎ)の状態にある。そこには騒ぐ風も、波のうねりもない。この心のなぎの中に、ふいに内部からわきおこる衝動や、外からのなんらかのシグナルが、さざなみをたてる。さざなみはたかまり、うねりとなって心をいたたまれなくする。それはなんらかの身体のAktを要求するのである。この絶えざる衝動や、外からのシグナルが、ブルックナーの交響曲のように、心を、すなわち自我を、外へと連れ出すのである。その波やうねりが、意識に発現する、不安や、惧れや、怒りや、喜びなどの情念にほかならない。
情念の原意識においては、すなわち意識が気分と一体化して、そこに自我そのものを感じている時、それは同時に、自我の最初の身体意識であるともいえよう。それは最も漠とした、特にこれという形を持たない、まさにつかみどころのない身体的自我のあり方である。情念とはそのようなものとしての身体なのであり、それについて本質的に言えることは、それがもっぱら感覚の質(クオリア)からのみなる身体であることだ。自我の躍動する内的身体、それが情念の本質である。身体を持った自我は情念とともに、世界に投げ出されるのである。自我はそのような身体としての生命的な宿命をもつゆえに、情念もまたdefault状態にとどまることができないのである。
しかしながら、自我がその世界内存在としての出発点において、<心のなぎ>の状態にあったということは、おのずと自我の帰るべき世界が指示されていると言えなくもない。たぶん、自我のこの Meeresstille の状態は、哺乳類の胎内での状態にさかのぼるのであろう。あるいは、さらには単細胞生物の安定性にまでさかのぼるのかもしれない。いずれにしても、生命は必ずしもelan vitalを本質とするとはかぎらないであろう。本質においては安定性を目指しているともいえるのである。それが普遍的に実現できないのは、生命自体の欠陥ではあるが。
自我は絶えずこの情念のデフォールト状態である<心のなぎ>に帰ろうとする傾向を持つ。この自我自体ともいえる根源的気分においては、すでに述べたように、それ以外の世界は意味も価値も失う。そしてこの状態は、たいていの恵まれた人が幼少年期に体験しているものであり、それが真の<幸福>であることも直感的に知っている。人間ばかりか、高等動物においても、この状態を窺わせる、生の安らぎを観察することが出来る。とりわけ、類人猿において、あたかも哲学的思索にふけるかのような趣を見せる場面に出くわせば、彼らがこの心のなぎにあずかっていることが、容易に推測できるであろう。生命が生の始めにおいて生物にこの心的状態を用意していることは、生の究極の目的が、同じ状態の復元であるという、啓示でもあるかもしれない。そうであるならば、無数の生物が生の始まりとともに、たちまちにして滅びるとしても、すでに一時ではあれ真の幸福を味わっている以上、生が一瞬であれ、百年生きようと、さしたる違いはないということになろう。この弱肉強食、四苦八苦の生命界において、個としての生命に与えられた、自然界の恩寵のようなものであろうか。 |
|
|
| 2018年10月21日(日) |
| 秋の風物 |
 |
 |
 |
近在は里山というほどではないが、低山帯が近いので田舎の風景が楽しめ、四季折々の散策には便利である。九月の半ばには、例年の彼岸花の里に出かけた。K川が湾曲した巾着田という所にある、数百万本もの赤い花を咲かせる、観光の名所である。ここまで人工的に咲かせると、自然というよりは花園である。一つ一つの花はよく見ると、そう気持の良いものではないが、一面赤の絨毯となって敷きつめられると、度外れた色彩感となって、あきるほど堪能させる。まれに白い花を咲かせている(写真、上、中)。
少し離れたK神社で、馬頭琴の演奏をするというので、聴きにいった。この大陸の楽器は、馬のかしらをした棹が特徴で、箱のような胴体に二本の弦を張った、シンプルなものだが、意外と迫力のある音を出す(スピーカーで増音されてはいたが)。もとは馬の尻尾の毛を撚って張ったそうである。その名の通り、馬の走るリズムを出すのに最適であり、面白く聴くことができた。押さえる時は、爪と皮膚の間を使うそうで、いかにも痛そうだが、タコができるまでの辛抱とのこと。演奏者は内モンゴル人だが、おもに日本で活動しているという。
コスモスにはまだ早かったが、十月に入るとあちこちで開花していた。ささやかな畑でコスモス祭りが行なわれていたので、出かける。ほとんど隙間もないくらいに密生して咲かせるので、あまり高くならない。花も小ぶりである。それでも薄曇の陽差しを浴びて、目の保養になる。
そばの神社で獅子舞をするというので、見物した。舞うのは、小学低学年あたりからの子供たちで、女の子は三人派手な赤い衣装を着て、頭に飾り物を載せ、シャーシャーと音を立てる半分に割った竹のようなものをこすりながら歩き、男子は色鮮やかな傘や獅子の装束をかぶって、そろって身をくねらすように舞う。その後を大人たちが単調な笛の音をを鳴らしながらつづく。その行列が社殿の周りを十数回まわるので、さすがに疲れて子供たちの獅子舞は揃わなくなるのが愛嬌。見物人はほとんど近所の人たちのようで、素朴な田舎の祭りである。
資料館の近辺の昔の地形を古地図で探るという、ウォーキングをかねた催しに参加してみた。森の中に大きな板碑が隠されていた。鎌倉時代末期(延慶年間)のものという。畑の中の野道を歩いたり、O川沿いに歩いたり、道々コスモスや、野菊や、黄色い小さな花を一斉に咲かせるセンダン草や、アワダチ草を愛でながら行く。歴史的な説明はほとんど聞き逃していたが、秋晴れの中、これまで通ったことのない道を行く楽しさがあった。
  
  |
|
|
| 2018年10月17日(水) |
| 身体の彼方へ |
|
|
|
この世界が、私の身体の客体化された姿であるならば、何故に私はそれを自在に支配することが出来ないのか。それが独我論的な観念論に対する、最大の反論であろう。筆者は独我論をとなえているわけではなく、私自身が意識において交渉しうる実在的・可能的な世界について探究しているのである。身体とは通常、私が私の意志や判断において、自在に動かしたり使用したりできる範囲のものである。その意味で、道具などが私の身体の延長であるとは言えるであろう。しかしこの物質界、あるいは表象として現われてくる世界のすべてが<私のもの>と言えるだろうか。むしろ、私はこの世界の中で、私ではないものと直面し、その脅威に怯えたり戦慄したりしているではないか。これをどのようにして、私の意識における認識の事実と整合することが出来るのか。
この世界が単なる現象であり、幻(Maya)であるというのではない。もしそうならば、私は好きこのんで幻を生み出す狂人の類であろう。その可能性はないともいえないが、少なくとも私は自発的にそうしているのではない。なんらかの強制力が背後に働いている。その力は私自身ではないのである。古代人はそれを端的に<自然physis>(*注)と呼んだ。それを主観的に言い表わしたものが<世界意志Welt-Wille>である。意識は内的にも外的にも、その力によって支配されている。私の身体は、何よりもまずこの世界意志の客体化した姿(Objekitaet)なのである。私の身体は私のものでありながら、私のものでない。この二重のあり方が身体の本質である。
*「自然とは運動と静止の原因が付帯的にではなく直接的、本来的に内属しているようなものにおいて、そのものが運動したり静止したりする原因となっている何物かのことにほかならない」(アリストテレス「自然学」)。これこそがアリストテレスの自然についての定義である。換言すれば、自然とは、自然的存在者における運動と静止との原因である。かくて、運動を起こす力としての自然とは、自然物をまさに自然物たらしめているもの、ということになる。――今道友信「アリストテレス」p.203-204。
私は私の意志によって、私の身体を動かしていると考える。その動かしている当の力は、しかし実のところ私のものではないのである。それを古代人は必然性とか、運命とか呼んだ。<意志の自由>は錯覚であり、古代人はそうしたドグマを信じてはいなかったであろう。今日の心理学においても、少なくとも意識的判断や行為において、意志の自由はないことが実験的に明らかにされている。意識の発現は、つねに実際の判断(脳内の判断)や行為よりも時間的にわずかながら遅れているのである。人間のあらゆる行為・判断は無意識の働きである、ある力により支配されている。それの働くのは人格の無意識的部分であるから、それは身体に属してはいても、私の意識には関係していない。身体は私が自由にしているのではなく、身体が身体を操っているのである。さらに言えば、意識もまた身体の無意識的働きによって操られているのである。
身体にしてすでに、その働きにおいて私の力の及ばないところで働いているのであるから、まして私の意識の客体化された世界全般においては、私の力の及ぶところはまるでないといってよい。そもそも私は、身体的存在を始めたことによって、すでになんらかの牢獄に閉じ込められているのである。私はそれが牢獄であることも知らずに、私の全世界として拡張し、探究し始めるのである。子供のころ古家に引っ越した時のことを思い出す。家に着いたとたん、興奮にとらわれて、家中の障子という障子、押入れという押入れを開けてまわったが、すぐに尽きてしまい、たいして広くもないので、がっかりさせられたことを思いだす。全宇宙はそれほど狭くはないが、探究に限りがあることに違いはなかろう(人間の情報能力は全宇宙の情報量には及ばないとされる)。この限られた世界、いわば収容所の中で、強制労働についているのが私の身体であるといえよう。
この宇宙は私の身体の客体化、すなわち私の意識の自己疎外における外化の産物であると同時に、身体を生み出したそもそもの力である世界意志の客体化でもあるのだ。それが表象としての世界の、二重の本質である。私は世界意志の産物である世界を、物質の世界(physis)と見なすと同時に、それが私の意識によって成立していることを知るのである。私の意識は、いわばこの世界の現象的存在の、共犯者であるのだ。意識がある所に、世界は現象する、すなわち表象として発現する。意識のないところに世界は、少なくとも表象としては存在していないであろう。それ自体としての世界がどのようなものであるか、自然科学が前提とするような世界は、すくなくとも<概念>としては考えることが出来ても、意識がその中にとらわれているこの世界とはまったく違ったものであろう。そもそも世界は意識を必要としていないのであるかもしれないし、そうならば、世界のあり方にとってこの現象界は、たしかに幻のようなものであろう。この幻のさなかに、自我は自己自身に目覚めるのである。
自我の目覚めをうながすものが、世界のいま一つの本質的要素であるイデアであることは、すでに述べたところである。イデアは単なる思索のための概念ではなく、それが形相因として世界意志を導くことによって、この世界の構造を成立させ、さらに表象における本質として現われることによって<美のイデア>として意志を沈静させる。この契機によって、自我は自己自身への反省へと向かい、そこに超越的純粋自我を見いだすのである。ここに身体から離脱した自我の解放の可能性が開けるのである。それと同時に表象としての世界の解消への道が、少なくとも自我のレベルにおいて、模索されうるのである。 |
|
|
| 2018年10月11日(木) |
| 自我と身体と世界の成立 |
|
|
|
自己探求ということがもてはやされ、それに対する批判も多くなされた。そもそも私とか自我というものに対する社会本能的反撥が、この国には根づいているようだ。自我の探求と言わずに、<自分探し>などという卑屈な言い方にも、そのことが現われている。脳科学者の養老猛氏が、あるテレビ番組で、本当の自分などと言うものは存在しない、今の自分と赤ん坊の時の自分とは、とても同じものとはいえないであろう、というようなことを述べていた。
たしかに今のおのれの姿と、赤子の時のそれとには、天と地ほどの違いがある。しかし自我の不思議は、赤子の時の私の意識と、今の大人になった私の意識とには、ある同一性があり、それが記憶によって連綿とつながっていることである。それは単なる感情移入や共感によるものではないことは、他者の身体内における体験を共有したり、心的作用を受けたりするのとは違って、そこに他者の意識が入りこまないことである。その区別を意識にもたらしているものが、私の身体の同一性であるといえるかもしれない。他者のイメージを、私の過去のイメージから区別することを可能にしているのは、同一の身体において起こったことかどうかという基準の他にはないのである。その点で、他者は私にとっては幽霊も同然である。単なる身体をもたないイメージに過ぎないからである。そうであるならば、やはり赤子であった私は、私そのものであり、今の私と同一の私である。
このように、自我の成立には、身体が大きな役割を果たしているようであるから、そもそも身体とはなにものなのかを、自我および世界との関係で考察してみたい。
* * *
自我はどのように発生するか、それについては幼児期の漠然とした記憶しかないので、その詳細を分析することは不可能である。しかし、幼児期の体験に似た状態を持つことはできる。それは睡眠時の半覚半醒の状態である。感覚の中で最も基本的な触覚あるいは皮膚感覚だけが漠然と残された状態で、意識が途絶えたり浮かんだりしている中に、ある部分の感覚に特に注意がいくことがある。それは温かみでも苦痛でも何でもよい。それは体のどこかに浮かんで感じられる。いや体という意識さえないであろう。どこかの空間に感覚のかたまりがあって、それが私の注意を引くのである。いやそれによって私の意識が目覚めさせられるのである。このどこから生じたとも知れない根源的感覚状態を、幼児期の意識の発生と重ねることが出来るであろう。
感覚の発生と同時に、そこに感覚をこうむっている私の意識が発生する。Der Leidende(受動者)としての自我がそこにある。では私に働きかける能動者Das Affizierendeとは何であるのか。それは意識が明瞭になると同時にあきらかになる。それは私の腕や足であったり、腹部であったり、すなわち私の身体である。しかしそのように構成される以前に、私の意識と身体との関係はどのようなものであるか。
意識が発生と同時に、感覚において自我とそれに対峙する自我を含んだ感覚の部分に分裂することは、あるいはこの分裂の意識が、自我の発生であることは、意識の原体験であると言ってよかろう。この段階においては、能動者と受動者は、はっきりと区別されない。たとえば半覚半醒の状態である痛みを感じたとすると、その痛みの中には痛みそのものと、私の意識そのものとが融合している。目覚めることによって、はっきりとその二つが分離するのである。しかしその分離した段階においても、その痛みが足の痛みであることが分かったときにも、それは<私の痛み>そのものなのである。私自身が<私>と<身体>に分離しながらも、私はその両方にまたがっている。この不可分離の関係が、私の身体の本質的あり方である。
私と身体は感覚において同時に発現するが、その発現の仕方は異なっている。私の意識は感覚そのものをおおっているが、私の身体は私の感覚の部分である。単なる感覚は私の身体を生み出さない、<私>がそこに現われることによって、感覚は私の身体となるのである。もちろん身体は感覚がなくても存在しうるであろう。低温火傷のように、目覚めた時に初めて痛みを感じることもあろう。その場合、私は身体と共に存在していなかったのである。感覚あるいは少なくとも表象がなければ、私は発現しない。私が発現するときには、身体も同時に<私の>身体として存在する。
このように発現した身体は、私が私の意識において、感覚を私の身体としておおいつつむことによって可能となるのであるが、そのことは私の意識が私の身体を生み出すと言い換えてよいであろう。すくなくとも、身体が単なる物質ではなく、私のもの(mein
Eigentum)である限りにおいては。このような働きをする私自身は、感覚によって目覚めさせられはするものの、感覚そのものでも感覚の産物でもない。身体はしかし、感覚そのものであり、感覚の産物であるといえるであろう。すなわち身体とは感覚をStoff(質料)とする、意識の形成物であるといえよう。そして身体とは、私が意識において見いだす、最初の物体なのである。あるいは物体が形成されるための、基礎をなすものである。
身体は未だに私の意識を含んでいる。この意識を排除する方向に働く私の能動的な働きが、私ではないもの、フィヒテの用語を用いれば、非我(Non-Ich)を生み出していくのである。味覚や嗅覚や聴覚は、未だに私の意識を濃厚に含んでいるが、すなわちそれらはまだ私の身体と呼んでもよいのであるが(比較的に客観化した聴覚でも、たとえば耳鳴りは私の感覚に過ぎない)、触覚と較べると、私でないものの感覚的意識が(あるいは刺激の意識が)、受動者である私の積極的な反応によって、かなり明らかにされる。しかし感覚からの自我の排除を、徹底的に推し進めるのが視覚であることは言うまでもない。身体から物体への移行は、生物においては目がそれを完成させる。生命界においては、そもそも感覚器は、膜を持った個体生命の外界との接触のために生まれている。感覚自体が外界からのメッセージなのである。それが客体化へ向かい、それを完成させようとするのは、種の維持・個体保存の当然の成り行きである。人間意識においても、それが反映している。
意識は感覚とともに現われるが、感覚自体は必ずしも意識とは関係しないであろう。生命的には、感覚は本来無意識の機能であるといえよう。感覚は物質の反応そのものであり、生命体においては、それが外界に対するAktとして発現すれば十分なのである。眼を持った三葉虫に、意識は必要でなかったであろう。そもそも意識は、すなわち自我は、どのような必要から感覚に伴わねばならないのか。意識は感覚そのものの機能よりも、時間的にわずかながら遅れるであろうし、効果的な反応のために役立つことはなかろう。生命的にある種のゆとりが、意識・自我の発生のためには必要なのである。それは行動が複雑に、かつある種の知性を必要とするようになる場合である。このような行動をする動物になって、初めて意識の萌芽が生まれ、自我が発生したのであろう。自我が発生することによって身体意識が生まれ、身体と物体との明瞭な区別が可能となるのである。これが動物的・身体的自我のありかたである。
この感覚の本質に則った自我のあり方は、自我を単に感覚的生命のための道具としてしまうが、すでに述べたように、身体を身体として確立させるものが、意識であり自我なのであるから、そこに意識ないし自我の能動性をみることができる。この意識の能動性は、感覚的生命の方向にそったものではあるが、単なる感覚では実現できない、身体表象の形成、物体界の形成へと進むのである。意識は最初に私の身体を見いだし、ついでそれを超越する自己疎外(Selbst-Entaueserung)を行なうことによって物体界を構成し、意識における<私の世界>を生み出すのである。世界は私の表象であるとは、その意味である。これを言い換えて、<世界は私の身体>(*注)であると言ってもよいであろう。私は私の意識において、私の身体を客体化することによって、この世界を生み出すのである。身体とは、この表象世界そのものなのである。私の独自性、唯一無二性とは、この世界の独自性、唯一無二性にほかならない。私はこの世界を、誰の世界と取り替えるわけにはいかないし、できることではない。私こそこの世界なのであり、この世界は私なのであるから。
(*正確に言うならば、Die Welt ist die Objektivation meines Koerpers im
Selbst-Bewusstsein.世界は自己意識における私の身体の客体化である。)
* * *
そもそも意識ないし自我を、世界形成へと向かわせる根本の力は、どのようなものなのか。それは意識ないし自我に本来備わったものなのか。あるいは、ほかからの力を借りているのであるか。感覚を生みだすのは生命的な力であるから、その根底には世界意志が働いているであろう。では、自我もまた世界意志の生成物なのであろうか。意識とその認識の働きも、世界意志の道具として生み出された、単なる機能に過ぎないのであろうか。そもそも、本来認識を持たない盲目の世界意志が、何故に認識を生み出そうとするのであるか。世界意志が自己認識を必要とすると考えるのは、まさに認識者の立場から言えることであり、世界意志がそうした要求を持つとは、必ずしも言えないのである。生命界は圧倒的に無意識に支配されているのであるから。認識機能は生命界での闘争を有利にする、そのことは間違いないが、それが生命自体への反省へと向かうことは、生命そのものにとって少しも有利ではない。まして認識が精神界にまでおよぶならば、生命にとって有害な対立者となるであろう。
ここで二重の視点から、この問題を考える。一つには単なる認識機能である。意識が認識の先天的機能を持つことは、自我の本質とは必ずしも同一ではなく、基本的にその機能が無意識であることにおいて、その原動力を世界意志、すなわち生への意志に求めてよいであろう。自我を駆って世界形成へとおもむかせるものは、盲目の先天的認識への衝動なのであり、カントや現象学が言う、超越論的自我(das transzendentale Ego)の働きといってよいだろう。いまひとつは、実在者としての自我の立場から、世界意志やその認識への衝動とは本質を異にする、反省的・自己認識的意識のあり方である。そこから超越的自我(das transzendente Ego)の意識が生まれる。
超越論的自我は、現象学によれば、<かっこにくくる>現象学的還元の果てに、<残余>として見いだされるある種のFormであり、空虚である。そこから意識の根源の働きであるIntention(志向性)が発現し、Erfuellung(実現、充実)へと向かう。抽象的用語ではあるが、それを世界意志の認識のメカニズムと考えてよいであろう。それに対して超越的自我は、あくまでも経験的認識において発見される実在者であり、ひたすらおのれ自身をのみ対象とする、特別な意識のあり方である。そこから翻って世界を見る時、おのれとは本質をことにする異様な事象の中に投げ出された自身を見いだす。この断絶と孤立の意識から、超越への意志が生まれるのである。この点で、超越的自我は世界意志に対して敵対的傾向を持つ。これを筆者は、世界意志の生み出した世界に対する、判定者としての自我の<宇宙的使命>とも述べておいたが、それは本来、世界意志自体に関わることではないのかもしれない。超越的自我は、ただこの宇宙から<退場>することを願っているのであるから。
このように、自我を超越論的に、すなわち先天的ないし先験的立場から考える場合と、意識の事実から進んで形而上学的、本体論的にとらえる立場とは、その根底においても帰結においても、まったく異なった思想を生むことになる。筆者の対場は言うまでもなく後者である。前者の立場からは世界意志を超越することは不可能であり、そこからはなんらの救済の思想も生まれない。カントの実践理性はいざ知らず、現象学は本来学術としてのみ成立を目指した学問であるから、なおさらである。哲学思想は純粋な学術としてもありうるであろうが、究極的には実践と結びつかなければ、自然科学に及ばないであろう。煩悩を断つために自然科学を研究する人はいないように、単なる学術としての哲学は、なんらの救済も与えないばかりか、かえって煩悩の克服には有害でさえある。もし形而上学に、それらの学術にないなんらかの価値があるとするならば、それが何らかの形で、救済への道の見通しを与えうることにあろう。自我の探究もまたそれを目指しているのである。
|
|
|
| 2018年9月24日(月) |
| 何が幸福をもたらすか |
|
|
|
*生活全般の快:日々の生活の効率化・簡素化。居住の快適。収入と支出・金銭に不安のないこと。
*肉体の快:食欲・性欲の充足。身体の健康のための運動・その他の配慮。
*心情の快:安定した人間関係または最小限必要な人間関係。趣味的・芸術的享楽。音楽・絵画・小説・詩・散策・動植物とのかかわり・旅・歴史・自然界。
*知性の快:思索と探究。科学研究・思想・哲学。
第一の生活全般の快が、最も基本的な幸福の条件であるが、これを実現するために、最も労力を必要とするものであり、このための労働だけで一生を終えてしまうことにもなりかねない。幸いにもこれを得られて、初めてその他の快も十全に得られるようになる。
第二の肉体の快は、第一の快の条件に大きく依存するが、食欲は生命の基本条件であり、これだけは欠かすことが出来ない。衛生と健康がそれに次ぐ。
第三の心情の快は、人間関係によって左右されがちであり、共感が大きく関係する。単なる性欲は、心情において性愛に変わる。人間関係を安定させるには、最小限にしぼるのが良い。それでも、夫婦・親子でも、たいていうまくいかないのであるから、孤独が理想である。芸術的・趣味的享楽を深めるには孤独が必要である。
第四の知性の快は、その他の快の充足の上での、余剰としての探究心にもとづく、知識欲の充足である。これは必ずしも一般的快ではない。
これらの幸福の四条件は、すでに恵まれた年少期に現われており、その場合には、成年後に自らの努力で拡大再生産するだけである。それのできない場合は、すなわち幸福の四条件を知らずに人生に乗り出すものは、あるいは知っていても、みずから作り出せないものは、永遠に幸福を失うのである。
これらの幸福の四条件を満たせないものが、世の中に多ければ多いほど、人の世は不安定である。酒・色に溺れたり、ギャンブル的な経済にふけったり、麻薬的な宗教に救いを求めたり、権力欲に駆られて政治を牛耳ったり、ルサンチマンに駆られて民族間の憎悪や戦争をあおったり、不幸がまさに世の中をさらに不幸にするのである。
いわゆる志とか野心とかをあおる、まさに不安定な心情を人生の意義と見るような幸福論は、他からあやつられた人生観であり、その幸福はもっぱら他に依存するゆえに、真の幸福からは排除すべきである。幸福は自己自身において求めるべきであり、他からの承認や、賞賛や、名誉などによって、左右されるものではない。人から褒められることが嬉しかった小学生ならいざ知らず、自ら幸福の条件を実現するためには、それが心情的に、国家であれ社会であれ、他からの毀誉褒貶によって条件づけられてはならないのである。
幸福の条件を自己自身に見いだすためには、集団や社会や国家や宗教といった、全体への服従を強いる勢力に対して、十分な内的・外的防禦がなされていなければならない。そのためには集団的本能や社会や国家や宗教に対する十分な認識が必要であり、それらの本質を批判的に探究することによって、強力な個人的意志を培わねばならない。
宗教や道徳や義務のようなものを排除するならば、たいていの幸福論がゆきつくところも、おのれ自身において幸福の条件を見いだすことである。神や国家や家族のような全体への奉仕や、義務感への陶酔などは、所詮見せかけの幸福であり、幸福の思い込みであり、あるいは幸福そのものに反しさえする。その条件は盲目的であることだからである。神や国家や義務だけを見すえていれば、それ以外のすべてが見えなくなる。
愛情を幸福の条件とする幸福論は、一面においては、心情の満足において憎悪に勝っているのであるが、やはり他者から愛されることを条件とする限りは、真の幸福を保証しない。自ら抱く愛情もまた、相手が誰であれ、親子であれ夫婦であれ親友であれ、いずれは裏切られる宿命にあるのであるから、幸福の究極の条件とはなり得ない。(それ故に宗教者は、決して裏切られないキリストの愛が必要なのである。)
幸福の四条件は、身体と精神の快を基本としているので、身体と精神の能力の衰えとともに、幸福の絶対量も減ることになる。人間が求めうる幸福には限りがあるのである。幸福は最後に幸福自体を否定することによって、その最後の段階にいたる。もはや幸福を求めないことに、究極の幸福が見いだされる。肉体の快、心情の快、知性の快が、知性・心情・肉体の順で、最小にまで縮小することによって、もはや快そのものの希求が消滅していくであろう。その時、生活全般は最も簡素なものとなり、動物のレベルに近づくであろう。動物は空腹さえ免れていれば、存在するだけで幸福なのである。その存在の快が、人間にとっても最後の幸福である。
その存在の快さえも否定する境地に達するならば、最高の幸福、あるいは幸・不幸を超越した<空無>の域に達するであろう。アタラクシアとかニルバーナと称される境地がそれである。生命が快と苦の連続であるならば、生命を超越する境地に達した究極の<幸福>のありかたである。
|
|
|
| 2018年9月14日(金) |
| 物質とは何か |
|
|
|
ごく当たり前のことに思われて、だれもが疑わないことほど、深く考えると、不可思議この上ない物事がある。この世界の根本の存在と思われている、物質もそのひとつであろう。物質とはなんであるか、すぐさま正しく説明できる人がいるであろうか。日常何の疑念もなく接している、この世界の事物の根本が物質であることを、たいていの人は疑わないであろう。しかし物質ほどとらえがたい、不可思議な存在はないのだ。18世紀イギリスのジョンソン博士という人は、バークレーが物質の存在を否定したのに腹をたて、ステッキで地面を叩いて、これが物質だと言ったそうだが、地面を叩くぐらいのことは夢のなかでもできるので、少しも証明になっていない。ただ単に人間の感覚意識の頑迷さを証明しただけのことである。
素朴に物質をそこにあるものととらえたのは、ミレトス学派の、アルケー(元質)の考えであった。水とか空気とか土とか火とか、とにかくそこにあるものを物質の根源としたのである。さすがに素朴すぎるので、感覚に対する反省から、デモクリトスは、人間の感覚意識で信用できるものと出来ないものを区別した。ロックに受け継がれた、この第一性質と第二性質の区別は、やはり相対的であって、比較的信用できるものとして、形や、固さや、密度や、重さのようなものを基準としたのである。それに対して、色や味や匂いや音は、主観的なものとした。物質は形や固さや密度や重さを持つが、その他の感覚の性質は物質とは無関係としたのである。デモクリトスはもちろん原子論者であるから、第一性質であれ、感覚でとらえたものをそのまま物質としたのではない。原子は見ることが出来ない微小なものであり、それがどんな形をしており、どんな性質を持つかは、単なる思弁的推測に過ぎなかった。
第一性質と第二性質が、感覚の性質である限り、ともに信用できないものであることを明らかにしたのはバークレーであった。物質が形や固さや密度や重さをもったものであるとするのは、単なる感覚意識のたぶらかしであり、それらのものを排除すれば、物質の性質としては何も残らないではないかというのである。ただ<観念idea>だけが存在する。それ以外になにも物質などを仮定する必要はない。形や固さや密度や重さの観念そのものが物質そのものなのだ。だからジョンソン博士か憤ったようには、物質は消滅したわけではない。ただそれらの基体(substance)に、物質などを仮定する必要はないというのである。これが観念論の発端である。この考えを継承したヒュームを経由して、カントは純粋理性批判の体系を作りあげたが、そこでは物質(実体)は一つのカテゴリーとしての概念である。物質そのものである物自体(Ding an sich)はnumenon(純粋観念)として、人間の悟性では捉えがたい存在である。すなわちまったくの空白である。このように物質の本体を神棚に上げてしまったわけであるが、しかし物質<現象phaenomenon>の探究自体は、保証されたわけである。
ちなみに、物質と並んで不可解な存在として、物質以上に曖昧模糊とした<魂>や<霊魂>の存在に関しては、バークレーは疑いないものとしたが、ヒュームは物質と同じくいかがわしい存在として排除した。カントも理論理性においては証明不可能としたが、実践理性で敗者復活をさせた。
カントが保証した現象の探究は、哲学とは無関係に、自然科学が着々と進めていた。自然科学の方法論では、もとから個物の現象と、それらを総括し一般化する概念の使用は、もっとも着実な<自然界>の探究の仕方であった。自然界にはなんらかの本質がある。その出発点は感覚に与えられた個物であり、その基準は主観、客観を問わないのである。もし色という感覚の性質がなければ、誰も光をプリズムにかけようとは思わないであろう。その結果光の波長の概念が生まれる。このように感覚の性質から出発し、概念によって分析的・総合的にとらえられた結果として生み出されるのが、物質という<概念>である。今日の物理学では、物質の根本は、超ヒモという物質界最少の長さ(プランク長さ)を持った弦の振動であるという。それはもちろん、デモクリトスの原子と同様、感覚でとらえられるものではなく、数学的概念であるが、古代原子論のような単なる思弁ではない。
それでは、現代の物理学において、物質の究極の探究は達成されたのであろうか。アリストテレスは、物質(質料
hyle, materie)とエネルギー(energeia)とを区別した。質料はそれだけでは潜勢態(可能態)であり、現実態(エネルゲイア)となるためには、形相(eidos)が内部にあって働きかけねばならない。そのようにして物質の本性(ousia)が生成(エンテレキー)してゆくのである。用語は複雑だが、ここで一番の中心概念は、形相(イデア、エイドス)である。このものがなければ、物質に運動が起こらず、生成も発展もないのである。現代物理学では、物質は質量であると同時にエネルギーである。両者は転換されうる。運動は慣性運動でない限り、エネルギーの交換によってなされる。アリストテレスでは、質料とエネルギーだけでは、運動は起こらないのである。ここでアリストテレスの原因に関する説が参考になる。
原因には質料因(causa materialis)と動力因(causa efficiens)と目的因(causa finalis)と形相因(causa formalis)とがある。質料は素材であり、例えば煉瓦であり、動力因は力の作用であり、例えば労力であり、目的因は何のためということであり、例えば住むための建物であり、そして形相因は、建物の設計図にあたる。ここで運動が起こるためには、そもそもの設計図がなければ、素材も労力も、目的も、単なる潜勢態にとどまっている。すなわち物質の段階にひとしいのである。形相因が、すなわちソフトが加わって、はじめて全体が動き出すのである。物質は、それが何であれ、生成の過程に移るためには、自らの内部にイデアを取り込まねばならないのである。この過程全体を物質と見なしてもよいであろう。現代物理学が、物質を質量とエネルギーの総体と見なすように、そして設計図に当たる形相因は、物理法則と考えられるように、宇宙の初発において、それらは一つのものであった(目的因は人間を初めとした生物以外には一般的ではない)。そこで共通している物質の特質は、質料因、動力因、形相因といった働き(Wirken)の概念である。物質について言えることは、作用・反作用や、エネルギー保存則や、質量=エネルギーの等価性といった、なんらかの原因・結果の関係である。この関係的働きが、最も抽象化された物質の概念であるといえる。ショーペンハウアーが物質を定義して、作用するもの一般(Das Wirkende ueberhaupt)、あるいは因果性そのもの(Kausalitaet selbst)としたのもこの意味である。
「物質は、物自体との関係ではなく、単に悟性の形式への関係から見るならば、客観的ではあるが、細かな規定なしに把握された、活動性一般(Wirksamkeit ueberhaupt)である。なんとなれば、物質的なものとは、その作用の特殊な種類を考慮しない、作用するものDas Wirkende(現実的なもの Wirkliche)一般に他ならないからだ。それ故に純粋な物質は、[感性]直観の対象ではなく、単に思考の対象であり、したがって抽象物である。他方、直観においては、物質は形式と性質との結びつきにおいてのみ、物体(Koerper)として、すなわち完全に特定された作用の種類として、現われる。実体概念の、唯一の現実的、正当な内容をなしている、純粋な物質は、客観化された因果性そのものであり、空間を満たし、時間において持続する。そのようなものとしては、物質は我々の認識の形式的部分に属する。その限りでは、本来物質は対象ではなく、経験の条件である。物質は、われわれの知性の形式によって必然的にもたらされた、あらゆる過ぎ去る現象の不変の基体(Substrat)であり、あらゆる変化の下で絶対的に持続するものであり、したがって時間的に始まりも終わりもないものである。」(Schopenhauer Lexikon: Materie より)
このようにとらえた物質概念からは、原子であれ、クオークであれ、超ヒモであれ、まだまだ具象性、すなわち感性直観の性質を帯びている。ここではパルメニデスとヘラクレイトスの両者が、物質概念を軸にして共存しているかのようである。物質とは具体的なものであるという、感性的存在である人間の度しがたい思い込みが、このような抽象物としての物質に反撥を覚えるのである。せめてクオークに色を付けてみたり、弦楽器をイメージしないと、物質らしさが現われないのである。現代の自然科学の大きな発見の一つに、人間が知っている物質なるものは、この宇宙を構成する物質の総量のわずか4%に過ぎないという、驚愕すべき事実がある。あとの96%は、ダークマターやらダークエネルギーとやらの、未知の物質が占めている。これらの暗黒な物質やエネルギーが発見されたのは、銀河系の重力の異常や宇宙の加速膨張といった、まさに間接的なWirkenによるものであった。正体の分からない間接的な作用が、物質の存在を推測させるのである。あるいは、もしそれが物質の基本的なあり方であるならば、Wirkenそのものであるダークマターやダークエネルギーこそが、宇宙の最も基本的な物質であるといえるであろう(*注)。人間知性のとらえているわずか4%の物質は、感性がとらえた特殊な物質のあり方であるともいえるであろう。
*ダークマターやダークエネルギーの正体は未だに確定的には知られていない。しかし、宇宙の初発において、量子ゆらぎから銀河や星が生まれるためには、バリオンのようなわずかな質量では、138億年経っても、いまだ今日見るようには成立していないのであり、実質はダークマターの引力が銀河や星や惑星や生命を生み出す大本であったとされる。目に見えるバリオンの世界であるこの宇宙は、ダークマターやダークエネルギーの進化に付随する現象であったに過ぎないようだ。いわば大きな池にボウフラのわくようなものである。
自然科学の探究する物質は、高度に抽象的な存在であるが、それが形而上学的な本体というわけではない。基本的に現象を因果的に説明する実在的根拠を物質と名づけているのである。形而上学のように、本体そのものに論及するわけではない。カントが物質現象の背後にあるものとした<物自体>のようなものは、自然科学とは無縁である。そもそも物自体は現象に対してWirkenの関係にないのであるから、<観測>にはかからないのである。ショーペンハウアーもその関係をObjektivation(客体化)としか言い表わせないのである。物質と物自体の関係については、さらに微妙である。
「物質は、事物の内的本質をなす[物自体としての]意志が、それを通して知覚できる状態に入り、直観でき、目に見えるものとなるところのものである。したがって、この意味では、物質は単に意志が目に見えるものとなったものであり、あるいは、意志としての世界を表象としての世界と結びつけるものである。物質は、知性の機能の産物である限りにおいて、表象としての世界に属し、あらゆる物質的存在、すなわち現象において発現するものが意志である限りにおいて、意志としての世界に属する。それゆえ、あらゆる対象は物自体としては意志であり、現象としては物質である。与えられた物質から、それに先験的に属するすべての性質、すなわちすべての直観と覚知の形式をとり除くことができるならば、残りのものとして物自体を得るだろう。すなわち、それらの形式によって、純粋な経験的内容として物質に現われる当のものを。しかしその場合、物質はもはや延長を持つものとも、作用するものとしても現われないであろう。すなわちもはや物質ではなく、物自体としての意志を、眼前にもつのである。
物質におけるすべての定まった性質、すなわちすべての経験的内容は、ただ物質を通して目に見えるものとなるもの、すなわち物自体としての意志に基いている。物質はしたがって意志そのものではあるが、しかしもはや自体(an sich)としてではなく、それが見られるものとなる、すなわち客観的形式をとる、限りにおいてである。客観的に物質であるものは、主観的に意志である。物質は意志のすべての関係と性質を、時間における像として映しだす。物質は直観的世界の素材であり、意志はすべての事物の本質自体である。」(Schopenhauer Lexikon: Materie より)
いささかトートロジーの気味もあるが、ショーペンハウアーにとって、物自体とは、人間の内的本質から読みとれるものである。外界からは類推によってしか得られないのである。それに対して物質は基本的に外界の現象からの抽象であり、この両者を結びつけるには、大鉈を振るわねばならない。物自体は本来物質の形而上学的本体と見なされているのであるから、あるいは純粋な思考の対象としてのnoumenonであるから、その境界は微妙なものとならざるを得ない。物質も物自体も、どちらも高度な抽象概念なのである。この世界の本体が世界意志であるという発想は、物自体と現象との区別から発しているが、物自体に到達しうる唯一の道が、自己意識における意志の不可思議にあることを見抜いたのは、彼の独創であった。そこから同時に、物質の不可思議を探究する道も開けたのである。物質もまた物自体に肉薄できるところまで探究することが可能なのである。
* * *
表象と物質
物質が高度な抽象概念であるならば、ふつうに物や物体と考えられているものは何であるのか。バークレーはそれを単なる観念(表象)であるとしたが、ふつうには感覚の対象と考えてよいだろう。感覚の性質は、第一性質であれ第二性質であれ、物質そのものではないことは、以上に論じた。それらの性質が個物において、あるまとまりをもって現われた物が、普通にいう物体(Koerper,body)である。すなわち感覚の性質あるいは表象において個別化された物質が、いわゆる物であり、物体である。
物体と物質との間にはある種の対応関係がある。いま色彩を例にとって考えてみる。人間の網膜の神経細胞は、赤と青と緑のほかには感知できない。それらに対応する自然界の物質は、光(フォトン)の波長である。可視光域のある波長の幅の光が感知されれば、それが知覚において処理されて、赤という感覚の性質を生み出す。赤の感覚は、光の波長という概念的存在物とは、まったく別のものであり、異なった存在者である。直観と概念というまったく異なった両者が、意識においてなんらかの対応関係において捉えられるのである。この不可思議から、一方は観念論、他方は唯物論という、思想的対立が生まれてくる。自然科学はもちろん後者である。
いま唯物論すなわち自然科学の立場に立つならば、この対応関係が成り立つのは、そもそも感覚器をはじめ、人間の認識機能が、脳神経系という物質的プロセスから成り立っているからである。このプロセスを反映するものが、意識であり、感覚の性質であってみれば、意識や感覚は当然物質に従属する<現象>に過ぎない。意識や自我などといったものも(まして魂や霊魂なども)、単なる脳の機能であり、脳が崩壊すれば運命を共にする。物質以外の本質的存在を仮定する形而上学などは、単なる空想や妄想、もしくは思弁にすぎないものであり、よく言って人類の<願望>の産物である。
それに対して、観念論に立つて反論するならば、唯物論自体が物質という概念を絶対視するある種の形而上学ではないか。概念がそのまま実在であるとするのは、プラトンのイデア論と同様であり、もし謙虚に唯名論に立つならば、概念を絶対視するいわれはないのである。色彩を説明するために、必ずしも光という物質を仮定する必要はない。色彩を始めとするあらゆる感覚の性質、すなわちあらゆる観念は、神が人間の魂に吹き込まれたものであり、それ自体が絶対の存在なのだ(バークレーやマールブランシュの説)。観念論の弱点は、観念の絶対性を保証するために、神への信仰に頼らざるを得ないことである。こうした素朴な観念論でなくても、なんらかの絶対者、絶対精神や自我一般や、などを<措定setzen>しなければならない。唯物論も観念論も、結局のところ、偏った形而上学であるといえる。
ここでショーペンハウアーの物質の定義に帰ろう。物質は<作用するもの一般>という高度に抽象的な存在であるが、同時に彼の形而上学の立場から、<意志が目に見えるものとなったもの>であり、世界の本質は主観的には意志であり、客観的には物質であるとされる。両者をつなぐのは、物自体という概念であり、物自体が客観的には物質として現われ、主観的には意志として現われる。ある種のトートロジーが感じられるのはこの点であるが、これを唯物論と観念論の対立という観点から見れば、同一物が、客体と主体とにおいて分離し、かつ本質において融合しているものと考えられる。すなわち観念論と唯物論の融合が試みられているのである。
物質は世界意志が目に見えるもの(Sichtbarkeit)となる、すなわち客体化(Objektivation)するための条件であって、意志は物質において個物として(すなわち物体として)発現するのである。形而上学的本体である意志は、物自体であり、まさにカントが客観的世界の背後にあって、現象するものとした当の本体である。唯物論は物自体に迫ることは出来ないが、そのもっとも抽象的な物質概念において、意識の内面において発見された本体としての意志と結びつくことによって、物自体との関係を付与されるのである。世界意志は、物質において、その自己客体化を行い、表象としての世界を生み出すのであるが、その条件として物質と、その個別化した物体を必要とするのであるから、その意味で、表象としての世界は、同時に物質の世界であると言っても良いのである。世界は観念であると同時に物質なのである。ここに観念論と唯物論の争いが調停されている。ショーペンハウアーの<神のいない>形而上学の近代性(modernity)と現代性(actuality)がここにも見られる。稀有な形而上学といえよう。
* * *
世界は観念(表象)であると同時に物質であると述べたが、このことを自然科学の立場から考えても、同じことが言えよう。意識や自我が脳の機能であるなら、その機能の発現である意識や自我そのものは、やはり物質の作用の発現にほかならないのである。いやむしろ、作用としての物質そのものなのである。世界の根源のエネルギーが光のエネルギーであるならば、まさに光(フォトン)そのものの発現が意識であり自我である。私という存在はフォトンそのものなのだ。私は物質そのものを、私自身において捉えているのである。主観的に見られた物質が感覚の性質であり、意識であり、自我である。かつてフェヒナーも同じような主張をした。世界はあるがままに客観的に実在するのであると。しかし、この主張が(神なしに)成り立つためには、物質が、あるいは物自体が根底になければならないであろう。単なる実在の主張は、ヒュームのように懐疑論におちいるからである。
観念と物質(実体)が知的存在の認識主観において別個の次元に分かれることは、カントの言うように人間知性の宿命のようなものである。直観と概念、内容と形式といったDikotomieは、世界の本質自体には属していないのである。 一方の側にのみ立てば、偏った世界観となり、それは自然科学も形而上学も同様である。その点では、物質と形相、自然科学と形而上学に同等の価値を与えたアリストテレスが模範である。ショーペンハウアーの形而上学もこの模範に従っている。とはいえ、究極の真理の探究ということが可能であるとするならば、それは単なる自然科学では不可能であろう。単に概念を操作しただけでは、<存在>の神秘は解明されないからである。単なるessentiaからはexistentiaは導き出せない。この中世哲学の失敗を、形而上学はくり返すわけにはいかない。根本の神秘である<世界>や<自我>の存在の謎は、なんらかの経験的・実存的形而上学に委ねられるほかはないのである。 |
|
|
|
|