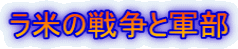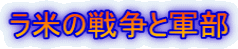1980年代前半までラ米諸国に駐在した経験を持つ方々は、多くの国で軍部の存在感が強く印象に残っておられよう。軍部の役割は国防だ。政権転覆を狙う武装勢力との内戦にも出動する。だが、軍国を思わせるほど軍のプレゼンスが高かったのは、外国軍からの攻撃の脅威があったためではない。内戦対応の側面が強く、多くの国が軍政下にあったことが大きい(別掲の軍政時代とゲリラ戦争参照)。
だが、今日のラ米は、明らかに変わった。常備軍自体を持たない平和憲法下のコスタリカを除くラ米十八ヵ国で、軍政時代を経験したパナマも軍隊を保持しなくなった。軍事費のGDP比を見た場合、ラ米で世界平均を超えるのは革命政権が続くキューバ、ゲリラ戦争が続くコロンビアとその隣国のエクアドル、及び域内最大国として軍備で突出するブラジルや人権侵害で悪名高い軍政を経たチリの5ヵ国だけである。ブラジル、チリ及びエクアドルが概ね英仏並み、いずれも文民統制は取れている。アルゼンチンに至ってはその半分の水準に過ぎない。1980年代の「中米危機」を経験したグァテマラ、エルサルバドル、ホンジュラス及びニカラグアとメキシコは日本よりも低い。ブラジルと並ぶ域内大国メキシコは、元々軍部のプレゼンスが低い。ラ米は軍部の影響力が際立つ、という認識は、根本から改めたい。
その上で、ラ米の軍部が果たした役割を歴史的側面から概観したい。
スペイン人やポルトガル人が新大陸を征服し、先住民を支配したのは、一つにはキリスト教による教化もあるが、軍事力による強権支配があった。独立革命は、殆どの場合独立派と王党派の間の軍事行動を伴い、多くの戦死者を出した。独立達成後、従軍した人たちの多くが創設された国軍に配属されるか、復員してもカウディーリョ配下の武装勢力や大農園の守備隊に入るかなどした。後者が米国の独立革命と異なる点で、黎明期はカウディーリョ同士の権力闘争で内乱が多発した。そうでなくとも、複数国家誕生の結果、国境線を巡る隣国との戦争も起きた。メキシコは米国やフランスからの武力侵攻も受けた。
独立後国家体制が整ってくるとカウディーリョは退場し、軍制は近代化される。ラ米諸国の多くは、ドイツやフランスに近代軍制を学んだ。二十世紀に入ると幾つかの中米、カリブ諸国に米軍が進駐するようになり、ドミニカ共和国、ニカラグア及びパナマでは彼らの指導によって国家警備隊が創設された。国防軍というより国家秩序維持を目的とする軍事組織だ。ドイツは第一次世界大戦を起こし、ナチズムを経て第二次世界大戦に突っ込む軍国化の道を歩んだ。ラ米でも、1930年代から軍部が国政の前面に登場する軍政国が多く現れた。それでも、軍部に親独傾向が強いラ米諸国のどこも、大戦でドイツに味方しなかった。大戦後は、軍制自体に文民統制の思想が強い米国の軍事システムに組み入れられた。だが、東西冷戦を背景に、一旦民主体制に戻っても軍部が自国政権の容共姿勢を危惧し、国政への発言力を高める傾向がみられる。
1959年のキューバ革命後、本来国防を担うべき軍部の仮想敵は、すっかり自国内のゲリラになってしまった。本格的に到来した軍政時代の軍部の役割が、本項で対象としないゲリラ戦争、となる。本項では、独立後のラ米諸国による国際戦争(関係国はパナマ、キューバ、ドミニカ共和国、コロンビア、ベネズエラ以外の14ヵ国)と重要な内戦(但しカウディーリョ時代のそれと、革命戦争、ゲリラ戦争を除く。関係国はチリ、コロンビア、コスタリカ、ドミニカ共和国の4ヵ国)について述べる。

ラ米諸国の軍事力
独立黎明期(1820-50年代)の戦争
ラ米確立期(1860-1910年代)の戦争
二十世紀の国家間戦争
ラ米の内戦
|