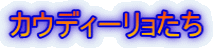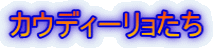|
「カウディーリョ(Caudillos)」は、スペインで1939年から36年間に亘って国家元首の地位にあったフランコ総統が、自らを「スペインの神の思し召しによるカウディーリョ」と呼び習わさせてことで知られる。大統領でも首相でもない国家の最高指導者で独裁権を有する将軍、ということだ。その意味会いで、ポルトガルのサラザール、ドイツのヒットラー、イタリアのムソリーニも同範疇に入る。
ラ米史では定義付けが、別掲のラ米のポピュリズムのポプリスタ(ラ米型ポピュリスト)と異なり、明確ではない。だから、具体的人名になると、研究者や評論家によって様々だ。だが、少なくともフランコ総統と異なり、大統領に就いたカウディーリョは多い。私は、一般的に言われている私兵を持つ武装勢力の頭目で、大衆的人気が有り、且つ権力行使に当たっては家父長的傾向を持つ人たち、を例示したい。主として、ラ米独立革命で台頭し、建国期に活躍した。ある人は大統領として国家体制を固めた。ある人は内乱状態を収め、経済開発と国家統合に大きく寄与した。政治的感覚の持ち主もいれば、我儘な独裁者の域を出ず国民乃至住民に途端の苦しみを味あわせた人もいた。戦争を仕掛け負けて失脚した人もいる。学識豊かな人もいれば文盲もいた。
ラ米人の深層に「マチスモMachismo」の存在がよく指摘される。マチョ(男気、男らしさを持つ人)崇拝思想、とでも言えようか。マチョは、理屈抜きで家族や友人のために命をかけることを厭わない。また男尊女卑ではない。女性を敬い、護り、且つ立てるという響きもある。ラ米に限らず、スペイン、ポルトガル、イタリアなど、ヨーロッパのラテン民族によく見られる。ある意味でマチスモの極地とも言えるカウディーリョは、上記のように一般化しにくい面はあるが、戦略・戦術に長け、部下の忠誠を受け、政治・経済支配層からの信頼が篤く、一方で地方単位、或いは国家単位で権力に就けば、家族、親戚、縁者、郎等、及び友人に対し、経済的、或いは社会的な便宜を図った。いわゆる縁故主義(Clientelismo)が育つ所以であろう。
カウディーリョに対する評価は、欧米の歴史家や評論家では極めて低く、民主主義に逆行する存在、と決めつける人もいる。定義が曖昧なまま感覚的に独裁、圧政に照準を合わせると、そうなろう。十九世紀のラ米知識階級には「スペイン的後進性」の象徴の一つ、と捉え、嫌った人もいる。内乱や内戦の元になるとして、カウディーリョ排除の必要性を訴えた人もいた。だが同時代の大衆人気は高かったし、後世の国民から敬愛される人も多い。
スペイン植民地の独立戦争は、副王(総監)軍が徴募した現地人から成る「王党軍」に対し、独立派が徴募した「独立派軍」の戦いであり、前者の兵士が後者に乗り換えることはよく見られた現象だった。概ね、応募はカウディーリョの私兵団単位だった。戦後復員した兵士は、一部は国軍で採用されたが、多くは戦中に司令官を務めた彼らのカウディーリョを頼った。カウディーリョには正規軍の軍人崩れもいたし、農園主、或いは大農牧場で牧童たちを束ねる人もいた。兵士らは彼らの大農園や大牧場の自警団で働き、或いは運命共同体の一員となり、こと起きればカウディーリョの蜂起に従った。
植民地時代に築かれた大農園、大牧場は、独立革命で既存の保護者を失い、夫々が自助のための武装を必要と考えた。保護者を失ったのは一般住民についても言える。多くの住民がやはり自衛のため武装した。これを束ねる実力者が必要だが、この役割を担ったのがカウディーリョ、と言える。大農園主や大牧場主自身がカウディーリョになるか、他のカウディーリョと契約した。出自が下層だろうが、十分カウディーリョになれる時代背景もあった。
黎明期のスペイン系アメリカ諸国は大体において米国を見習った代表制民主主義を志向した。しかし広大な面積を持つ独立国で、いきなり国家最高権力者を選挙で決める政治体制に変わると、その選挙自体の公平性が証明できない中では、被選出者に対する正統性が必ず問題となってくる。国政を目指すエリートらは政治路線を巡って妥協無き対立に陥った。一人の権力者が選出されると、選出手続きの不正を理由にその正統性を巡り、反対派がクーデターを起こす事件は多発した。ここに才覚に優れたカウディーリョの活躍の場があった。カウディーリョ自身が、自らの意思で、権力獲得にも動いた。自らの兵力を使い、列強の侵攻に向かった人もいた。政権を奪取した後、国内平定と経済発展に努めた人もいた。後世、国家の英雄として敬愛されるカウディーリョは、決して少なくない。
建国期以外にも、カウディーリョは多く見られる。彼らを別記する形で本項を進めたい。

建国期のカウディーリョたち
l建国時の経済社会状況
アンデス諸国のカウディーリョたち
ラプラタ諸国のカウディーリョたち
メキシコ・中米・カリブ
十九世紀末以降のカウディーリョ
|